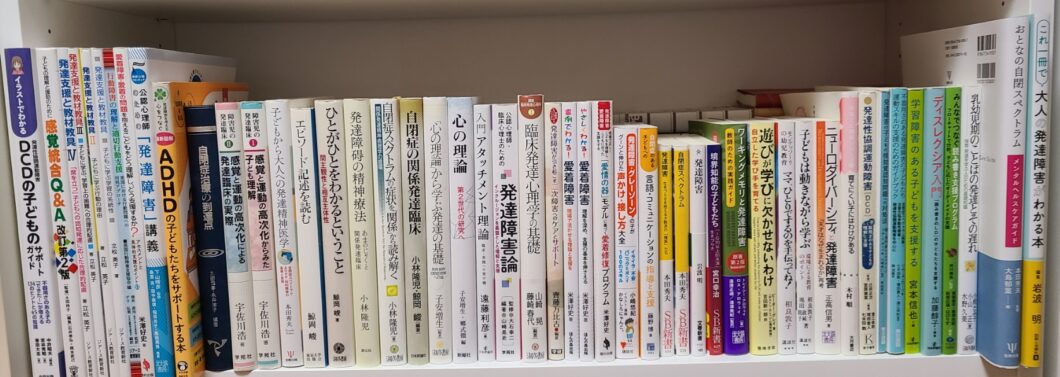-

-
療育現場で子どもを観察する視点-行動科学と間主観性による客観性の違い-
療育現場で発達に躓きのある子どもたちと接していて難しいのは、子どもたちの行動の背景要因や行動動機などです。 例えば、もの投げや癇癪など療育者がその対応に困る行動など、「なぜこうした行動を …
-

-
【発達障害の強弱・重複(併存)について】療育経験を通して考える
日本では発達障害といえば、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、学習症(LD)などが主な症状としてあります。 また、DSM-5(アメリカ精神医学界の診断と統計マニュア …
-

-
学童期の療育で得意なこと・好きなことを見つける重要性について
療育で大切なこととして、学童期の課題では、学習や仲間関係が主なものとしてあります。 中でも、仲間関係から得られる自己有能感はともて大切な発達課題です。 関連記事:「療育で大 …
-

-
発達障害とSNSやゲーム依存について-療育経験を通して考える-
発達障害のある方は、過集中傾向が強いことや、対人関係よりも他のことを求める傾向、そして、二次障害などからSNSやゲームに依存する人も多いと言われています。 SNSやゲームは、使い方さえ間 …
-

-
療育現場で両義性を理解して関わることの大切さについて-子どもの「なる」を育てるために-
2022/06/21 -両義性
「両義性」とは、あちらをたてればこちらがたたずといった相反する状態のことを言います。 療育現場で子どもたちと接しているとこうした相反する心理状態に向き合う場面に出会います。 例えば、一人 …
-

-
療育現場での両義性について考える-自己充実欲求と繋合希求性の視点から-
療育現場で子どもと接していると様々な矛盾を感じます。 例えば、A君が自分一人の力であれもやりたいこれもやりたいと駄々をこねています。しかし、一人ではできないため、結局は大人に助けを求めよ …
-

-
子どもの気持ちがわかる・通じ合うということ-間主観性の視点から考える-
2022/06/19 -間主観性
著者は長年、療育現場で発達に躓きの子どもたちと関わってきています。 こうした子どもたちの多くは、発語がない子、発語が見らえるがなかなか自分の思いを伝えることが難しい子まで様々な人たちがお …
-

-
子どもの思いや気持ちがわかるということ-相互主体性の視点から考える-
2022/06/18 -相互主体性
著者は長年、療育現場で発達に躓きのあるお子さんたちと多く関わってきています。 その中で、子どもの思いや気持ちを理解することをとても大切にしています。 一方で、思いや気持ちを …
-

-
【なぜ自己理解(特性理解)は必要?】大人の発達障害(ASD)の自己理解の必要性
発達障害のある人において、発達特性に対する自己理解はとても大切です。 発達特性にも、様々なものがありますし、特性の強弱も人のよって幅があります。 何が得意で何を苦手としているのか、また、 …