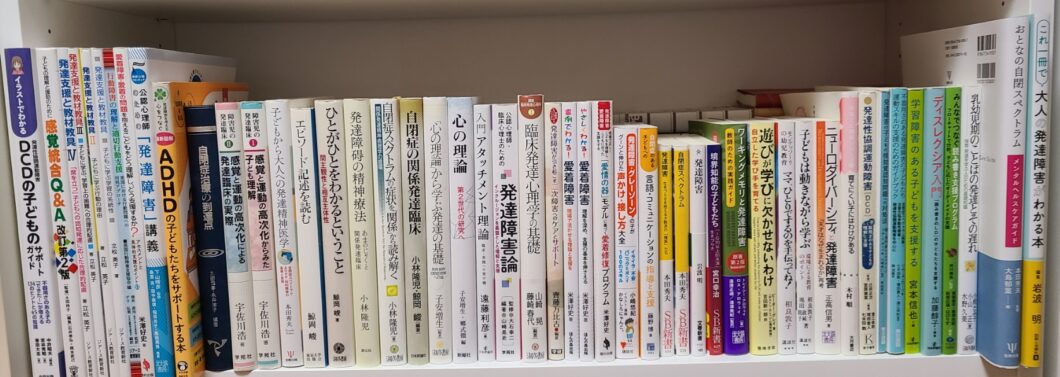-

-
【心の理論と実行機能の関係について】誤信念課題を通して考える
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 心の理論を測る方法として、〝誤信念課題″といったものがあります。 〝誤信念課題″ …
-

-
【心の理論への支援で大切にしたいこと】療育経験を通して考える
2023/04/23 -心の理論
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 心の理論には、一次の心の理論から二次の心の理論へ発達段階があります。 心の理論を …
-

-
【心の理論を獲得する意味について】心の理解はなぜ必要なのか?
2023/04/22 -心の理論
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 心の理論は一般的には、4~5歳頃に獲得すると言われています。 心の理論を獲得する …
-

-
【〝うそ″はどのように発達するのか?】心の理論の視点から考える
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 心の理論にも発達段階があり、一次の心の理論から二次の心の理論へと段階を踏んで人の …
-

-
【〝うそ″と〝冗談″の違いとは何か?】二次の心の理論の発達から考える
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 心の理論には、一次の心の理論から二次の心の理論へと発達していくなど、発達段階があ …
-

-
【人はなぜ〝うそ″がつけるようになるのか?】心の理論の発達から考える
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 心の理論には、一次の心の理論から二次の心の理論へと発達していくなど、発達段階があ …
-

-
【一次の心の理論、二次の心の理論とは何か】療育経験を通して考える
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 これまでの心の理論の研究によれば、心の理論にも発達段階があると考えられています。 …
-

-
【自閉症から見た心の理論の困難さの要因について】視線・表情をキーワードに考える
2023/04/15 -心の理論
「〝心の理論″とは、他者の意図、欲求、願望、信念、知識といった心の状態を推論する能力」のことを言います。 心の理論の困難さは自閉症の人に見られることがわかっています。 著者の療育現場でも …