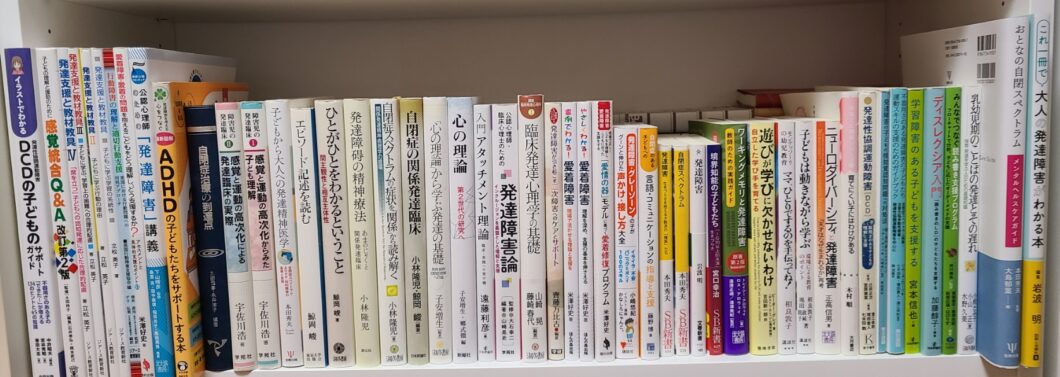-

-
【マインドブラインドネス仮説とは何か?】自閉症の特徴について考える
2023/05/24 -マインドブラインドネス
自閉症(自閉症スペクトラム障害:ASD)とは、対人コミュニケーションの困難さとこだわり行動を主な特徴とする発達障害です。 自閉症には様々な行動面や心理面の特徴があると考えられています。 中でも、心の理 …
-

-
【療育の力を育むために大切な視点について】過去を掘り起こすこと、未来を作ること
2023/05/21 -療育
著者は発達障害など発達に躓きのある子どもたちへの療育(発達支援)を行ってきています。 療育を行っていく中で、様々な能力が鍛えられていくという実感があります。 例えば、子どもたちの状態像を …
-

-
【実践を行うための目標の重要性について】発達障害児支援の経験から考える
著者は発達障害など発達に躓きのある子どもたちへの療育(発達支援)を行ってきています。 療育現場での様々な実践経験を通して、実践をまとめることの大切さや実践をまとめていくために必要なことに …
-

-
【実践をまとめていくために必要なこと】発達障害児支援の経験を通して考える
著者は発達障害など発達に躓きのある子どもたちへの療育(発達支援)を行ってきています。 これまでの実践経験をまとめることは、①経験から意味を見つける、②実践の質を高める、などの意味があると …
-

-
【実践をまとめることの意味について】発達障害児支援の経験を通して考える
著者は発達障害など発達に躓きのある子どもたちへの療育(発達支援)を行ってきています。 長年の療育現場での実践を踏まえて、実践をまとめることの意味について考える機会が増えてきました。 &n …
-

-
【カサンドラ症候群への支援方法について】愛着アプローチを例に考える
2023/05/17 -カサンドラ症候群
〝カサンドラ症候群″とは、簡単に言えば、主にパートナーとの関係において、片方の(あるいは両方の)、共感性の乏しさが原因となって生じる心身の不調のことを指します。 それでは、 …
-

-
【カサンドラ症候群になりやすい人の特徴とは何か?】不安型の人を通して考える
2023/05/16 -カサンドラ症候群
〝カサンドラ症候群″とは、簡単に言えば、主にパートナーとの関係において、片方の(あるいは両方の)、共感性の乏しさが原因となって生じる心身の不調のことを指します。 上記のパートナーの特徴の …
-

-
【カサンドラ症候群の原因としてよく見られるパートナーの特徴】アスペルガー・タイプと回避型愛着スタイルを例に
2023/05/15 -カサンドラ症候群
〝カサンドラ症候群″とは、簡単に言えば、主にパートナーとの関係において、片方の(あるいは両方の)、共感性の乏しさが原因となって生じる心身の不調のことを指します。 上記のパートナーの特徴の …