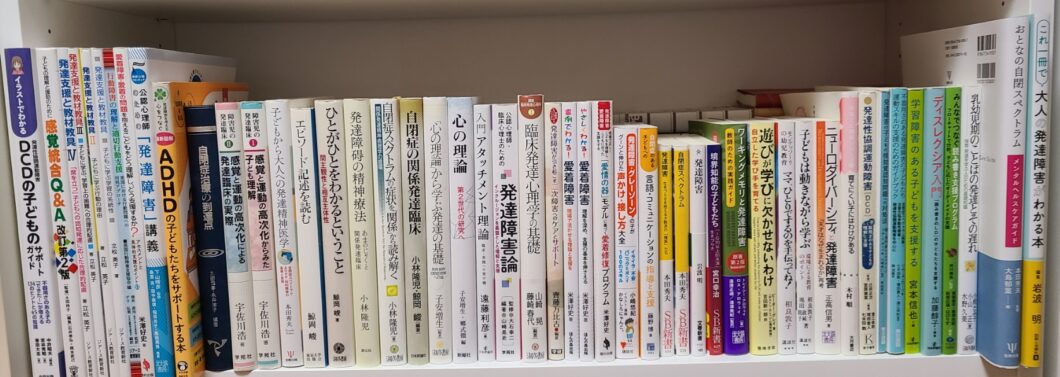-

-
発達障害の分野に関わっていると、障害とはそもそも何であるのか?ということを考える機会が多くあります。 障害というとネガティブなイメージが思い浮かぶかと思いますが、障害があろうとなかろうと、AさんはAさ …
-

-
発達支援の現場で自分の役割について考える【多職種連携の視点から】
様々な職場環境において、自分には何ができるのか?何が得意なのか?などについて考えたことがある方も多いかと思います。 私自身、発達支援の仕事の中で、自分には何ができるのか?と自問自答していた時期がありま …
-

-
最近は福祉や教育、医療において連携という言葉を耳にすることが増えてきました。 その中には、チーム学校など「チーム」という言葉が使われる場合もあります。 発達支援の現場においても多職種連携は非常に大切で …
-

-
療育(発達支援)経験から学んだこと:発達を理解することの大切さ
療育(発達支援)とは、障害のあるお子さんやその可能性のあるお子さんの発達のつまずきや特性などを理解し、自立や社会参加に向けて支援を行うことをいいます。 私が以前勤めていた療育施設の園長先生は、療育のこ …
-

-
2020/05/31 -発達の最近接領域
発達支援に携わる人たちにとって様々な専門性が必要になります。 一方で、関わる子どもたちの状態像や関わるフィールドなどによっても求められる専門性に違いが出てきます。 それでは …
-

-
2020/05/30 -コミュニケーション障害, 発達障害
発達障害の人は、コミュニケーションなど人との会話において難しさを持っていることがよく知られています。また、相手の意図の理解が難しいため、場違いな解釈や意見を述べてしまうこともあります。 こうした特徴は …
-

-
発達支援の現場で、人との関係をつくることに難しさをもつケースがあります。 その中には、愛着に問題を抱えている場合もあるなど、非常に理解と支援をしていく上での難しさを感じます。 一方、大人との信頼関係が …
-

-
職場環境の変化で感じたこと:療育施設から放課後等デイサービスへの移行について
2020/05/28 -放課後等デイサービス
職場環境が変わると、以前とは異なる思考や習慣などを身に付ける必要性に迫られたことを実際に経験された方もいるのではないかと思いす。 発達支援の現場においても、職場環境が変わると、子供たちへの見方や支援の …
-

-
放課後等デイサービスの一日を振り返る:活動において大切にしていること
2020/05/27 -放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、発達に何らかのつまずきのある児童が学校後に利用するサービスです。 ここ最近、全国各地で急増傾向にあります。そして、様々な種類の事業所があり、取り組み内容も異なります。 ですので …