ADHD(注意欠如多動症)とは、多動性・衝動性・不注意を主な特徴としています。
ADHDにも多動性・衝動性が強くでるタイプ、不注意が強くでるタイプ、両者の特徴が混ざっている混合型など様々なタイプがあります。
多動性や衝動性に関しては、「落ち着きのなさ」や「待てない」といった特徴があります。
例えば、家庭だけではなく公共の場で走り回ったり、順番を守れない、人が話している途中で割り込んで話すなどがあります。
著者は長年、療育現場で発達に躓きのある子どもたちと関わってきていますが、その中にはADHD児もおり、上記のような特徴が見られることが多くあります。
それでは、ADHDの特徴として代表的な「多動性」について、どのような対応が必要なのでしょうか?
そこで、今回は、ADHD児への療育について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、多動性の対応について理解を深めていきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は、「司馬理英子(2020)最新版 真っ先に読むADHDの本:落ち着きがない、忘れ物が多い、待つのが苦手な子のために.主婦の友社.」です。
ADHD児への療育:多動性の対応について
以下に著書を引用しながら、〝多動性(落ち着きのなさ)”への対応を見ていきます。
落ち着きのなさ=活発さが活かせる活動をしよう
ルールを明確にし、カードにして活用する
レストランなど騒ぐとまわりの迷惑な場所は避ける
夕方からは静かな活動をさせて寝るための準備を
以上が、著書を引用した多動性への対応のポイントになります。
それでは、それぞれ著書の体験も踏まえて詳しく見ていきます。
落ち着きのなさ=活発さが活かせる活動をしよう
ADHD児はとにかく落ち着きがありませんが、これは裏を返すと行動的であるともいえます。
著者が見ている子どもたちも有り余るほどエネルギーがある元気な子がたくさんいますが、こうした子どもたちには、体を使った遊びなどエネルギーを発散できる活動やスペースを作ることが大切になります。
また、体を使った遊びを通して、自分の身体機能を向上させたり、運動遊びの楽しさを知ることにも繋がります。楽しみの中でこそ、ルールがあると面白いということも実感できる子も多くいます。
ルールを明確にし、カードにして活用する
多動性はその特性からルールの外に飛び出す行動に繋がる場面が多くあります。
著者が見ている子も、ルールを逸脱することにより困ったことに繋がる状況を作ってしまう子もいます。
こうした子に対して、事前にルールを作る必要があります。ルールは、自分や周囲の安全を守ること、周囲に迷惑がかからずお互いにとってメリットがあるという設定が大切です。
特に初めてやることや、初めて行く場所などには、ルールの提示がないと、大人が声をかけても静止することが難しいことが多いため、事前にルールを作り、伝えることを大切にしています。
レストランなど騒ぐとまわりの迷惑な場所は避ける
基本的に静かにしないといない場所は、極力さけた方が良いです。
もし避けることが難しい場合には、前述したルールを伝えたり、少しずつ環境に慣れる練習も必要かと思いす。
特性上静かにすることが難しいという理解を前提に、叱責することをしないような事前の環境設定が重要です。
夕方からは静かな活動をさせて寝るための準備を
ADHD児は、何かに没頭すると夜になっても過集中状態で活動を続けることがあります。するとその疲れが翌日以降に持ち越すことに繋がります。
就寝数時間前からは、徐々に静かな活動に切り替えるなど寝るための環境設定が必要です。
著者は、遊びの中でメリハリを大切にしています。
遊びが終わった後は、クールダウンするようにして、気持ちを落ち着けるように配慮をしています。
以上が、ADHD児の多動性への対応のポイントになります。
ADHD児の中で、多動性や衝動性の特徴が強い子どもたちはとにかく元気で活動的です。
こうした特性を理解してきながら、こうした子どもたちがより生きやすくなるための理解と支援を今後も継続していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「ADHD児への療育-不注意の対応について-」
関連記事:「ADHD児への療育-衝動性の対応について-」
ADHDに関するお勧め書籍紹介
関連記事:「ADHDに関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「ADHDに関するおすすめ本【中級~上級編】」
司馬理英子(2020)最新版 真っ先に読むADHDの本:落ち着きがない、忘れ物が多い、待つのが苦手な子のために.主婦の友社.

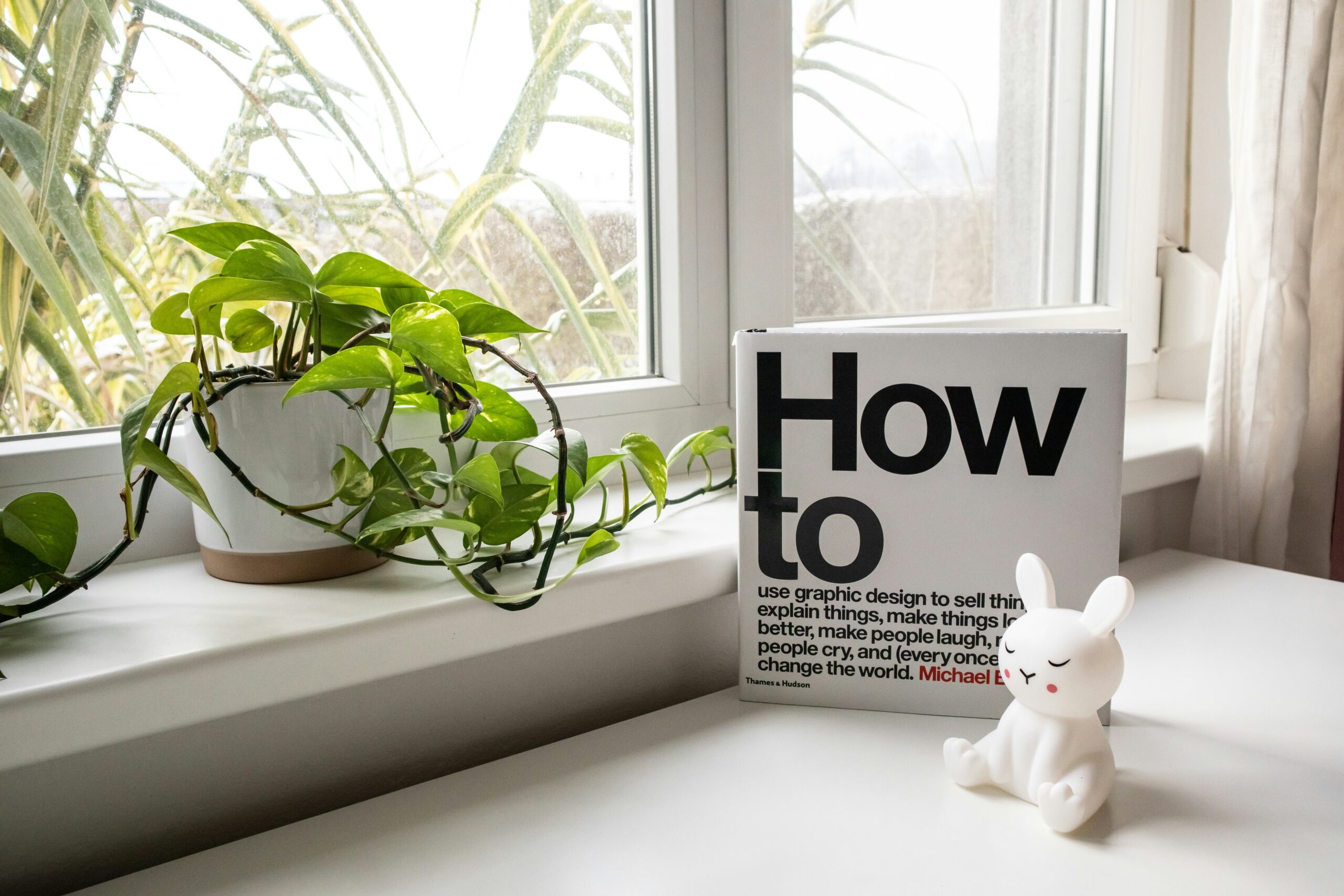

コメント