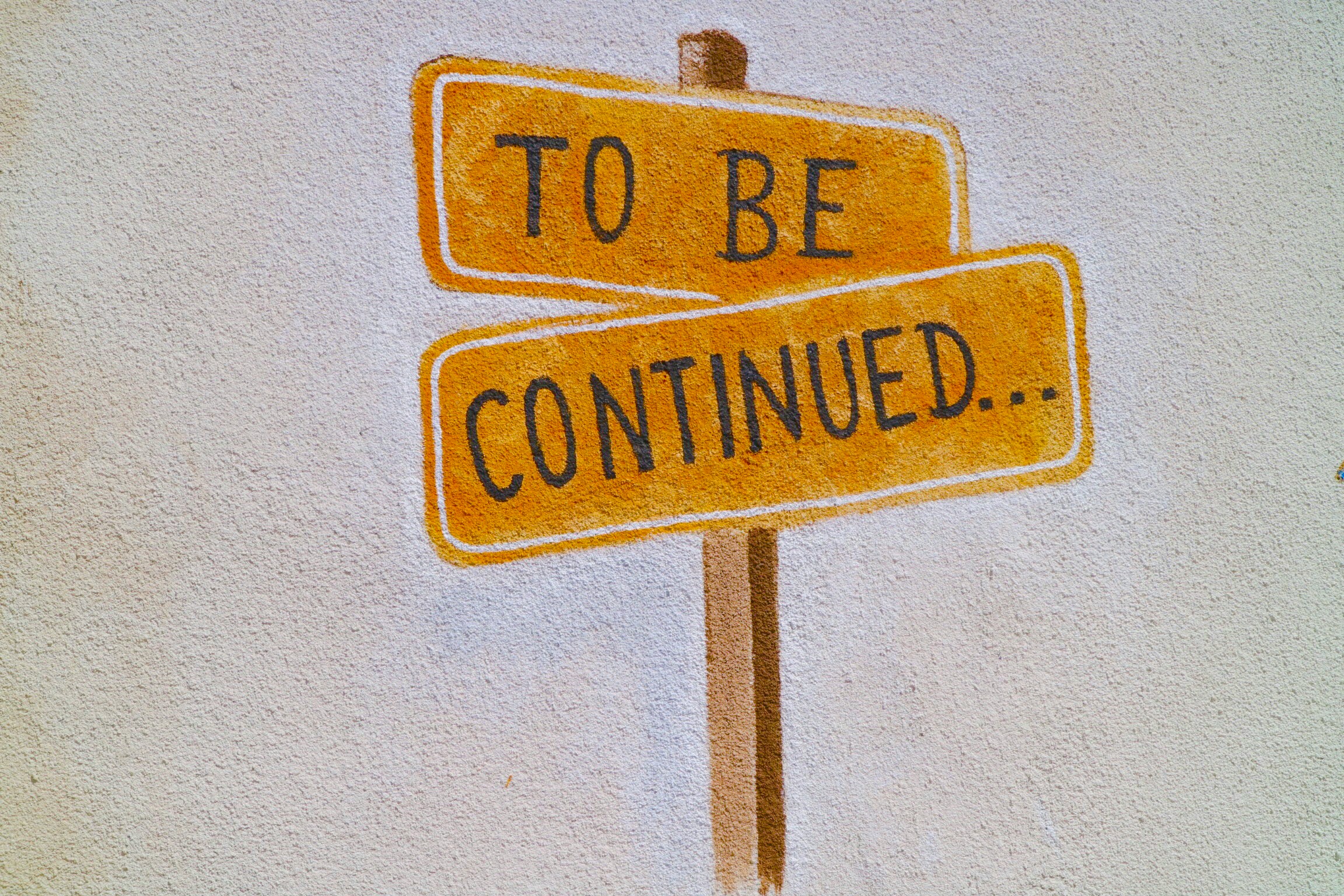
療育(発達支援)では、〝遊び″が中心的な活動になります。
子どもたちは〝遊び″を通して、自己を発揮したり、他者と関わる楽しさを学んでいきます。
子どもたちが行う〝遊び″は、一度きりで終わるものもありますが、多くの場合、次の日も、また次の日もといった具合にやり続ける様子が多く見られます。
それでは、同じ遊びをやり続けることには、どのような意味があるのでしょうか?
そこで、今回は、療育(発達支援)で大切な〝遊び経験の物語化″について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「田中浩司(2014)集団遊びの発達心理学.北大路書房.」です。
〝遊び経験の物語化″について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
保育者による遊びの指導は、1回限りの実践で完結するものではなく、継続的で連続的なものである。≪遊び経験の積み上げ≫とは、このような子どもたちの遊びの経験に連続性をもたせる指導であった。
仲間と協同的に体験を物語ることは、お互いの体験を重ね合わせ、集団としての物語を生成する機会となる。
著書の内容を踏まえると、保育者などの大人が子どもの遊びをリード(指導)することは、一度で完結するものではなく、〝連続性″があります。
そして、子どもが遊びによる経験を積み上げていくためにも、〝連続性″のある関わり方が必要だと言えます。
〝遊び経験の物語化″とは、遊びの〝連続性″の中で、自身の体験を物語として生成していくことを意味します。
子どもたちは、大人や他児との関わりを通して、様々な〝連続性″のある経験を共同体として、集団として作り上げていきます。
多くの遊びには、〝エピソード″があります。
子どもは様々な〝エピソード″を作り上げ、〝エピソード″を語ること、語り合うことを通して、〝遊び″の意味を見出していくのだと言えます。
著者の経験談
著者の療育現場では、子どもたちがこれまで取り組んできた様々な遊びを〝エピソード″として生き生きと語る様子がよく見られます。
著者が取り組んでいる活動(遊び)の多くは、その日で完結するものは少なく、何らかの〝続き″が存在しています。
例えば、〝ごっこ遊び″で、〝野球ごっこ″をすることがありますが、その日に行った結果や出来事などが翌日以降の遊びをさらに盛り上げていくことに繋がります。
○○君が打った!〇点取った!ファインプレーがあった!〇対〇で○○チームが勝った!など、〝野球ごっこ″には様々な〝エピソード″が生じます。
そして、翌日以降には、以前の〝エピソード″をもとに、ピッチャーを交代して挑戦する!球種を増やす!ピンチヒッターを新たに用意する!など、新し情報が付与されます。
こうした〝エピソード″が少しずつ増えていくことで、子どもの中には(大人にも)一つの遊びがある種の〝連続性″を持ちながら展開していく感覚が生じる部分が出てきます。
それは、自分たちのコミュニティ独自の文化によって築き上げられた独自の〝エピソード″とも言えます。
子どもたちは、自分たちが作り上げてきた〝物語″〝エピソード″を嬉しそうに語る様子がよく見られます。
それは、楽しい!新しい発見があった!成功した!他者と喜びを分かち合えた!など、〝快の感情″が身体の深部に記憶として体積しているものでもあります。
人は〝記憶″によって、過去を、現在を、そして未来を物語ることができます。
そのため、療育において大切なことは、子どもたちが良い人生の〝物語″を築いていく手伝いをすることでもあると言えます。
そのためにも、〝遊び″を深い意味・価値のある〝物語″へと発展させていくこともまた大切であると感じています。
以上、療育(発達支援)で大切な〝遊び経験の物語化″について考えるについて見てきました。
子どもたちはこれまでの遊びのエピソードをよく覚えていることがあります。
それは、大人である著者が忘れてしまっているものも多くあります。
昔、未就学児であった発語のない自閉症児A君との関わりがありましたが、その保護者の方から卒業しても園で過ごした頃の写真を大切に持っているとの言葉を頂いたことがあります。
A君にとっては、言葉には置きかることが難しくても、〝記憶″として、園での生活の〝エピソード″を思い起こす〝写真″だったのではないかと思い心が強く打たれたことを今でもよく覚えています。
人は経験を〝物語る″〝物語にする″力があります。
そして、〝物語″によって人の人生はより豊かなものになる側面が多くあるのだと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育現場で関わる子どもたちと良い人生の物語の一部を築いていくことができるように、子どもたちと楽しい時間を共有していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「療育(発達支援)で大切な〝遊びの流れ″を作ることについて考える」
関連記事:「療育(発達支援)に役立つ遊びに関するおすすめ本【初級~中級編】」
田中浩司(2014)集団遊びの発達心理学.北大路書房.










