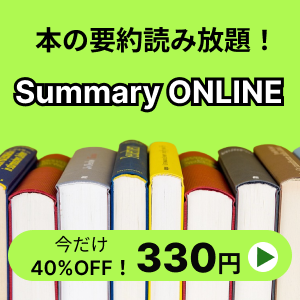発達障害児・者への支援において、〝二次障害″の理解と支援はとても大切です。
著者も長年療育現場で、発達障害など発達に躓きのある子どもたちをサポートしていますが、その中で、〝二次障害″の支援と予防はとても重要であると感じています。
それでは、発達障害の二次障害を理解する上で必要となる知識には一体どのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害の二次障害を理解する上で非常に役立つおすすめ本4選【初級~中級編】について紹介していきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
実際にこれから紹介する本を通して著者自身、発達障害の二次障害の理解が深まった、支援の役に立った等、有益な知識を得ることができました。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
1~4の番号はランキングではありません。紹介内容を見て入りやすい本から手に取って頂けるといいかと思います。
1.発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート
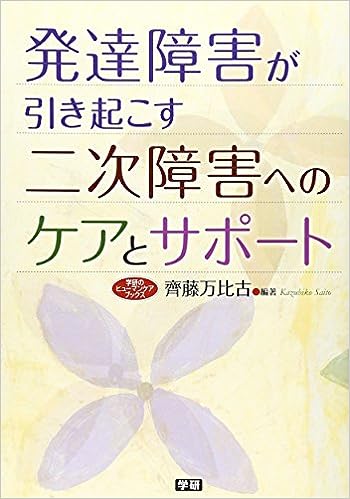
二次障害とは?二次障害はなぜ現れるのか?二次障害へのケアとは?など、発達障害の二次障害を理解する上で根本的な説明や発症のメカニズムが詳しく記載されています。
また、乳児期~思春期までの二次障害へのケアの方法、学校や家庭、医療など様々なフィールドでの支援方法も載っています。
二次障害には大きく、外在化と内在化があります。
この本ではどちらの場合についても詳細に取り上げられています。
後半には、当事者が語る二次障害についても書かれています。
発達障害の二次障害の理解について少し専門的な知識についても触れたい、そして、二次障害の概観を掴みたいという方にはお勧めです。
2.〝うつ″〝ひきこもり″の遠因になる発達障害の〝二次障害″を理解する本
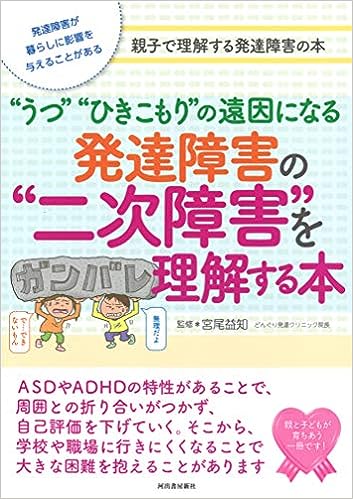
発達障害の二次障害について基本的な知識を得ることができる本です。
イラストも豊富なため初心者にとっても分かりやすい内容になっています。
二次障害の発症のメカニズム、二次障害のサインと対応方法などご家庭で取り組めるものが多く記載されています。
発達障害が持つ特性(ASD、ADHD、LD)がマイナスに影響して二次障害へと繋がるというケースが少なからずあります。
こうした状態を理解し、身近なことから取り組める方法を知りたい方にはお勧めです。
3.「キレる」はこころのSOS 発達障害の二次障害の理解から

〝キレる″という言葉が一昔前からよく聞かれるようになりました。
〝キレる″の背景には様々な原因と理由がありますが、その中でも、この本では発達障害の二次障害の視点から〝キレる″という行動の意味が非常に深く説明されています。
発達障害のある方には、〝反抗挑戦性障害″を併発するリスクが高いことが分かっています。
二次障害は大きく、外在化と内在化がありますが、この本では、主に〝反抗挑戦性障害″といった外在化への理解と対応方法が詳細に記載されています。
ご家庭や支援現場で子どもたちと関わる方の中には、手に負えないほど子どもが〝キレる″〝荒れる″〝挑発を繰り返す″〝暴言を吐く″などの行動に迷走されている方も少なくないかと思います。
そんな人たちにはぜひ読んで頂きたい本です。
4.子どもの発達障害と二次障害の予防のコツがわかる本
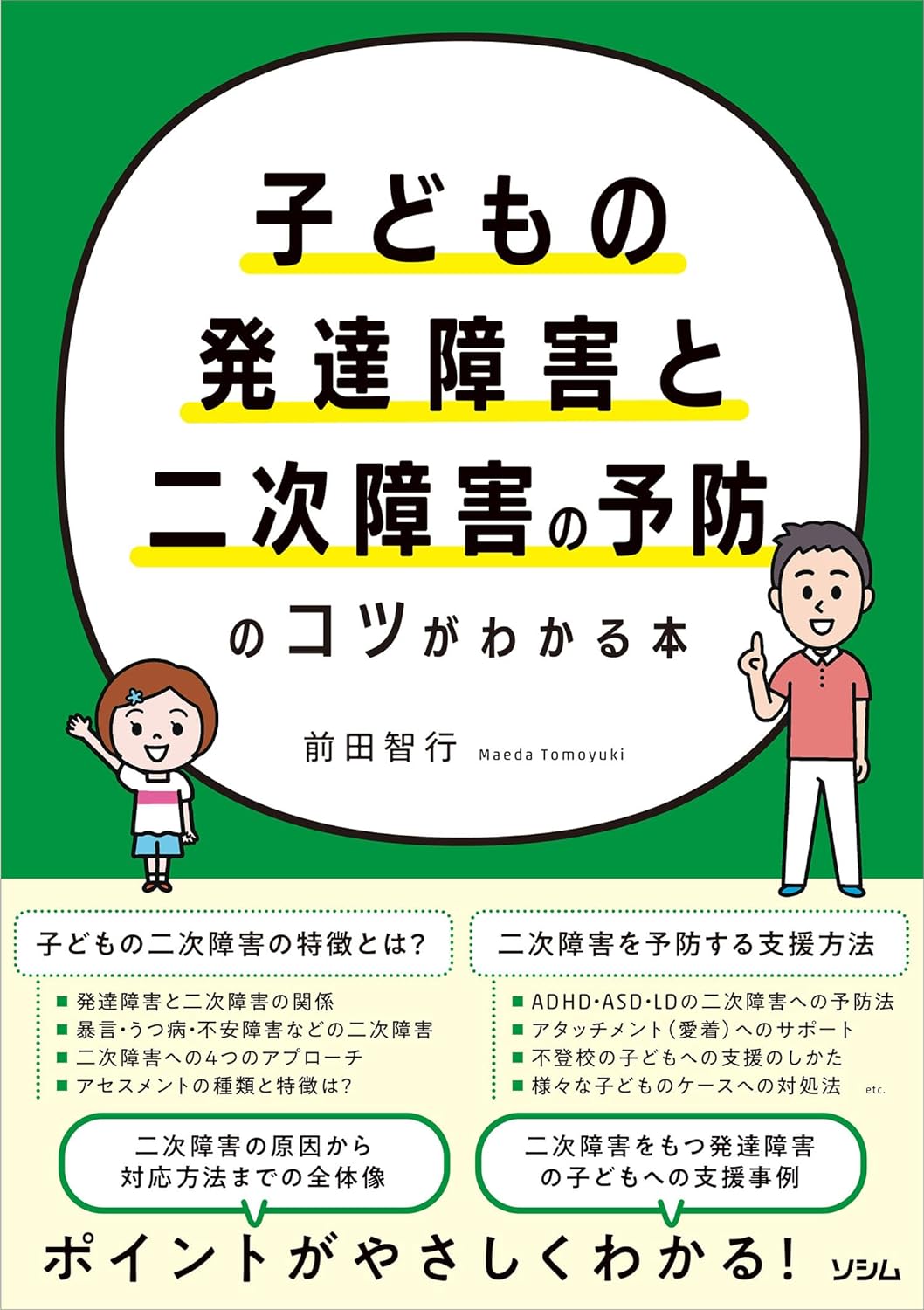
そもそも二次障害とは何か?二次障害にはどのような種類やアプローチの方法があるのか?障害の種別による二次障害の特徴はあるのか?二次障害のアセスメントのコツはあるのか?など、二次障害に関する様々な疑問について分かりやすく解説されている本です。
また、様々なケースに対する支援事例なども記載されています。
図も豊富にあるため、ポイントが分かりやすくまとまっているため、初心者の方にもお勧めです。
関連記事:「発達障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「行動障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」