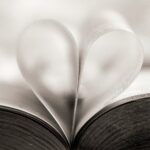愛着に問題を抱える生徒はいつの時代にも一定数の割合でいます。
学校という集団生活の場において、愛着に問題を抱える生徒が取る行動や言動は先生たちを非常に悩ませるものでもあります。
それでは、愛着に問題を抱える生徒に対して、先生ができる理解と対応にはどのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、愛着に問題を抱える生徒への理解と対応について、先生ができることをお伝えしていきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「遠藤和彦(編)(2021)入門アタッチメント理論:臨床・実践への架け橋.日本評論社.」です。
愛着に問題を抱える生徒への理解と対応について【先生ができること】
以下、著書を引用しながら見ていきます。
先生にとっても、回避的で否定的な、あるいは依存的で手がかかる生徒への対応は簡単ではありませんが、そうした生徒の表現に対して、根底にはアタッチメント欲求が隠れていると理解し、親がこれまでしてきたであろう反応とは「違う」反応を返していくことが、生徒が新しい良好な人間関係のパターンを獲得していく支えになると考えられます。
著書の内容を踏まえるといくつかのポイントがあります。
1.愛着に問題を抱える生徒への対応は困難
2.愛着に問題を抱える生徒は根底に愛情欲求が隠れている
3.愛着に問題を抱える生徒への対応方法
大きくは、以上の3点があります。
それでは、次にそれぞれについて説明していきます。
1.愛着に問題を抱える生徒への対応は困難
愛着に問題を抱える生徒への対応は困難です。
それは、ネガティブな行動に目を奪われ、行動の背景にまで目が向きにくいからです。
愛着の問題は、これまでの特定の養育者との情緒的な絆がうまく作れなかった、あるいは、ゆがんだ形でできてしまっている状態です。
なので、生徒の根底には不安感が強くあります。
こうした不安感が言動や行動として外に向くと非常に先生を困らせ・振りますことが多くなります。
例えば、生徒が先生に挑発的な言動を多くしたり、わざと苛立せるような行動をするなどがあります。
こうした言動や行動など起こっているそのもの(現象面)に直接的に向き合い続けると、関わる先生も徐々に疲労してきます。そして、関係性も悪化していきます。
また、先生といった立場上、良くない行動を正そうとすることも多くあるため、愛着に問題を抱える子どもの行動を変えることは簡単ではないため、対応がうまくいかない苛立ちを抱え続けることにもなります。
2.愛着に問題を抱える生徒は根底に愛情欲求が隠れている
愛着の問題の根源は、安全感・安心感の欠如です。
これは愛情欲求が隠れているとも言いかえることができます。
子どもは、特定の養育者との情緒的な絆から、自他への信頼を獲得していきます。
つまり、他者は安心できる・自分を守ってくれる存在であるという他者への確信が育ち、こうした他者への確信が育つことで、他者に大切にされている自分は世界から受け入れられているという自己への確信が芽生えてきます。
他者への確信が不安定だと、常に周囲の顔色を伺うなどの行動が増えたり、他者は信頼できないので頼れるのは自分だけといった回避的な行動を取るようになります。
他者への信頼が弱いと、他者の愛情を試すような行動を取ることがあります。
つまり、自分が取ったネガティブな行動に対して、この大人はどのような関わりをするのだろうか?どこまで許してくれるのだろうか?どうせすぐに注意したり自分を否定してくるのだろう、などの愛情を試す行動が見られます。
以上から、愛着に問題を抱える生徒の根底には愛情欲求が隠れているということが言えます。
3.愛着に問題を抱える生徒への対応方法
著書にもあるように、愛着に問題を抱える生徒への対応方法は、これまでの大人との関わりで形成した負の連鎖を断ち切るような関わり方です。
これはある意味、生徒にとって意外性のある関わりとも言えます。
愛着へのアプローチは様々なものがありますが、大切なことは、特定の信頼できる先生が安全基地となることです。
関連記事:「愛着で大切なこと【安全基地となる人の特徴について】」
そして、安全基地となる先生との信頼関係により、自他の感情理解を促すことです。
人は、他者から自分の感情を受容されて初めて、自分の感情を正しく認識したり、自分の感情を言葉にしていくことができます。
そして、ネガティブな感情も信頼できる大人と関わることで、軽減・回復できるという経験を重ねていくことで様々な感情が発達していきます。
これは、以前なら否定されていた自分の行動や言動に対して、異なる理解・関わりをしてくれる人(生徒の根底にある不安感や愛情欲求を理解してくれる人)のことが言えるでしょう。
安全基地となる人との関わりの中で、感情を発達させることが、愛着に問題を抱える生徒への対応としてはとても大切になります。
関連記事:「愛着アプローチとは何か【2つのアプローチから考える】」
関連記事:「愛着障害への支援:「愛情の器」モデルを例に」
以上、愛着に問題を抱える生徒への理解と対応について【先生ができること】について見てきました。
学校現場においても、愛着に問題を抱える生徒は多くいるかと思います。
その中で、基本となる大切な関わり方は共通しているように思います。
異なるのは、学校現場という環境と学校の体制にあります。
そのため、チーム学校という言葉もあるように、内部・外部のスタッフで協力した体制を作っていくことが重要です。
著者も学校の先生方と関わる機会が多くあるため、生徒への対応がうまくいくためには、チームで協力してやっていくということがとても大切だと実感しています。
私自身、まだまだ未熟ですが、今後も生徒(子ども)の問題となる行動の背景にまで目を向け、支援の質を高めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
遠藤和彦(編)(2021)入門アタッチメント理論:臨床・実践への架け橋.日本評論社.