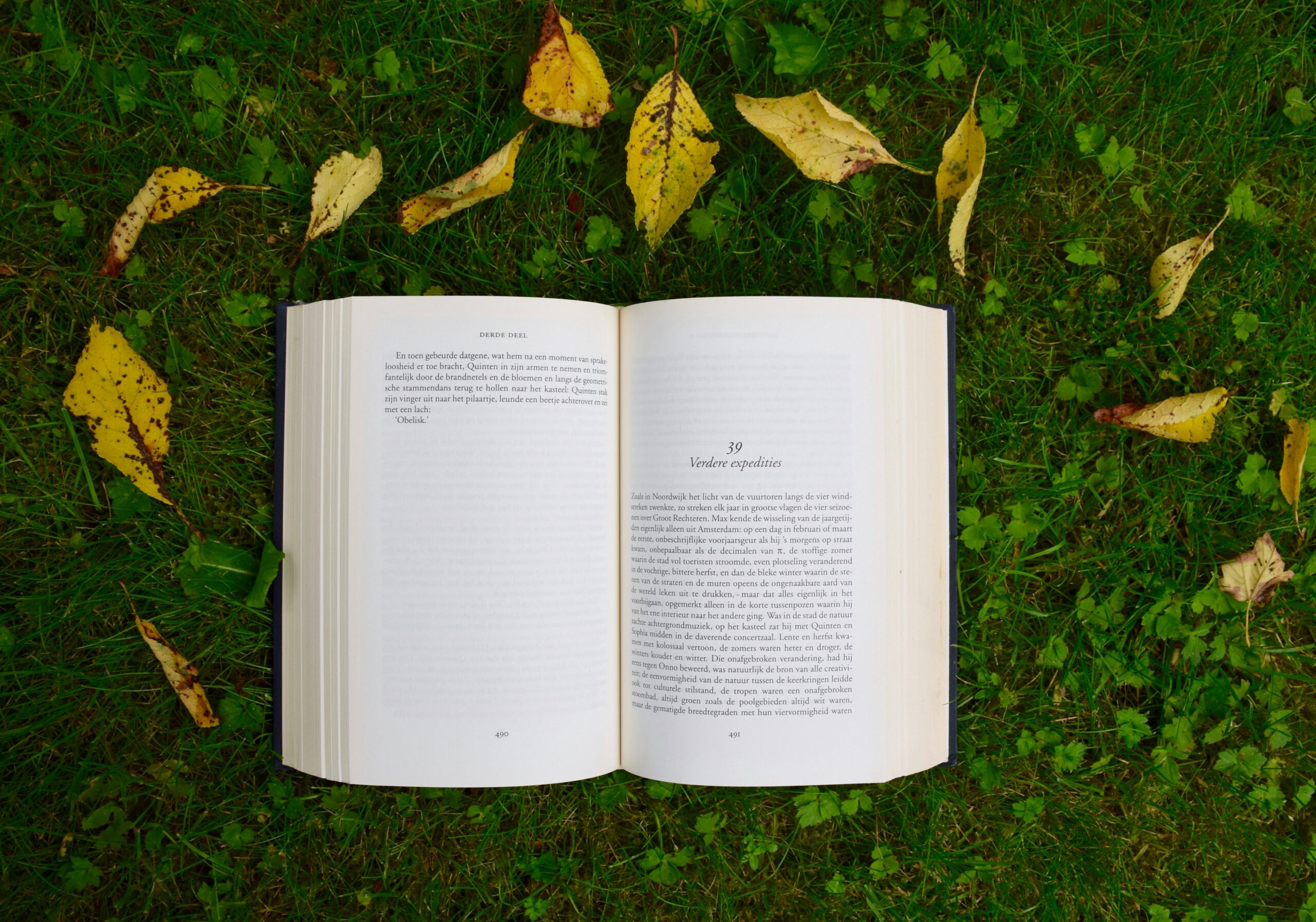
ADHD(注意欠如多動症)は、多動性・衝動性・不注意を主な特徴としています。
この中で、多動性・衝動性が有意なタイプと、不注意が有意なタイプと、すべての特徴を併せ持つ混合タイプがあると言われています。
ADHDの行動特徴の背景には実行機能が影響していると考えられています。
関連記事:「ADHDの実行機能について:実行機能の3つの要素と療育での実践を通して考える」
著者は長年、療育現場で発達に躓きのある子どもたちと関わる機会がありましたが、その中にADHDの人たちも多くいました。
その中で、上記の3つの特徴以外にも、様々な行動の特徴があると感じています。
それでは、ADHDの行動特徴には多動性・衝動性・不得意の3つの特徴以外に、他の特徴はあるのでしょうか?
そこで、今回は、ADHDの行動特徴について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、多動性・衝動性・不注意以外の特徴について理解を深めていきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は、「大島郁葉(編)大島郁葉・鈴木香苗(著)(2019)事例でわかる思春期・おとなの自閉スペクトラム症:当事者・家族の自己理解ガイド.金剛出版.」です。
ADHDの行動特徴について:多動性・衝動性・不注意以外の特徴
以下に著書を引用しながら見ていきます。
ADHDの特性は、さまざまな脳部位が絡む実行機能障害ととらえられます。三つの主な特徴に加えて、やらなければいけないことに取りかかれない行動開始の困難、言われたことをすぐに忘れてしまう作業記憶(ワーキングメモリー)の容量不足、すぐにキレてしまうような感情(情動)制御の未熟さは、日常生活において不適応の原因となりやすいものです。
著者の内容から、ADHDの行動特徴として、多動性・衝動性・不注意以外の特徴として(あるいはそれが要因となって)、行動開始の困難さ、作業記憶(ワーキングメモリー)の容量不足、感情(情動)制御の未熟さがあると記載されています。
もちろん、作業記憶の容量が不足しやすいことで不注意が生じる、感情制御の未熟さが多動性や衝動性として行動にでるなど、これらの特徴はADHDの3つの行動特徴と関連しているとも言えます。
ここでは、これらの関連性については言及せずに、その内容について見ていきます。
行動開始の困難さ、作業記憶の容量不足、感情制御の未熟さを知ることで、より現場でADHDの人たちを理解することに繋がると言えます。。
著者の療育現場でも、こうした行動特徴は、強弱はありますが多く見られます。
それでは、次に、こうした行動特徴についてそれぞれ著者の療育経験を通してお伝えします。
著者の体験談
行動開始の困難さについて
すぐに物事に取りかかることができない行動開始の困難さは、ADHDの方に多く見られます。
著者が関わるADHDの子どもたちにも、なかなか宿題に取り掛かれない(保護者からの伝達)、片付けに取り掛かれない、帰り支度までに時間がかかるなど、声掛けしても、そこから行動のスタートに時間を要することが多いと感じます。
そのため、支援のポイントとしては、スケジュールを事前に立てること、遅れるのを想定して早めに声掛けなどを行うことだと思います。
ADHDの人は、行動を開始するのが困難である一方で、一度、スイッチが入るとすごいスピードで物事に取りかかる場合もあります。
こうした行動のスイッチを入れることも大切です。
著者も、例えば、片付けなどで大人と子供チームで片付け競争を遊びの中に取り入れることで、片付けの行動にスイッチが入り、すごいスピードで片付けをする様子が増えたなど、苦手な面がある一方で強みを発揮する場合があることを実感することがあります。
作業記憶(ワーキングメモリー)の容量不足について
作業記憶(ワーキングメモリー)が影響してか、言われたことをすぐに忘れてしまうこともADHDの方にはよく見受けられます。
関連記事:「ワーキングメモリの概要:活用されているモデル・学習や発達障害との関連性について」
例えば、ついさっき決めた遊びのルールを忘れたり、やるべき活動の順番を忘れたり、予定や物の管理などを忘れるなどがあります。
そのため、支援のポイントとしては、紙やホワイトボードにルールや予定・手順を書くなど、視覚情報に残すことなどが考えられます。
口頭指示では、どうしてもその情報はすぐに消えてしまいます。
また、振り返ることも視覚情報があった方が振り返りやすいと思います(思い出しやすい)。
その他、作業や手順を細切れにするなど、○○をやったら次は○○など、記憶の容量をできるだけ使わないような環境設定も重要です。
著者も、その日の予定はホワイトボードに書く、遊びのルールを見える化するなどの取り組みの継続から、何かを忘れるという行動が減ったという印象があります。
感情(情動)制御の未熟さについて
キレやすい行動の特徴として、感情(情動)制御の未熟さもまた、ADHDの方にはよく見られます。
例えば、何か気に障ることを言われたらキレる、相手が誤って軽くぶつかったらキレるなど、著者の療育現場ではトラブルになりやすい要因の一つです。
そのため、支援のポイントとしては、キレた感情をまずは静めることが大切です。
その後に、本人がイライラした感情をくみ取りながら振り返り、一緒に解決策を考えていければ良いと思います。
キレた直後に何とか無理に介入しようとすると、逆に大人との信頼が崩れることがあります。また、本人は、「またやってしまった!」という失敗経験を単純に積み重ねるだけになってしまいます。
著者も直ぐに介入したことで失敗したことが何度もありました。
キレた直後にクールダウンをはかり、その後、落ち着いたら大人と振り返りができると信頼関係を基盤とした感情制御の力が少しずつついてくるといった印象があります。
関連記事:「ADHD児への療育の大切さ-不適切な関わりをやめるだけで子どもは変わる-」
以上が、ADHDの行動特徴についての説明になります。
ADHDは、その行動特徴から、トラブルになりやすく、社会的に不適応を起こすことが多くあります。
そのため、特徴(特性)への適切な理解と関わりがとても大切だと思います。
私自身、今後も、ADHDの行動特徴への理解を深めていきながら、日々の実践を大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
ADHDに関するお勧め書籍紹介
関連記事:「ADHDに関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「ADHDに関するおすすめ本【中級~上級編】」
大島郁葉(編)大島郁葉・鈴木香苗(著)(2019)事例でわかる思春期・おとなの自閉スペクトラム症:当事者・家族の自己理解ガイド.金剛出版.









