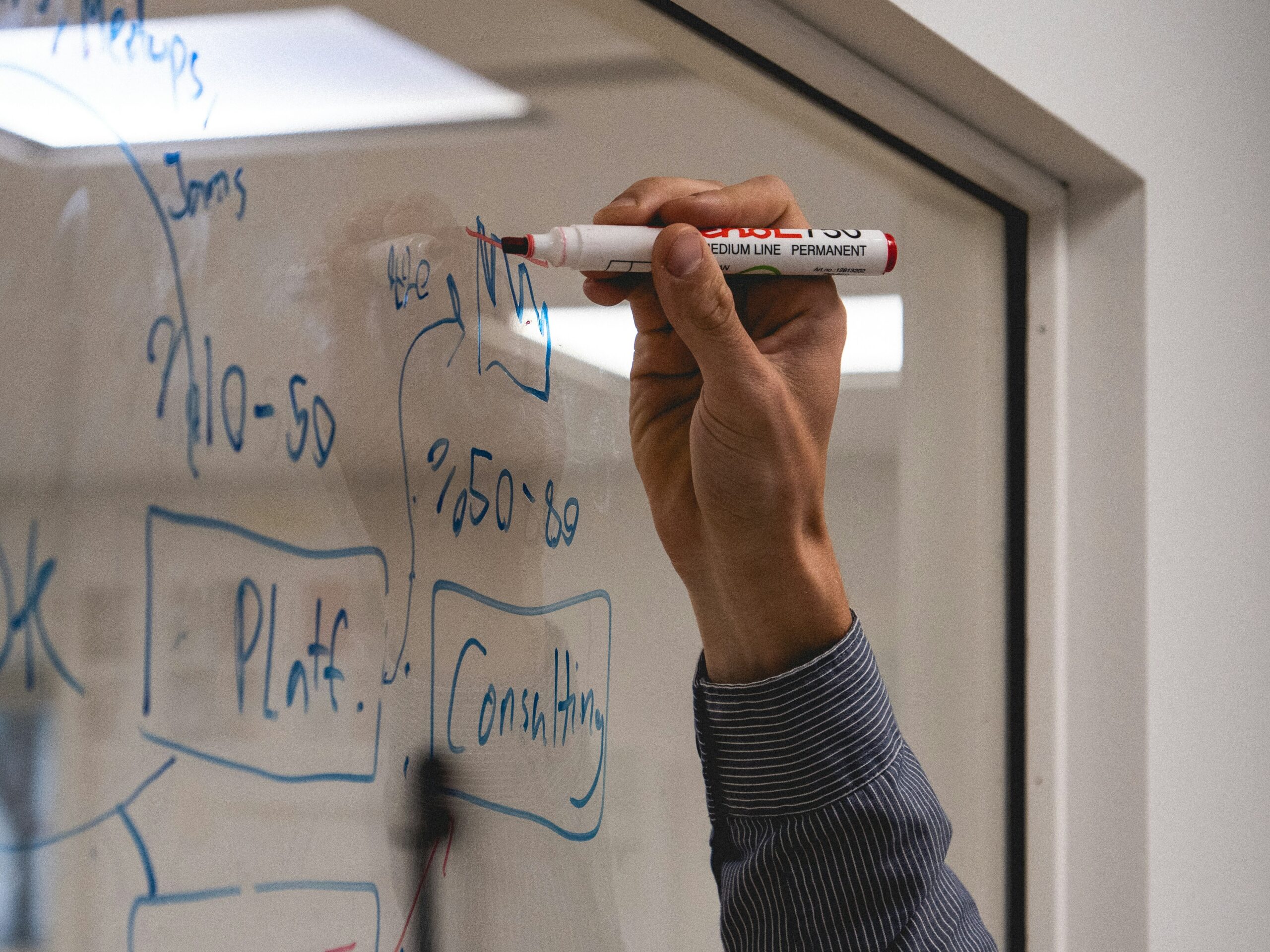
自閉症(自閉症スペクトラム障害:ASD)は、対人・コミュニケーションの困難さと限定的興味と反復的(常同)行動を主な特徴としています。
著者は長年療育現場で発達に躓きのあるお子さんたちを見てきましたが、その中に、自閉症の方も多くおります。自閉症の場合には、変化に対する不安が強いため、事前の見通しや活動場所の保障などをしていきながら、変化の幅を減らすことが特性への配慮としてはとても大切です。
また、自閉症の方は、視覚的な理解が得意なケースも多いため、視覚的な情報の提示も併せて重要なポイントになります。
こうした自閉症への配慮や支援を考える上でポイントとなるのが、居場所への支援です。
それでは、自閉症への居場所支援とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
今回は、自閉症への居場所支援について、著者の療育経験も交えながら、物理的・時間・作業・人間関係をキーワードに理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は、米澤好史著「事例でわかる!愛着障害 現場で活かせる理論と支援を」です。
【自閉症への居場所支援】物理的・時間・作業・人間関係をキーワードに考える
著書の中では4つの居場所支援を取り上げ説明しています。
以下にその4つについて部分的に引用しながら簡単に説明していきます。
1.物理的居場所支援
①物理的居場所支援=環境不安の防止:固定椅子・指定席・囲い⇒クールダウンの場所、クールダウンの場所確保。自分で行けるのが完成形。連れ出す時は、他から連れ出しに来る方が効果的。
1つ目に物理的居場所支援があります。つまり、空間を構造化し、自分が安心できる場所を保障するということです。
そして、落ち着かなくなった際には、クールダウン場所を事前に設定しておき、そこに連れていき(あるいは自分で行くなど)、気持ちを静める空間も用意しておくことが重要です。
著者の療育現場でも、部屋ごとに活動スペースをパーテーションなどで区切ることで、その空間が視覚的に何をする場所なのかをできるだけわかりやく提示するようにしています。
「自分のスペースはAの場所」「Aの場所で○○をする」といった安心感があると、子どもの情緒も落ち着くケースがよく見られます。
自閉症の場合には、感覚過敏の人も多くいます。そのため、他の様々な刺激(他児の大声や泣き声)でパニックを起こす場合もあります。
そのため、事前にクールダウンをとれる場所も想定しておくようにしています(残念ながらまだ不十分な点もあります)。
2.時間の居場所支援
②時間の居場所支援=予定不安の防止:時間計測による作業の切替・絵時計による予告支援など生活を構造化する。
2つ目には、時間の居場所支援があります。つまり、その日の活動の流れを時計や黒板(ホワイトボードなど)に書くなどして、時間を構造化するものです。
著者の療育現場でも、その日の活動のスケジュールをホワイトボードに書いたり、個別のスケジュールが必要なケースは、子どもと一緒に予定を事前に立てるようにしています。
ポイントは事前に予定を伝えることです。
自閉症のお子さんたちは、急な変更に対して柔軟に切り替えることが難しいため、事前に予定を伝えることがとても重要だと現場を通して実感しています。
その日の予定の変更を、その日の活動前に伝えることでも混乱する場合には、前日(数日前)に予告するようにしています。
もう一つのポイントは視覚情報の活用です。
これは自閉症のお子さんの強みを活かした関わりでもありますが、予定を視覚的に残すようにすると、より理解しやすくなると思います。
3.作業の居場所支援
③作業の居場所支援⇒常同行動・エコラリアの防止:お絵かき・塗り絵・制作等、熱中できる作業があることが安心に。
3つ目には、作業の居場所支援があります。これは、特定の場所で特定の活動(作業)をすることで安心感をつくるということになります。
著者の療育現場でも、こうした特定の場所で、制作遊びや感触遊びなどを行える作業場所を用意しています。
自閉症のお子さんの中には、常道行動(手をひらひらさせる・コマのように体を回転させるなど)が見られる場合には、感覚情報が不足していて不足した情報を取り込むために行っているか、遊ぶものがうまく見つからず(こちらの対応の悪さもあり)手持ち無沙汰から生じる場合などがあります。
こうした状態で、お絵描きなど特定の作業に誘うと、やりたいことが定まり安心して活動をする様子が見られます。
その際に大切なポイントとして、子どもたち一人ひとりがどのような活動が好きかを把握しておくということです。
自閉症のお子さんは、好きな活動を長時間やり続ける集中力もありますので、好きな活動を一緒に考えていくことが重要かと思います。
また、活動のゴールを事前に設定しておくことも終わりを見えるようにするために大切なポイントになります。
4.人間関係の居場所支援
④人間関係の居場所支援:最重要
(ⅰ)信頼できる人=捉え方を認めてくれる
(ⅱ)役割意識=そこにいていい理由
(ⅲ)特異な認知に共感するサイン=信頼関係
4つ目の、人間関係の居場所支援は、著書の中で一番重要視しているものになります(愛着関係の支援をベースとした際に)。
大切なポイントは、信頼できる人とは、本人の認知など本人の捉え方を理解してくれる人のことを言います。そして、信頼できる人といると情緒も落ち着きます。
役割意識を与えることで(家庭の手伝い・クラスの係など)、その場所にいて良いという安心感も高まります。
特異な認知に共感するサインとは、本人が好きな世界観(アニメや漫画など)やワード(その世界観から出てくる好きな言葉)などを理解しそれを活用するということです。
著者の療育現場でも、自閉症の子どもは、対人・コミュニケーションなどに苦手さはあっても、人との関わりを求める場合も多く見られます。
中には、「○○さんとの遊びを楽しみにしてきた」という人との関わりを強く求めてくる子もいます。
こうした関わりを求めてくる場合の大人は、前述した本人の認知特性など本人の捉え方をよく理解してくれる人を好む傾向があるように思います。
そして、普段落ち着きのない子も、信頼できる人と一緒にいると非常に情緒が落ち着く様子が見られるのも実感としてあります。
その他、特異な認知に共感するサインもよく活用します。
例えば、あるお子さんが自分の興味関心に没頭しており、大人が帰りの声がけをしても情報として入らない場合には、本人が好きなワードなどを活用して注意を大人に向けてから、再度声がけすると切り替えがスムーズになることもよく見られます。
以上、自閉症への居場所支援について4つの視点から見てきました。
どの視点も療育現場で活用すると効果があると実感しています。
私自身、まだまだ力不足ではありますが、今後も自閉症への関わり方について実践を通して学んでいきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「自閉症への支援-構造化と合意から考える-」
米澤好史(2020)事例でわかる!愛着障害 現場で活かせる理論と支援を.ほんの森出版.









