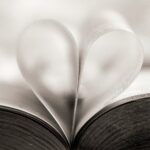発達支援の現場(療育現場)で働いていると、非常に関係性を築くことが難しい子どもたちがいます。
著者は長年療育現場で働いていますが、こうした関係性を築くことが難しい子どもたちの中には「愛着」に問題を抱えている子がいると感じています。
もちろん、これまでの生育歴の情報などから愛着に問題があったことがわかるケースもあれば、そうでないケースもあります。
現場で愛着に問題を抱えている(抱えているであろう)子どもたちへの支援はとても難航します。
重要なポイントは、一人の人から関係性を築くこと、できるだけ早期に介入すること、チームでサポートするなどの体制をしっかりと作ること、感情の発達の遅れを理解し支援することなどがあります。
関連記事:「愛着障害への支援:「愛情の器」モデルを例に」
愛着に問題がある子どもはとにかく大人の注意を引く挑発行動、暴言や攻撃行動といった問題行動を起こすことが多くあります。
こうした子どもに周囲の大人は「叱る」といった対応を取る方も多いと思いますが、「叱る」対応には問題点があると考えられています。
それでは、愛着に問題のある子どもには、叱り方も含め、どのような支援方法が有効だと考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、愛着に問題がある子どもへの支援について、「叱る」対応の問題点とそれを踏まえた支援方法について、臨床発達心理士である著者の経験談も含めてお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は、「米澤好史(編著)(2019)愛着関係の発達の理論と支援.金子書房.」です。
「叱る」対応の問題点について
それでは著書を引用します。
「叱る」はたいていの場合、こどもが不適切で叱る必要を感じる行動を先にした後で叱るというように、「後手」のかかわりだからである。先にこどもがある行動をしてある感情を感じている事態で、後からの対応でその感情を変えるのはそもそも困難である。
著書の中では、「叱る」対応の問題点は、子どもが問題となる不適切な行動をした後の、「後手」の対応になっているため、「後手」の対応では改善効果が期待できないとしています。
再び著書を引用します。
「叱る」に自動的に他者の行動を変容させる機能はない
著書では、「叱る」という行為には行動を変えることは困難であるということも併せて記載されています。
著者も療育現場で、愛着に問題のない子も含め、「叱る」という行為で子どもがポジティブに変化したという実感はありません。
もちろん、一時的に問題となる行為を止める効果はあるかもしれません。また、「叱る」行為をよく取る人物のいうことは聞くがそうでそうでない人(やさしい人など)に代わるとすぐに態度が変わるということが起こります。
このような場合には、責められるのはやさしい人だったりしますが、これでは問題の解決にはなりません。
そして、長期のスパンで「叱る」よりも「褒める」ということが重要かと思います。
「叱る」には、行動を止める働きはあるかもしれませんが、「褒める」には、その子の内部の意欲のエネルギーをさらに引っ張り上げ、主体的に行動することに繋がると感じます。
関連記事:「療育で大切な視点-子どもへの「叱り方」について-」
それでは次に、愛着に問題への支援方法で大切な視点をお伝えします。
愛着の問題への支援方法について
以下に著書を引用します。
愛着の支援では、目の前での行動の問題にのみとらわれず、現れやすいところに問題が出やすいという意識が必要です。(略)「こうしよう」と別の行動に誘うことで結果的にその行動をやめることができるような支援が大切なのである。これはこどもの今している行動に後手で対応するのではなく、新たな行動に誘う「先手」の支援だから成功しやすいのである。
著書の内容から、大切なポイントは「先手」支援ということになります。
問題行動への対応は起こってからの「後手」の対応ではなく(結果「叱る」に繋がります)、子どもの感情状態に早くに気づき、早めに働きかけることが大切になります。
著者も、愛着に問題を抱える子への対応として大切にしていることは、「予防的な視点」です。つまり、問題行動が起こりやすい状況を分析し、その状況を作らないようにしています。
これも、「先手」の対応だと思います。また、問題行動が起こりそうな場合には、他の情報に注意を逸らす支援や本人がメリットを感じやすい提案などを早めにとるようにしています。
その中で、特定のスタッフが関わることで楽しかった活動を共有できたという経験を積み重ねていくことも併せて大切にしています。
愛着の問題のある子どもたちとの関わりは長期戦です。
その中で、こうした子どもたちを叱り続けて行動を変えようとすることに意味がないということを強調しておきたいと思います。
大切なのは、「先手」の対応です。
私自身も、療育現場で愛着の問題のある子との関わりは試行錯誤の過程であり、前進と後退をくり返すことも多く、大変なエネルギーが必要になります。
関わるスタッフ同士での協力体制をしっかりと取りながら、一人の人の負担が偏らないことも重要だと思います。
そして、今回参照した著書などの知識をフルに活用していくことも大切だと思います。
今後も子どもたちに対して、より良い理解と支援ができるように頑張っていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
米澤好史(編著)(2019)愛着関係の発達の理論と支援.金子書房.