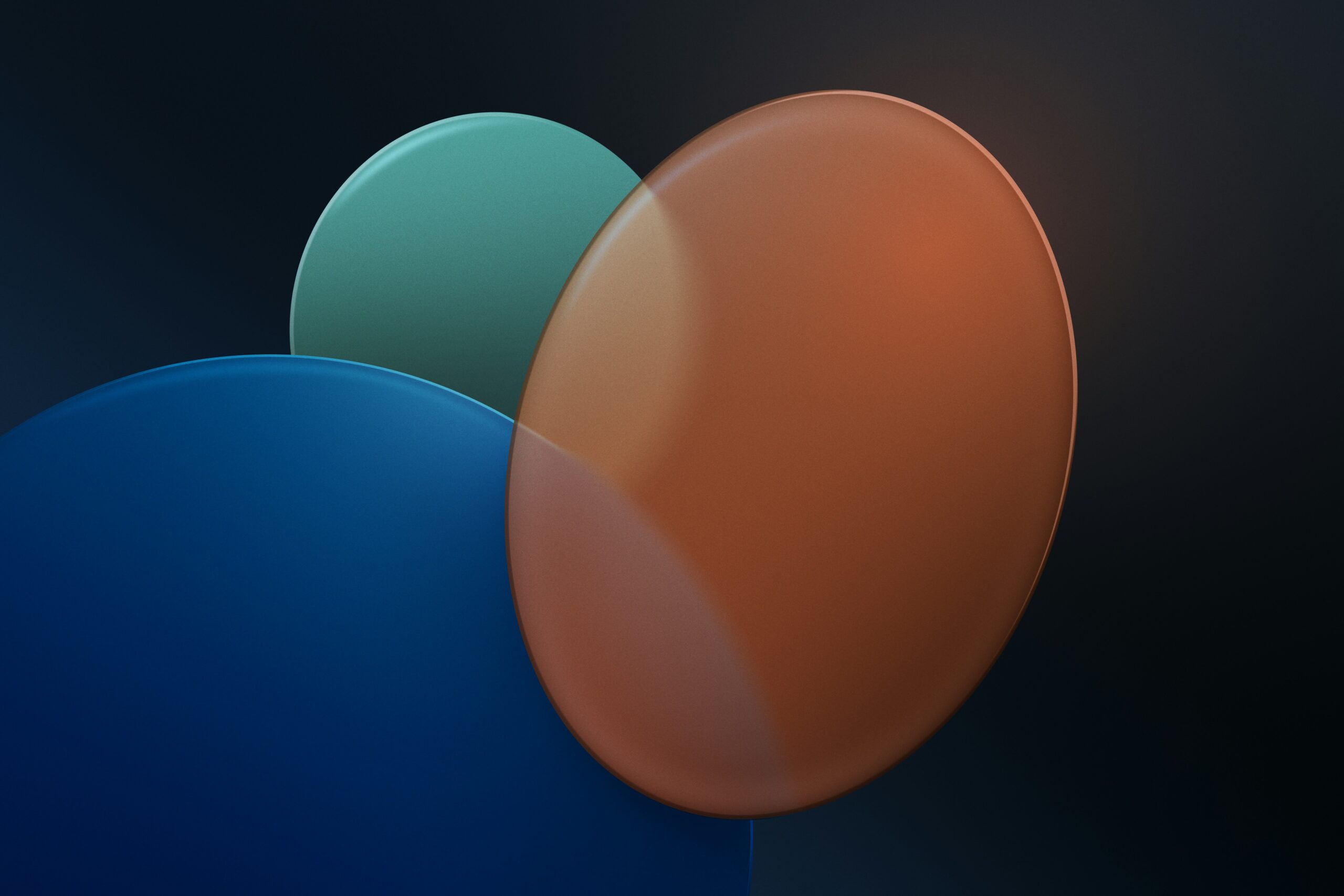
様々な発達障害が重複(併存)しているケースが多くあると言われている中で、どのようにして重複(併存)の状態像を理解していけば良いかで思い悩んだことはありませんか?
例えば、自閉スペクトラム症(ASD)の診断がある一方で、診断はないがADHDの特徴も見られるような気がする(その逆もあります)、ある行動特徴の背景にはASDとADHDのどちらの特性が影響しているのかなど、発達障害の重複(併存)の理解は複雑だと言えます。
著者がこれまで療育現場で見てきた子どもたちの多くが、発達障害の重複(併存)のケースも多いと感じる一方で、状態像の理解の難しさ、そして、状態像を理解していきながらより良い支援に繋げていくことの難しさを感じています。
かつての著者は発達障害の重複(併存)に関する知識がほとんどなかったため、手探り状態でのスタートでした。
今回は、現場経験+理論+書籍の視点から、発達障害の重複(併存)に関する理解と支援のヒントについてお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
目次
1.発達障害の重複(併存)の理解のあり方に迷走していた著者のエピソード
2.発達障害の重複(併存)を理解する理論・書籍
3.発達障害の重複(併存)に関する支援の意味・効果が見えてきた著者の経験談
4.まとめ
1.発達障害の重複(併存)の理解のあり方に迷走していた著者のエピソード
著者は、長年療育現場に関わる一方で、大人の発達障害の人たちとも関わる機会が多くありました。
その中で、一つの発達障害の特性理解だけではどこか腑に落ちない感覚がありました。
例えば、ASDの特性だと診断を受けているが明らかに不注意や多動性も見られるケース、逆にADHDの診断を受けているが対人コミュニケーションの困難さや感覚の問題といったASDの特性も見られるケースなど様々あります。
一つの診断名や診断名からくる発達特性の理解だけでは、目の前の子どもの特徴をより正確に捉えることに難しさを感じていました。
また、特定の発達特性にのみ捉われた理解をしてしまうことで、当事者の困り感の本質が見えなくなってしまうこともあると感じています。
そんな中で、様々な発達障害の書籍を見ても、それぞれの障害特性に関する情報は載っていても、肝心な様々な発達障害が重なり合っている状態像の理解に関する情報はなかなか目にすることがありませんでした。
一方で、徐々に文献を読み進めて行く中で、医学系の方が書かれた本に発達障害の重複(併存)を取り上げているものがありました。
発達障害の重複(併存)を取り上げている本、様々な発達障害の違いを取り上げている本などを読み進めて行く中で、少しずつ目の前の子どもたちの複雑な状態像の理解を深めていくための突破口が見えてきました。
もちろん、発達障害の特性以外にも子どもを理解する上で大切な視点は多くあります。
一方で、発達障害の特性は生涯に渡り残り続けるものであるため、その個別の特性理解、さらには、特性の重複(併存)の理解は必須だと考えます。
2.発達障害の重複(併存)を理解する理論・書籍
最初に、〝重複″と〝併存″の意味の違いですが、両者はほとんど同じ意味合いで使用されていますが、少しニュアンスが異なると考えられています。
〝重複″とは、2つ以上の発達障害の診断特性が「重なっている」ことを指し、〝併存″とは、「一人の人に複数の診断が同時に存在する」ことを指します。
ほとんど同じ意味ですが、〝重複″が現場や保護者向けの説明で使用されることが多く、〝併存″が学術論文や診断基準などで使用されるといった違いがあります。
今回は、明確な分類はせずに使用していきたいと思います。
それでは、発達障害の重複(併存)の理解を深めていく上で、著者が非常に参考になった書籍を以下に紹介していきます。
書籍①「本田秀夫(2018)発達障害:生きづらさを抱える少数派の「種族」たち.SB新書.」
書籍②「田中康雄(2019)「発達障害」だけで子どもを見ないで:その子の「不可解」を理解する.SB新書.」
書籍③「岩波明(2017)発達障害.文春新書.」
書籍④「岩波明(監修)小野和哉・林寧哲・柏涼ほか(2020)おとなの発達障害 診断・治療・支援の最前線.光文社新書.」
以上の書籍を踏まえて、著者が非常に参考になったキーポイントとして、1.発達障害の重複(併存)・強弱、2.なぜ、発達障害の重複(併存)の理解は難しいのか?、3.ASDとADHDの違い、4.年齢による特性の変化です。
それでは、次に、以上の4つのキーポイントについて具体的に見ていきます。
1.発達障害の重複(併存)・強弱
それでは、書籍①を引用しながら発達障害の重複・強弱について見ていきます。
私は、発達障害関連の問題で専門外来を訪れる人の多くは、重複例だと感じています。重複の程度は人によって異なりますが、ひとつの障害の特性だけが存在し、そのための診療だけで対応できるという例は、比較的少ない印象です。
発達障害の特性には「強弱」があります。特性は「有りか無しか」「1か0か」で考えられるものではありません。すべての特性に強さ、あるいは濃さのようなものがあります。それは濃淡のグラデーションのようなものです。
発達障害の重複例はひとつの障害特性を持つケース以上に多い印象があると、発達障害の専門家である〝本田秀夫さん″は著書の中で述べています。
その状態像は、様々な発達特性の強弱(グラデーション)や重なり方によって様々な違いがあると言えます。
例えば、ASD(強)+ADHD(弱)のケースもあれば、ASD(弱)+ADHD(強)など様々なタイプが存在しています。
こうした違いによって、見えてくる状態像には、非常に多くのタイプがある一方で、理解において複雑さが出てくるため、状態像の理解が難しくなると言えます。
最近では、複数の診断を受けている発達障害児・者も出てきており(例:ASD+ADHD+SLD)、発達障害は重複(併存)していることが珍しくなくなってきています。
こうした発達障害の重複(併存)のケースを理解する上で、書籍①は大変参考になると言えます。
この本では、子どもから大人までを対象としているため、多くの方に参考になるものだと感じます。
次に、同じく発達障害の専門家である〝田中康雄さん″は発達障害の重複(併存)について次のように述べています(以下、著書②を引用)。
僕は、発達障害はある一定の特性をもつ「脳のバリエーション」「脳のタイプ」としてとらえています。(略)「脳のタイプ」である以上、当然その現れ方には強弱があり、多種多様でもあります。さらに日々の成長や環境によって変わることもあります。(略)濃さはみんな一定ではなく、ある特性がとても濃い人もいればとても薄い人もいます。同じ人であっても、生活環境や状況に応じて色濃く見えるときもあれば、あまり目立たないようなときもあります。(略)複数の「発達障害」のタイプが重なり合って現れることも多く、1人の子に診断名が1つだけ、ということになるとは限らないのです。
著書の内容を踏まえると、先に見た書籍①の〝本田秀夫さん″と同様に、発達障害には、複数の特性が重複していたり、強弱が見られるなど多種多様だと記載されています。
さらに、成長に伴い変化していくこともあれば(詳しくは4で見ていきます)、環境要因によっても変わってくると考えられています。
例えば、ASDのこだわり行動に対して、良い配慮を受けられる環境があればASDの特徴が目立ちにくいこともあり、一方で、あまり配慮が受けられない環境にあればASDの行動がより顕著に見られる、さらには、二次的な問題(癇癪・パニックなどの問題行動)となって現れることもあります。
書籍②は、書籍①と比べると、発達障害の重複(併存)をメインに扱った本ではありませんが、乳児期~思春期にかけての子どもの不可解な行動を理解するヒントが豊富に記載されています。
不可解な行動の背景と支援への手掛かりには、様々な要因があるといったことを踏まえると、発達障害の重複(併存)も含めて対応していく上で多くのヒントが得られると感じます。
著者は、以上の観点(書籍①②等)を踏まえて、療育現場で子どもたちを見る際に、さらには、大人の発達障害の人たちと関わる際に、発達障害の重複(併存)の可能性を必ず考える習慣が身に付いたように思います。
2.なぜ、発達障害の重複(併存)の理解は難しいのか?
発達障害の重複(併存)の理解がなぜ難しいのかについて、書籍①を引用しながら見ていきます。
発達障害の特性の重複はなかなか理解されないのか。その背景としてさまざまな要因が考えられますが、そのひとつに、「研究が専門分化している」ということがあります。医学や心理学の研究者、とくにアメリカの人たちは、自分の専門としてる分野に特化した研究を行う傾向があります。
著書の内容から、発達障害の重複を理解する難しさの一つとして、専門の研究が分化している点があります。
例えば、ASDに関する研究、ADHDに関する研究など、特定の発達障害に関する研究が進められていることが多いため、逆に重複に関する研究が少ないことが背景としてあります。
実際に当事者の人たちと関わることで、単独の障害特性だけでの理解が難しいと感じる場面が多く、こうした状況はまさに、研究と現場とが解離している所だと思います。
一方で、発達障害の重複や強弱を重視した研究もあります。
キーワードは、〝DAMP症候群″〝ESSENCE″〝MSPA″です。
以上に関する記事は「【発達障害の「重複」「強弱」への理解】「DAMP症候群」「ESSENCE」「MSPA」を例に」に記載しています。
3.ASDとADHDの違い
ASDとADHDは、場合によっては似ていると感じることがあります。
もちろん、ASDとADHD両方の特性を有しているケースもありますが、単独の場合、行動の背景は異なると考えられています。
例えば、対人コミュニケーションの問題は、ASDの人たちにおける困難さの特徴(他者の心の状態理解が難しい)でありますが、一方で、ADHDの人たちにも衝動性の特性が影響してコミュニケーションの問題が発生することがあります(他者の心の状態理解はできる)。
例えば、あまり深く考えずに衝動的に話して相手を不快にさせてしまうなどです。
ADHDのコミュニケーションの問題は、長期化すると二次的な問題へと発展することがあり(対人面での失敗経験の蓄積)、二次的な問題に至ると他者とのコミュニケーションを避ける様子が見られるなど、ASDの特徴と見分けづらい状態になることがあります。
ASDとADHDの違いを見分ける上で、次の点が重要だと言えます(書籍③を引用)。
ASDの特徴である「対人関係、コミュニケーションの障害」(他人の気持ちが理解できない、場の空気が読めないなど)は、ADHDと区別する鑑別点にはならないことが多い。
ASDとADHDを区別するには、むしろ「同一性へのこだわり(常同性)」が鑑別点として重要である。ASDでは、特定の対象に対して強い興味を示したり、反復的で機械的な動作(手や指をぱたぱたさせたりねじ曲げる、など)がみられるが、このような症状はADHDではまれである。
著書のあるように、ASDとADHDを区別するポイントとして、対人関係・コミュニケーションの障害は鑑別点にはならず、〝同一性へのこだわり(常同性)″が鑑別点だと考えられています。
ASDとADHDを区別するポイントが〝こだわり行動の有無″といった理解を踏まえた上で、その他、不注意や衝動性、対人関係の問題などASDとADHDには似たような躓きがある一方で行動の背景に違いがあります。
この点について詳しくは以下の記事に記載しています。
関連記事:「ASDとADHDは似ている?-似ているが行動の背景は異なる-」
書籍③の執筆者である〝岩波明さん″もまた、大人の発達障害の専門家です。
この本を通して、ASDとADHDそれぞれの特徴や違いについて詳しく学ぶことができます。
著者は、以上の観点を踏まえて、様々な発達障害(ASDやADHDなど)には似たような行動が見られるも、行動の背景は異なるといった深い理解へと繋ぐ学びのきっかけを得ることができたと感じています。
4.年齢による特性の変化
発達障害の特性の現れ方は年齢によっても違いがあると考えられています。
この点について、次に、書籍④を引用しながら見ていきます。
最初に現れるのは多動です。少し年齢が上がると、多動、衝動が現れてきて、学歴期になると不注意の問題も顕在化してきます。思春期以降になって社会性の問題が顕在化する頃には、衝動性が下がってきます。さらに、不注意、こだわり、社会性の問題が徐々に強くなり、多動、衝動が見えなくなってくることもあります。
発達過程において・・・
さらに・・・
といったパターンがあると記載されています。
著者のこれまでの発達障害児・者との関わりを踏まえて見ても、発達初期ほど、衝動性・多動性が多く見られること、思春期前後から対人コミュニケーションの困難さといった社会性の問題が顕著になってくるといった印象があります。
また、多動性・衝動性が落ち着いてくる一方で、不注意は継続して残り続けることや、こだわり行動も継続して残り続ける(こだわり保存の法則)といった印象もあります。
こうした変化には、環境の影響、脳の成熟の要素や個人の適応方略といった個人の影響などが関連していると言えます。
年連による特性の変化の視点をおさえていくこともまた、今後も見据えて、今現在関わる子どもにどのような配慮・支援が必要であるかを検討する上で重要なことであると感じます。
3.発達障害の重複(併存)に関する支援の意味・効果が見えてきた著者の経験談
これまで見てきた〝発達障害の重複(併存)″に関する知識を療育現場に取り入れていく中で、次のような支援の意味・効果が見えてきました。
まずは、発達障害の重複(併存)の可能性を踏まえることで支援の幅が広がったことです。
例えば、AさんはADHDの診断を受けている状態で、著者が勤める放課後等デイサービスに通所を始めることになりました。
そうなると、支援上、ADHDの特性を踏まえた支援が必要になります。
一方で、Aさんには、ADHDの特性以外の影響からくる対人面の問題も少なからず見られていたように感じていました。
著者はこの時、発達障害の重複(併存)の視点を踏まえて考えることで、実はAさんには、ASDの特性もあるのではないか?といった仮説を立て、ASDの特性を踏まえた支援も同時に行っていきました。
支援の継続の結果、A君の状態理解が深まっていき、今、どのような支援の優先度が高いの(困り感に繋がる特性理解の優先度)かが少しずつ分かるようになっていきました。
診断こそ受けていませんが、Aさんには、ADHDの特性以外にも、ASDの特性があったのだと改めて実感しました。
さらに、Aさんの特性の現れ方は、小学校の低学年の頃は、ADHDの特性が強く、高学年になるにつれてASDの特性がより顕著になっていく印象があったため、年齢による特性の変化も考慮する重要性があると感じました。
次に、発達障害の重複(併存)の視点を持つことで様々な行動の背景要因がより理解できるようになったことです。
著者の療育現場には、複数の発達障害を持つ、あるいはその可能性のある子どもたちが多くいます。
例えば、Bさんは、不注意傾向が強く、忘れ物が頻繁に見られていました。
Bさんは、診断こそ受けていませんが、ASDとADHD両方の特性が見られていました。
そのため著者は、ASDとADHDの両方の特性を踏まえた支援を考えていきました。
例えば、ASDの特性で言えば、そもそも忘れ物をすることに困り感を抱いていない可能性があるため、忘れることで困ること、忘れずに過ごすことのメリットなどを伝えることで、忘れ物への認識(優先度)をより強化していく方法を取っていきました。
一方で、ADHDの特性で言えば、物の整理整頓の仕方、次の活動に移る前に出した物を片付ける、予定を事前に確認する習慣を伝えていくなどの方法を取っていきました。
こうした支援の継続の結果、Bさんは少しずつではありますが、忘れ物をする頻度が減っていったように思います。
発達障害の重複(併存)の視点は、似たような行動特徴が見られた際の行動の背景を探る視点、そして、背景を踏まえた支援の方向性を考える上で重要だと感じます。
4.まとめ
発達障害の重複(併存)の割合は専門家の間でも多いと考えられています。
発達障害が重複(併存)することで状態像は非常に多様になり、例えば、様々な発達特性の組み合わせに加えて(ASD+ADHDなど)、各特性の強弱(ASDが強い+ADHDが弱いなど)によって様々なバリエーションが見られます。
それに加えて、環境要因の違い、年齢による変化によっても状態像に違いが出てきます。
ASDとADHDには、一見すると似たような行動特徴もありますが(例えば、不注意傾向など)その背景は異なります。
そのため、行動特徴の背景を理解した支援が必要だと言えます。
書籍紹介
今回取り上げた書籍の紹介
- 本田秀夫(2018)発達障害:生きづらさを抱える少数派の「種族」たち.SB新書.
- 田中康雄(2019)「発達障害」だけで子どもを見ないで:その子の「不可解」を理解する.SB新書.
- 岩波明(2017)発達障害.文春新書.
- 岩波明(監修)小野和哉・林寧哲・柏涼ほか(2020)おとなの発達障害 診断・治療・支援の最前線.光文社新書.









