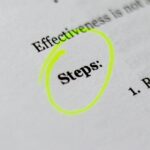自閉症児に見られる物事の全体像の見えにくさが影響して、生活上の様々な事柄で悩んだことはありませんか?
例えば、自分の興味関心に対する過度な執着、同じ内容の事を繰り返して見る・話す、細部にフォーカスすることで全体像が見えないなどの特徴は〝中枢性統合の弱さ″があると言えます。
まさに、〝木を見て森を見ず″の状態のことを言います。
物事の全体像が理解できないと、スケジュール管理や集団活動、遊びの全体像の理解など日々の生活上様々な困り事が生じる可能性があります。
一方で、〝中枢性統合の弱さ″に対して、どのような支援をしていけば良いかといった難しさもあります。
かつての著者も特徴は理解できても、具体的に何を大切に、支援をしていけば良いか思い悩むことがよくありました。
今回は、現場経験+理論+書籍の視点から、自閉症児の中枢性統合の弱さへの支援のヒントをお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
目次
1.弱い中枢性統合に関するエピソード
2.中枢性統合を理解する理論・書籍
3.支援の経過と結果
4.まとめ
1.弱い中枢性統合に関するエピソード
今回は、自閉症児のAさん(当時、小学校高学年)の放課後等デイサービスでのエピソードを紹介します。
当時のAさんは集団活動に関する経験値が少なく、例えば、遊びにおいて、自分の興味関心を中心に遊びを進めようとする様子が多くありました。
興味関心も非常に限定的であったため、遊びのルールにおいても、自分の興味関心に合わせてルール決めをしていくことがよくありました。
そのため、他児がその非常に限定的なルールに応じないと文句を言うなど、よくトラブルに発展することも多々ありました。
一方で、Aさんには、他児と楽しく関わりたいといった動機もありました。
著者はなんとかAさんが他児と楽しく関わることができるために、集団活動における遊びにおいて〝弱い中枢性統合″が一つの課題となっている状況を打破する方法を試行錯誤していました。
2.中枢性統合を理解する理論・書籍
細部に着目しやすい傾向のある自閉症児(者)は、その特徴から、細部をより探求するジャンルにおいてはむしろ強みになることがあります。
一方で、私たちの生活は物事の全体像を理解しないとうまくいかないことも多くあります。
著者は、次の著書を参考に、自閉症児の中枢性統合の弱さへのアプローチを取ることを心がけてきました。
書籍:「下山晴彦(監修)(2018)公認心理師のための「発達障害」講義.北大路書房.」
それでは、〝中枢性統合の弱さ″に対するアプローチのポイントを引用します。
・中枢性統合の弱さ:部分に注目しやすく部分を統合して全体像を把握することが苦手
➤重要でない細部に目がいく:重要点に注目しやすい工夫・全体像を把握できる工夫
➤物事の意味理解を促す
以上の引用文を支援の現場に活かすために、著者は次の支援内容を構想しました。
ポイントは、集団活動における遊びにおいて、①遊びの全体像を最初に提示する(動画や画像がある場合は活用する)、②その中で必要最低限のルールを事前に提示する、③日々の活動の中で遊びの繋がりを意識した声がけをする(役割・ストーリー性など)などを意識して関わっていきました。
3.支援の経過と結果
前述した①~③のポイントを中心とした支援を意識することで、Aさんは少しずつ集団活動での遊びの全体像を理解できる場面が出てきました。
もちろん、遊びには予めルールがある程度しっかりと定まっているもの(カードゲーム・ボードゲームなど)から、ごっこ遊びなどより想像性や柔軟性が求められるといったルールが曖昧な遊びまで多様にあります。
Aさんにとって、予めルールの枠がしっかりあるものの方が、遊びの全体像を理解は非常に早く進んでいきました。
この時に、説明書や動画での解説などが中枢性統合の弱さを補う上で非常に役に立ったと感じています。
一方で、ごっこ遊びに関しては、関わり手が遊びのルールやポイントを分かりやすく伝える工夫が必要です。
著者は遊びはじめにAさんに守って欲しいルール(守ることで遊びが楽しくなるという点を考慮して)を伝えること、○○という目標・目的を目指すこと(遊びの全体像を促す)、その中で、子どもたち一人ひとりに共通のあるいは異なる役割があること、そして、過去から現在までの時間の中での遊びの展開(ストーリー性)などをポイントに続して伝えていきました。
その結果、Aさんは集団活動における遊びにおいて、遊びの全体像を理解しながら動く様子が増えていきました。
そのため、他児とうまく関われる様子も増えていったと実感しています。
さらに、Aさんのこうしたポジティブな変化には、中枢性統合の力が高まったことにプラスして、他者の心の状態(心の理論)に対する理解が進んだことも大きな要因だったと感じています。
大切なことは、重要な点にフォーカスした伝達、物事の全体像が理解できるための工夫、物事の関連性・意味づけを伝えることだと思います。
4.まとめ
自閉症児(者)には、物事の細部に着目しやすく、全体像の把握を苦手とした弱い中枢性統合が見られます。
そのため、支援においては、全体把握を促すための働きかけ(重要点の整理・伝達、全体像を把握できるための工夫、物事の繋がりといった意味理解を促すなど)が重要な視点だと言えます。
書籍紹介
今回取り上げた書籍の紹介
- 下山晴彦(監修)(2018)公認心理師のための「発達障害」講義.北大路書房.
その他、自閉症児の中枢性統合の理解に参考になる書籍紹介
自閉症に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「自閉症に関するおすすめ本【初級~中級編】」