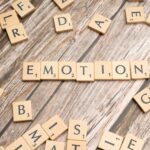愛着障害の子どもへの対応として、キーパーソン(子どものことを一番よく知っている人)との1対1での関わりを通した〝先手支援″が重要だと考えられています。
キーパーソンが子どもに先立って対応することで、子どもはキーパーソンへの信頼感を高めていくことができます。
関連記事:「【愛着障害の子どもへの対応で必要な先手支援】主導権を握ることの重要性を通して考える」
一方で、先手を取る行為の中には、〝厳しく子どもを注意する″ことで、子どもの行動を縛るケースもあると言えます。
それでは、愛着障害の子どもに対して、厳しい対応をすることで良い効果が期待できるのでしょうか?
そこで、今回は、愛着障害の子どもに対する厳しい対応には効果はあるのか?について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「米澤好史(2018)やさしくわかる!愛着障害 理解を深め、支援の基本を押さえる.ほんの森出版.」です。
愛着障害の子どもに対する厳しい対応には効果はあるのか?
以下、著書を引用しながら見ていきます。
よく見られることですが、担任の先生が「先手」を取って、厳しい対応をすることを宣言し、「こういうことをしてはいけない」とあらかじめこどもたちの行動を縛る対応があります。失礼な言い方で恐縮ですが、いわゆる「恐怖政治」です。
この対応が、愛着形成・愛着修復がしっかり意識された支援であったかどうかは、担任の先生が替わった際に確認できます。
著書の内容から、愛着障害の子どもに対して、厳しい対応をすることは、いわゆる〝恐怖政治″とも言え、その効果は、担当者が変わった際に顕著に見られると考えられています。
つまり、担当者が厳しい対応を取っていた人から、優しい人へと変更になった際に、急に子どもが荒れ始めたのであれば、支援はうまくいっていない、効果はなかった、さらに言えば、悪化したと言えます。
著書には、この原因として、これまで厳しい対応を受けていた子どもが、過度に我慢を強いられていた状態が、解放されることで、愛着障害に見られるネガティブ行動が顕在化したのだと考えられています。
そして、さらにまずい状態は、新しい優しい人の対応がまずいと周囲から非難を受けてしまうことだとされています。
このように、愛着障害の子どもに対して、厳しい対応を取ることは、長期的に見て効果が期待できないと言えます。
著者の経験談
著者はこれまで様々な療育現場に携わってきています。
その中には、程度の差はあるものの、愛着に問題を抱えている子どもたちが多くいたことが推測できます。
そして、こうした子どもたちへの対応には、関わり手の考え方の違いがあったのも事実だと思います。
中には、今回見てきたように、〝厳しい対応″を取ることで、子どもの行動を統制することに非常に重きを置いていた人もいたと思います。
いわゆる〝恐怖政治″となっていたケースもあったと思います。
一方で、こういった人の対応により、子どもたちのネガティブ行動がうまく抑えられていた場合も少なからずありました。
そのため、周囲から見ると、対応・支援方法が良いと錯覚してしまう場合もあるのだと思います。
かつての著者も、子どもが落ち着いている姿(本来は我慢しているだけ)を見て、〝厳しい対応″の人のやり方には効果があるのでは?と少なからず思い込んでいた時期もあったほどです。
一方で、こうした子どもたちは、〝厳しい対応″をする人の様子をじっくり観察していたり、その人がいないとネガティブ行動が急に見られるようになったりなど、どこか〝このやり方は良いのだろうか?″と感じることもありました。
現在は、子どもにとっての安心感・安全感を作ることを重視して、長期のスパンで子どもたちとの信頼関係を構築することを心がけています。
この視点の方が、著者のこれまでの療育経験及び知識からの学びを踏まえても、高い効果が期待できると実感でするようになったからです。
やはり、〝厳しい対応″は、子どものポジティブな行動を形成することには繋がっていかないのだと思います。
以上、【愛着障害の子どもに対する厳しい対応には効果はあるのか?】療育経験を通して考えるについて見てきました。
愛着障害の子どもに対する〝先手支援″はとても大切です。
一方で、〝先手支援″について、子どもに対して、事前に行動を制限するような〝厳しい対応″をしていくことが望ましいと勘違いしないことが重要です。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も愛着障害への理解・対応方法について、さらなる学びを継続していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「愛着に問題のある子の支援-「叱る」対応の問題点について-」
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
米澤好史(2018)やさしくわかる!愛着障害 理解を深め、支援の基本を押さえる.ほんの森出版.