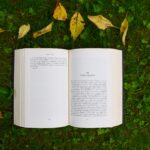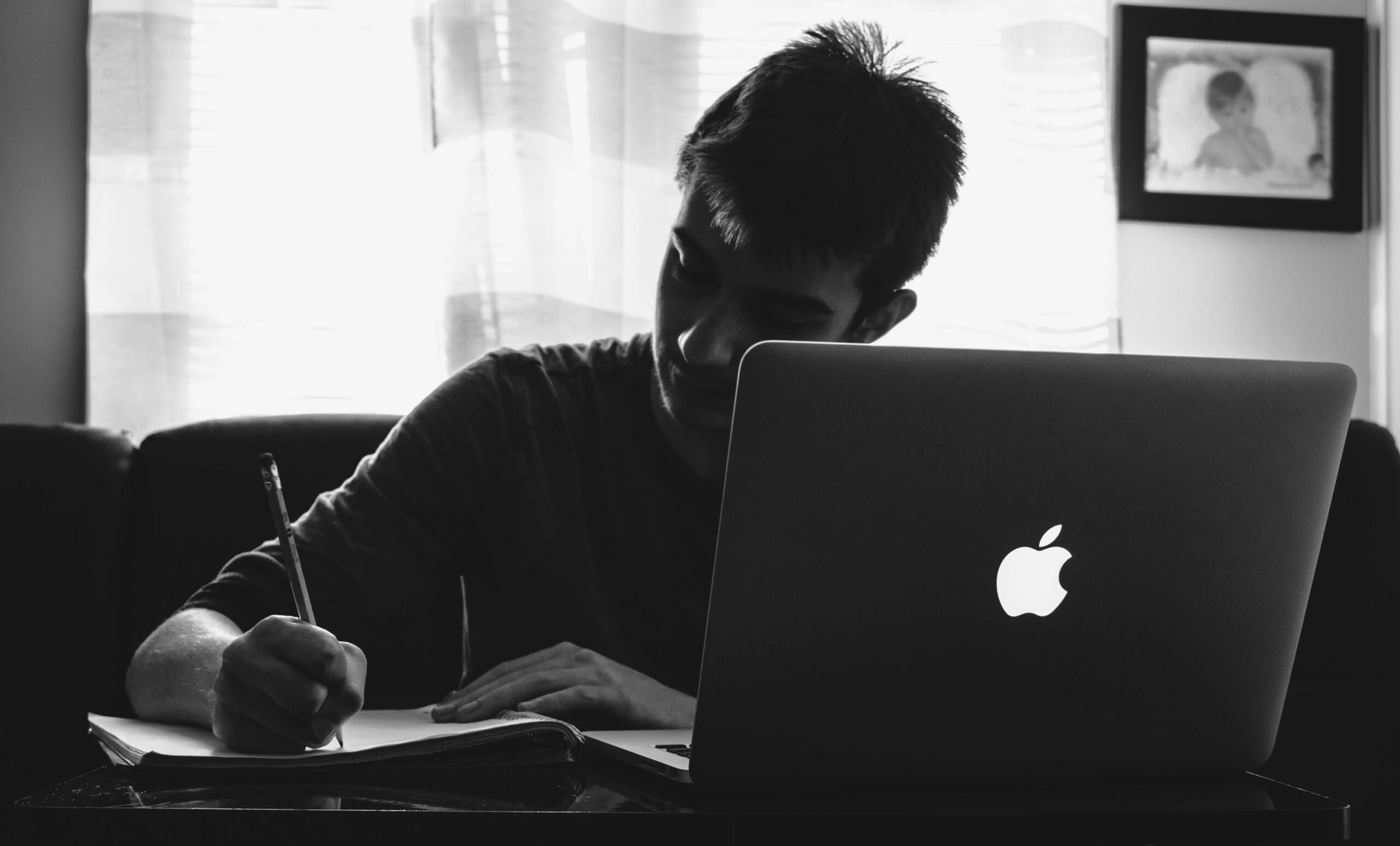
今回は前回の続きとして、著者が療育実践で非常に役に立った視点についてお伝えします。
(前回の記事では、①太田ステージ、②感覚と運動の高次化理論についてお伝えしました。どちらも、発達初期の感覚と運動の段階から概念理解までの発達段階を詳細に記述した内容、そして、それぞれの段階に応じた遊びや教材教具などの工夫すべき点などが説明されています。詳細は「【発達支援(理論編):療育実践で役立つ視点】太田ステージ・感覚と運動の高次化理論」。)
今回取り上げる理論・視点は、③感覚統合理論、④関係論的アプローチになります。
これらの理論・視点を知ることで、著者は障害のある子どもたちの発達段階についての理解が加速度的に進んだと実感しています。興味のある方は参考までに調べてみて下さい。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
③感覚統合理論
エアーズという方が考えた理論です。
人間が持つ様々な感覚の特徴やそうした感覚に過敏・鈍感さがあると行動としてどういった特徴があるのかなどが解説されています。また、感覚の過敏・鈍感さについての対応方法なども書かれています。
エアーズの書籍は翻訳本であり、理論的な部分で少し理解が難しい感じがします。そのためお勧めなのは、作業療法士の木村順さんがいくつか書籍を出していますので、こちらを参考にしていただけると非常にわかりやすいかと思います。
中でも私がお勧めするものは、「育てにくい子にはわけがある」という本です。
こちらの本を読んでいただけると、感覚統合の理論がわかりやすく解説されており、専門的な用語もわかりやすい解説がついてますので初心者の方にも参考になると思います。
今の療育現場では感覚統合は非常に普及してきたという実感があります。
私自身、前職場と今の職場において研修などのテーマで感覚統合について取り上げたものも何度かあり、職員間で話に上がることが増えている印象があります。
私も感覚統合理論について理解が進むことで、これまで当たり前と思っていた、自分の感覚と障害のある子どもたちの感覚が非常に異なるという視点が得られたと感じています。
感覚統合に関しては、いくつか記事に書いていますので、もしよろしければ参考に見てみて下さい。
感覚統合理論に関するお勧め書籍紹介
④関係論的アプローチ
関係論的アプローチは、人と人との関係そのものを取り扱った考えになります。
様々な専門家が本を出していますが、その中で私がお勧めするものとして、鯨岡峻さんと小林隆児さんの書籍があります。
前者の鯨岡峻さんは、現象学という学問をベースに人と人とが関係性を持つことはどのようなことか、その過程ではどのようなことが生じているのかを詳細に記述しています。
後者の小林隆児さんは、自閉症などの発達障害について、そもそも関係性を構築することが難しい事例などを通して、関係性を構築するためのヒントやその過程でどのような現象が生じているのかを関係論的アプローチから記述しています。
どちらも専門書となっていますので、簡単に読みこなすことは難しいかもしれませんが、人が人を理解することの大切さや難しさが深く理解できると思います。
私自身、療育現場で日々子どもたちとの関わりの中で、うまく関係が築けない、今の状況は、はたしてうまくいっているのかなど、日々悩みながら現場に臨んでいました。
さらに、障害のある子どもたちを相手にしているため、関係性の面でより専門的な知識や理解が必要だと感じていました。
今回紹介した著者の本には、こうした現場の問いに応えてくれる有益な情報が豊富に記載されていると感じます。
私は関係論的アプローチの考え方で相手のとの関係性に関して、自分の取り組みを見直したり、より深い意味を見出すなど多くのヒントを得ることができたと実感しています。
関係論的アプローチに関するお勧め書籍紹介
以上が、療育実践において役に立った視点の続きの紹介になります。
今後はこうした内容に関して、現場の子どもたちをより深く理解できたと感じた内容に関して深堀していきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
関連記事:「【発達支援(理論編):発達支援の現場で役立つ視点】発達特性・愛着」