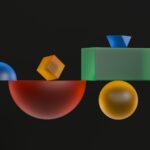人との関わり方が難しい、相手の意図や考えがよくわからない、相手の表情が読み取りにくいなど対人関係の難しさを特徴とした自閉症といわれる人たちがいます。
職業柄、私は自閉症児・者と関わる機会が多くありますが、自閉症の人たちにも様々なタイプがいるかと思います。
それでは、人との関わりが難しいとされる自閉症児において、どのような関係作りが必要なのでしょうか?
そこで、今回は自閉症についての特徴を説明していきながら、私が実際に療育現場で自閉症のお子さんと関わった体験談を関係性の視点からお伝えしていきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「アメリカ精神医学会 高橋三郎・大野裕(監訳)(2014)DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院.」です。
自閉症について
自閉症とは、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)によると、自閉症スペクトラム障害(Autism Spectrum Disorder:ASD)と定義されており、①持続する相互的な社会的コミュニケーションや対人的相互反応の障害、②限定された反復的な行動、興味、または活動の様式といった2点を主な特徴としています。②の下位項目の中には、知覚の過敏性・鈍感性といった知覚異常を含みます。
簡単に言うと、対人関係やコミュニケーションなど社会性の困難さや、自分なりのやり方にこだわる、臨機応変に行動を変えることが難しい、感覚が過敏だったり鈍感だったりするという特徴があります。
例えば、「お風呂を見てきて」と言われた際に、湯加減を見に行くところをただじっとお風呂場を見ているなど、相手が伝えたかった意図を状況を踏まえて判断するのが難しい、また、本の並び方や通学路の道順は必ず自分なりの法則があるなどのこだわり、大きな音や子供の泣き声にとても敏感などとった例もあります。
また、上記の特徴がありながらも、スペクトラム(連続体)ですので、非常に自閉症も人それぞれ多様であるということが言われています。他の障害、知的障害や注意欠如/多動性障害、学習障害、発達性協調運動障害などとの併存もよく見られます。
以上が簡単にではありますが自閉症についての概要となります。
著者の体験談(自閉症児との関係性の構築について)
ここから先は私が療育現場で関わった自閉症児A君との関係性をつくるうえで苦労した点や理解や支援についての話をしていこうと思います。
A君は自閉症であり、発語も単語が少し言えるという知的発達のお子さんでした。
私との初対面はとにかく近づくとすぐに距離を取り離れていく、数日経っても数週間経ってもこの状態が続きました。少し積極的に距離を近づけようとすると時には怒りを露わにさせることもありました。
私はA君と一体どうすれば仲良くなれるのか考える日々が続きました。A君の好きな絵本を手に取り近くで読むなど、彼の興味関心から関係性を深めようとしました。
しかし、興味関心から様々な試みをするも惨敗に終わりました。そんなある日、A君がしていたおもちゃ遊びと同じ遊びを少し離れたところで試しにやってみました。しばらくするとA君は少し気になりだしたのかこちらを見ていました。しかし、私は何も反応しませんでした。すると、さらにA君は距離を縮めてこちらを見続けました。そこで、A君が遊んでいたおもちゃ遊びを少し私なりにアレンジし発展させて遊び始めました。A君はさらに興味を示し、とうとう私に触れる位の距離で遊びをじっくり見はじめました。
この日を境に、A君は私がやっていることに興味を示す機会とそれを近くで見ようとする様子が増えてきました。こうした日々がしばらく続いた後、A君はお気に入りのおもちゃを私のところまで持ってきて”やってみて”と以前私がやっていた遊び方が見たいとお願いしてきました。
こうした彼からの要求に応える中で、A君からの笑顔やスキンシップ行動も出てきました。A君と手を繋げた日、抱っこできた日は私の中で感動体験として残っています。周りの職員たちからは「いつの間に仲良くなったのですか?」と言われることも多かったです。当然、保護者の方も喜んでくれました。
この経験の中で、A君は人がどのように動くのか予測できない、自分のテリトリーを侵されるのではないかという不安などを強く感じていたのではないかと私は仮説を立てました。
そこで、この人は大丈夫だと安心してもらえるようにゆっくり関係を作ることに決めました。言葉にできないA君との距離感や視線などをヒントにしながら、興味関心を活用しゆっくり距離を縮めることに成功しました。距離が縮まるとこれまでは想像できなかった体を使ったダイナミックな遊びができるようになり、大声で喜ぶ声や、何度も”遊ぼう”とお願いする様子も増えました。まさに、関係性が変化することでA君の世界が広がり始めたのだと思います。
自閉症といっても様々な方々がいます。
テキストで行動の特徴を学べる部分も多くある一方、現場で時間をかけなければ学べないこともあると思います。
今回のように関係性に困難を抱えていても、相手を理解しようとする姿勢があれば少しずつ前進できるのではないかと思います。
もちろんその過程で、自閉症の方々の行動特性を知ることは非常に大きな意味を持ちますし、経験を重ねながら深まっていくことあります。
ここに挙げたのは一事例ですが、非常に私に関係性の大切さを教えてくれた貴重な経験です。
この経験があったからこそ相手とじっくりと時間をかけて向き合うことの大切さを深く実感しました。今後も、関係性について経験と知識からその理解を深めていこうと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
アメリカ精神医学会 高橋三郎・大野裕(監訳)(2014)DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院.