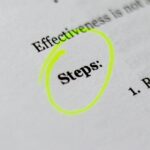人とコミュニケーションをとることを苦手としている自閉症の人たちは学校や会社、地域社会という集団環境の中で様々な配慮が必要になるかと思います。
私自身、療育現場などで多くの自閉症の人たちと関わる機会がありましが、その中で、安心できるコミュニティの重要性を感じています。
それでは、対人関係など人との関わりが難しいとされている自閉症の人たちにとって、どのようなコミュニティ作りが必要なのでしょうか?
今回は、自閉症の人たちが集団の中で生きる上で重要な概念である「ネスティング」を取り上げながら、コミュニティ支援について考えていきたいと思います。
そして、私もコミュニティの中で自閉症の人たちを支援してきた経験の中で大切だと考える点についても併せてお伝えしていこうと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回取り上げる資料は「本田秀夫(2017)自閉スペクトラム症の理解と支援.星和書店.」になります。
【自閉症へのコミュニティ支援の重要性について】ネスティングをキーワードに考える
それではさっそく「ネスティング(nesting)」についてですが、そもそもネスト(nest)とは、動物の巣、大きな入れ子という意味があります。
つまり、大きな社会の枠組みの中に、目的をもった小さな社会が入れ込まれた状態のことを言います。
自閉症の人たちは、その発達特性上、興味関心の偏りが強くあります。ですので、そういった特性に応じた活動拠点(nest)が必要になるというわけです。
一般社会の中では、社会の中に意識的に入れ込むという発想が重要になります。そういった居場所づくりは、社会の中でうまくいかなくなってから作るというより、初めから居場所があるということが二次障害の予防という観点からも大切です。
例えば、小学生が普段は多くの時間を学校で過ごしており、放課後や休日は「鉄道研究会」、「料理研究会」という感じでサブ・コミュニティに所属しているというイメージです。
自閉症の人たちは自分の興味関心であれば多くを語りたい、マニアックな内容を共有したいということもあるので、そういったコミュニティの形成を意識的に作るという発想が重要です。
著者のコメント
次に、私が自閉症の人たちと関わりから感じるコミュニティの重要性についてお伝えしていきます。
私は現在小学生を対象とした放課後等デイサービスで支援員として働いています。
そこには自閉症の人たちも多く来ています。彼らと関わっていると、自分の興味関心に火がつくと近くにいる大人を捕まえるなどして多くを語り始めます。内容は人それぞれですが、電車、アニメ、ゲームなどの話が多いです。
普段は一人で黙々と本を読んでいるお子さんも、自分の興味関心が他児と重なると他児に話しかけたり、質問したりという様子も見られます。
そういった経験を通して、「今日は○○君いる?」など興味関心から繋がった他児が来るのを楽しみにする様子がでてきます。さらに、その集団がより大きくなり、子供たちから遊びを考えだしたり、より仲間を意識した関わりも出てきます。
また、保護者の方々からも「○○君と会えるのを家でも楽しみしています」などと、ご家庭でも楽しかった様子を話しているのだと感じます。
そうした様子を見ていると、改めて彼らの興味関心が保障された環境が大切であると感じます。こうした経験を通じて、仲間意識や大人とのより良い関係性の構築、居場所感などにも寄与すると思います。
私は以前ある自閉症の成人男性とコミュニティについて非常に考えさせられる言葉を聞いたことを今でもはっきりと覚えています。
彼は「一つのところでうまくいかないことがあり、そこでつまずいた。だから、複数の場所があることが大切です。」という言葉でした。
これを聞いて確かに納得しました!我々はコミュニティといっても仕事や家庭、友人を通したコミュニティなど複数の居場所があります。そうしたコミュニティが複数あるということが大切だと彼の言葉を聞いて感じました。
私たちは複数のコミュニティに所属することで、多くの刺激や安心感などが得られ、バランスをとって生活しているのだと思います。
今後は自分たちが所属したいコミュニティを複数持ち、その中で仲間意識や自分の役割や貢献できることなど、より個々に応じて生き方が多様化してくると思います。
自閉症の人たちは自分からコミュニティを探し、関係を一から作ることを苦手としています。ですので、意識的に彼らが安心でき、そして、興味関心などからコミュニティを作るという発想が大切だと思います。
私も仕事を通して、彼らが安心できる環境の保障と楽しめる活動作りを継続していきながら、より良いコミュニティのあり方について考えていきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
本田秀夫(2017)自閉スペクトラム症の理解と支援.星和書店.