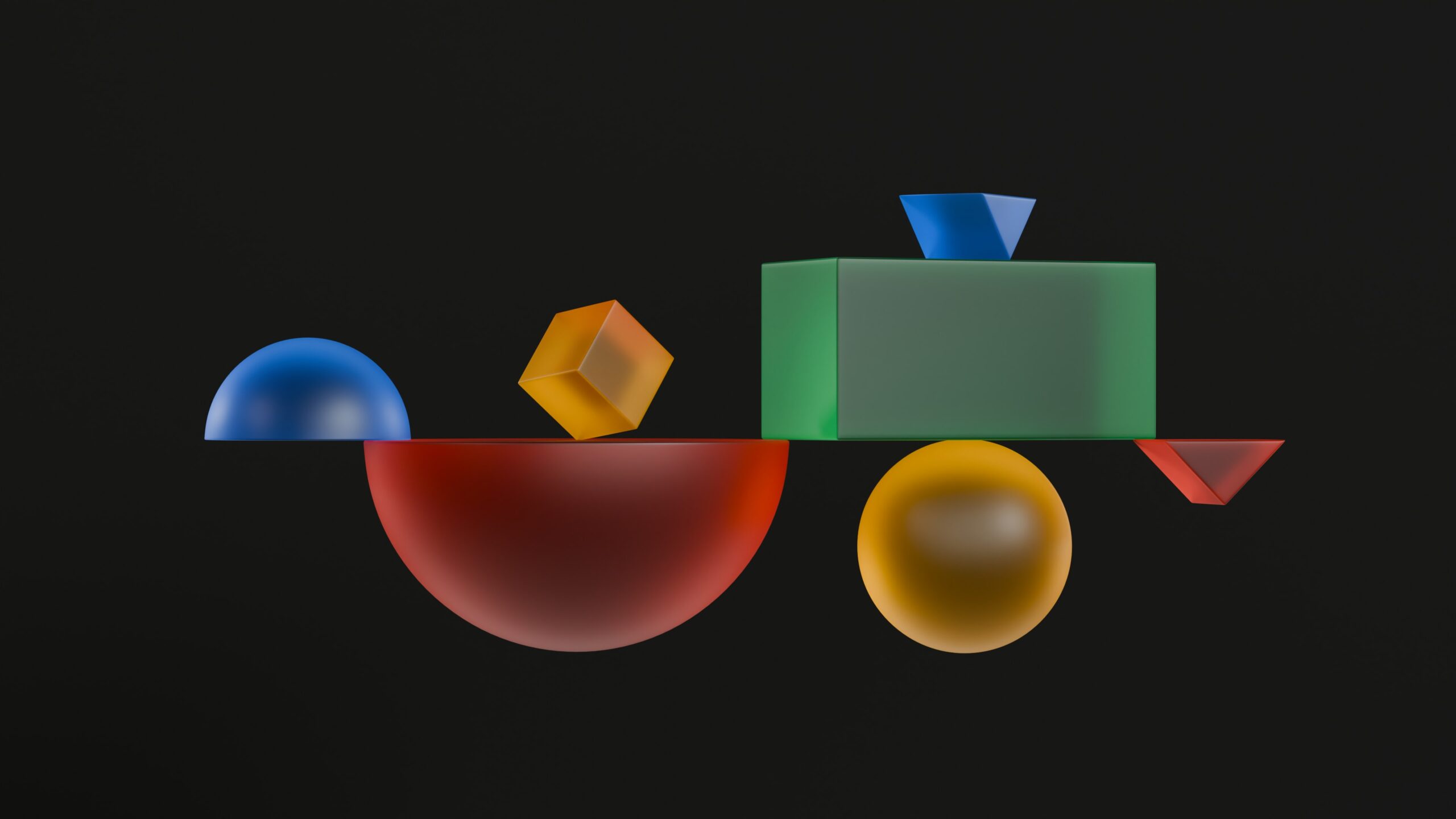
自閉症(自閉症スペクトラム障害:ASD)は、対人・コミュニケーションの困難さと、〝こだわり行動”を主な特徴としています。
〝こだわり行動“には、、作業の手順や道順、物の配置など、様々な内容があります。
自閉症のこだわり行動は、時には関わり手にとっては、付き合い方なども含め、対応が難しい場合があります。
それでは、自閉症に見られるこだわり行動は、発達の過程でなくなることはあるのでしょうか?
そこで、今回は、自閉症のこだわりはなくなるのか?について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、「こだわり」保存の法則を通して理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は、「本田秀夫(2017)自閉スペクトラム症の理解と支援.星和書店.」です。
自閉症のこだわりはなくなるのか?「こだわり」保存の法則を通して考える
自閉症のこだわりについて、〝本田秀夫“さんは多くの臨床経験からある法則を見つけました。
それが、「こだわり」保存の法則になります。
以下、「こだわり」保存の法則について見ていきます(著書引用)。
その人のこだわりたいというエネルギー量は、一生を通じてほぼ一定だという経験則です。こだわりのエネルギー全体の量は一定ですが、こだわりの対象は時々変わります。
著者の内容には、こだわりの総エネルギー量はほとんど変わらないため、こだわりのエネルギーが大きく減ることはないが、こだわる対象が変化することはあるという法則があると記載されています。
このように、〝こだわり行動“の総エネルギーは年齢が経過してもあまり変わらないとされています。
一方で、こだわりの対象には変化があるとされています。
例えば、「道順」へのこだわり→「物の配置」へのこだわりへの変化などがあると言えます。
認知の発達による「こだわり」の変化について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
子どもが成長して、認知が発達するにつれて、「こだわり」の内容も発達してきます。
著書の内容には、こだわりは認知が発達すると、その内容が変わると記載されています。
例えば、車好きでミニカー遊びをしていた子が、車の本や車の図鑑などよりマニアックな知識を得るようになるといった変化があります。
このように、認知が発達(物事を理解する力の成長)することで、こだわりの内容にも変化が見られると言えます。
著書の体験談
著者の療育現場でのある体験です。
未就学児のA君は、著者が数年間にわたって関わることがあった自閉症の男の子です。
A君のこだわりは順番です。
最初にA君がこだわり出したのは、大好きな絵本シリーズでした。
登園するとA君の日課は、大好きな絵本シリーズを著者と一緒に読むことでした。
その順番も決まっており、すべて読み切らないと、次の活動に移行することが難しいほど、毎朝、同じ絵本シリーズを読むことから活動がはじまっていました。そして、その後、朝の会という流れになっていました。
その後、A君は大好きな絵本シリーズにも飽き、次に選んだのが、絵本シリーズよりも難易度が高くこれまでほとんど関心のなかったジャンルであるトーマス図鑑でした!
よりによって図鑑!と思いましたが(読み切るまでに時間がかかるので・・)、これも決って、登園後の最初のルーティンとして組み込まれていきました。
A君が最もこだわったのは「順番」でした。つまり、○○の活動をして、次に○○の活動・・とったルーティンは変わらなかったと言えます。
そして、このエピソードから、こだわりの対象は移るも、こだわりのエネルギーの総量は変わらないといった印象を受けました。
次に、成人のBさんです。
Bさんもまた、自閉症の特性のある男性です。
昔のBさんが興味を持ったのが、数字です。
数を紙に書くということを繰り返すほど数字に魅了されていました。
その後、年齢があがるにつれ、電卓いじり、カードゲームの戦闘力の数字の暗記など、数字に関連する特定の興味関心に関する活動が発展していきました。
Bさんのこだわりは、「数字」であり、認知の発達により、「数字」に関連する遊びにも変化が見られるようになっていきました。
以上、自閉症のこだわりはなくなるのか?「こだわり」保存の法則を通して考えるについて見てきました。
これまで見てきたように、こだわりのエネルギーの総量はそれほど変わらない(こだわりはなくならない)ことや、認知が発達することで、こだわりの内容に変化が生じる場合があると言えます。
一方で、こだわり行動は、本人なりの意味があり、また、考え方・関わり方次第では強みになるとも言えます。
関連記事:「【自閉症児・者のこだわり行動の強みについて】療育経験を通して考える」
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も、自閉症の特性をさらに理解していけるように、こだわりへの理解を深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
自閉症に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「自閉症に関するおすすめ本【初級~中級編】」
本田秀夫(2017)自閉スペクトラム症の理解と支援.星和書店.









