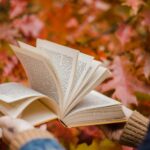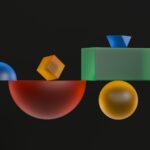知能検査で代表的なものに、ウェクスラー式知能検査(WISC)があります。
WISC‐Ⅳでは、4つの群指数(言語理解、知覚推理(知覚統合)、ワーキングメモリー、処理速度)と全検査IQの測定が可能となっています。
関連記事:「ウェクスラー式知能検査とは【発達障害の理解と支援で役立つ視点】」
それでは、様々なある発達障害の中で、例えば、自閉症(ASD)にはどのような能力の特徴があるのでしょうか?
そこで、今回は、知能検査から見たASDの特徴について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、得意と苦手な能力について考えを深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「岡田尊司(2020)自閉スペクトラム症 「発達障害」最新の理解と治療革命.幻冬舎新書.」です。
知能検査から見たASDの特徴について【得意と苦手な能力とは?】
以下、著書を引用します。
ASDの場合、他の能力に比して、処理速度が相対的に低い傾向があります。
ASDの中にもいくつかのタイプがありますが、言語や知能が比較的優れたアスペルガータイプでは言語理解が高く、処理速度が低い傾向を示すことが多いと言えます。
カナータイプと呼ばれる、元々自閉症と呼ばれていたタイプでは言語理解が弱く、むしろ視覚的情報処理の能力が高いのが特徴です。つまり、知覚推理が相対的に高く、言語理解が低い傾向を指します。
著書の内容を見ても分かるようにASDにも様々なタイプがあり、タイプによって得意と苦手さに違いが見られます。
著書の内容を整理すると、ASDには以下の3点の特徴があります。
1.ASDは、処理速度が低い傾向がある。
2.ASDは、アスペルガータイプだと、言語理解が高く、処理速度が低い傾向がある。
3.ASDは、カナータイプだと、言語理解が弱く、視覚的理解が高い傾向がある。
それでは次に、以上3つについて著者の経験談も交えて考えを深めていきたいと思います。
著者は発達障害のある子どもたちに療育をしていますが、子どもたちだけではなく成人のASDの方とも様々な関わりがあります。
そのため、ここから先は、子どもから大人を含めたASDの特徴についてお伝えします。
1.ASDは、処理速度が低い傾向がある。
ASDの処理速度の苦手さはよく見受けられます。
例えば、作業のスピードが遅い、作業効率が悪いなどがあります。
具体的なものとして、パソコン作業の入力、筆記の速さ、掃除など整理整頓スキルなどの際に苦手さが目立つように感じます。
これは、作業が非常に丁寧であり、〝ある程度で大丈夫“といった曖昧さが苦手なことや、不器用さなど運動スキルの苦手さなどが影響しているように思います。
一方で、一つのタスクを黙々とこなす力は非常に高いため、人によっては、繰り返しの練習の結果、作業内容にもよりますが処理速度がとても高くなっていると感じる方もいます。
実際に、処理速度が高く当の本人も作業スピードが速いと話されていたASDの人もいました。
このように、ASDは一般的には、処理速度が低い傾向がありますが、作業内容や練習次第で非常に個人差がでるように思います。
2.ASDは、アスペルガータイプだと、言語理解が高く、処理速度が低い傾向がある。
アスペルガータイプとは、ASDの中でも知的に遅れのないASDの特性がある人たちのことで、人昔前には、非常によく使用されていたタイプです(DSM-5以降から、ASD:自閉症スペクトラム障害に全て統一された)。
特徴としては、著書にあるように、言語理解が高いといった特徴があります。
著者の周囲でもアスペルガータイプの方はいますが、確かに言語理解が高く、言語によってロジックで考えていくのを得意としている印象があります。
ロジックとは、AならばB、BならばCという話の組み立て方であり、逆に、Aから一気にCという直感的な推理は苦手としている印象があります。
また、先のASDの処理速度の低さもあるように思います。
3.ASDは、カナータイプだと、言語理解が弱く、視覚的理解が高い傾向がある。
今ではあまり聞かなくなりましたが、知的障害ありのASDの特徴が非常に強い人たちのことをカナータイプといっていた時期もあります。
カナータイプには、知的に遅れが見られるため、言語による情報理解の困難さが目立つという特徴があります。
自閉症を有名にした映画に「レインマン」があります。
その時、出演している主人公がカナータイプの役を演じています。
著者が以前勤務していた療育現場には、重度の自閉症児が多くいました。
こうしたカナータイプの人たちは、言語理解は確かに苦手ではありますが、一方で、視覚的な情報理解は得意な印象があります。
著者が言葉でいってもうまく伝わらない自閉症児に、絵カードなどを活用した結果、コミュニケーションがスムーズに進むようになったと感じたケースは多くあります。
以上、知能検査から見たASDの特徴について【得意と苦手な能力とは?】について見てきました。
検査から見たASDの特徴を述べてきましたが、もちろん、個人差があります。
あくまでも傾向の話ですので、個々に応じた理解と対応が療育現場には必ず求められます。
一方で、先に見てきた特徴は現場でも実感できることが多いため、ASDを理解する手掛かりになると感じます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も知能検査・発達検査など客観的なツールを活用した子どもたちへの理解についても学びを深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【自閉症の人に向いてる仕事・向いてない仕事】療育経験を通して考える」
発達障害のアセスメントに関するお勧め書籍紹介
関連記事:「発達障害のアセスメントに関するおすすめ本【初級~中級編】」
岡田尊司(2020)自閉スペクトラム症 「発達障害」最新の理解と治療革命.幻冬舎新書.