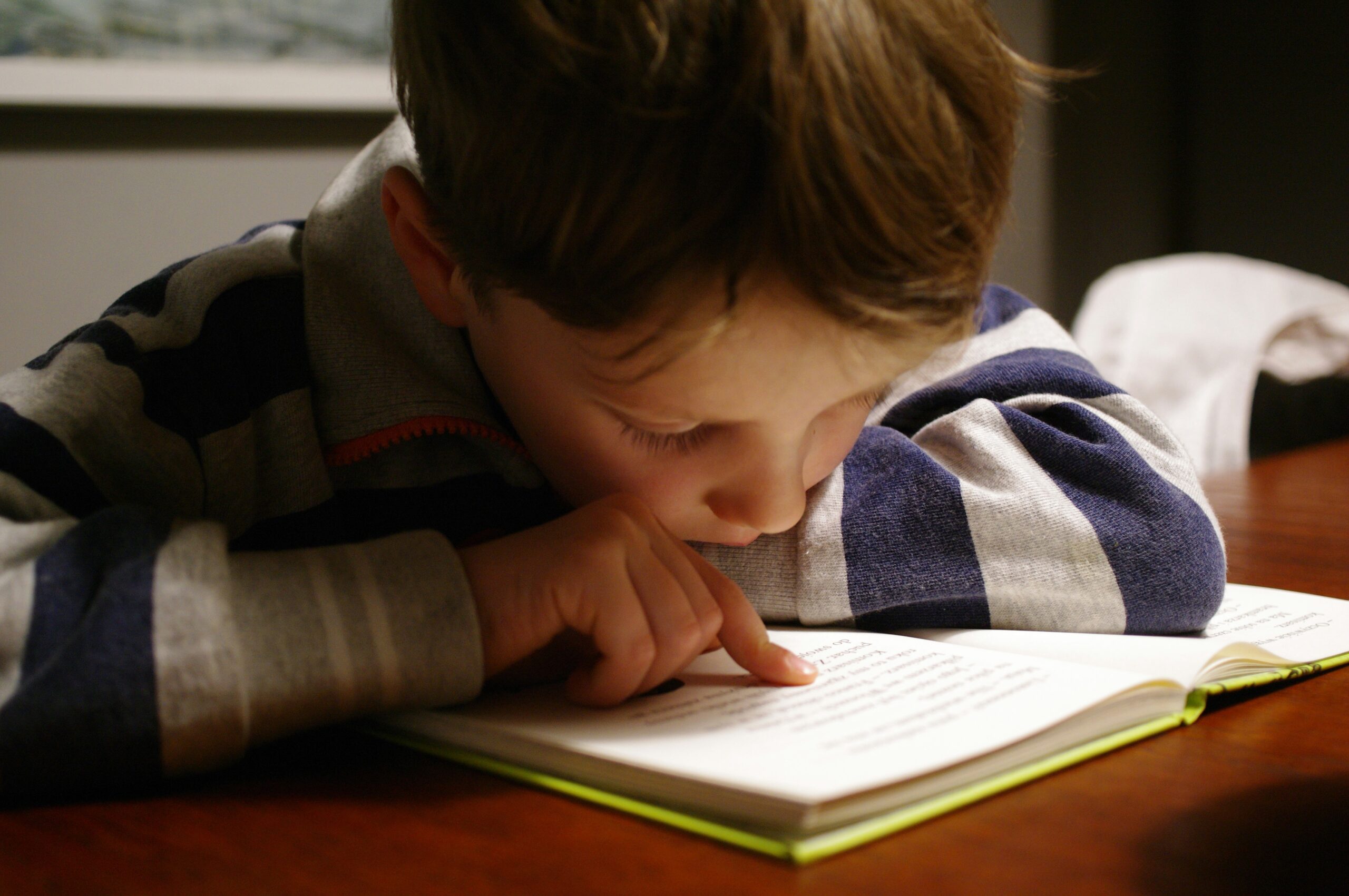
著者は発達障害の子どもの療育に長年携わってきています。
療育とは、治療的側面と教育的側面を併せ持っており、著者が現在勤める放課後等デイサービスなどでは、子どもの状態像から教育的側面からのアプローチを重視しています。
この領域にいると、そもそも発達障害は治るものなのか?といったことをよく耳にします。
そこで、今回は、著者の療育経験も踏まえ、発達障害の専門家である医師の杉山登志郎さんの著書を参考に、発達障害の治療について教育の重要性についてお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は、「杉山登志郎(2018)子育てで一番大切なこと:愛着形成と発達障害.講談社現代新書.」です。
発達障害の治療について-教育の重要性から考える-
以下、著書を引用します。
「これも“治る”という言葉の定義によるのですが、発達障害はきちんと対応していけば、年々良くなっていくのですよ。ですからもちろん治っていくわです。」(略)
「(略)子どもに合った教育をするというのは、どの発達障害であっても一番大事なことですが、とりわけサブに位置する3つの発達障害、不器用さ、学力、言葉の習得に対しては、医療によるアプローチには限りがあります。(略)どれも、子どもに合わせた適切な教育が治療に効果的なんですよ」
以上、著書からの引用となりますが、著書の中で医師の杉山登志郎さんは教育の重要性を指摘しています。
まず、発達障害は治るのか?といったことに対して、治るというのは、言葉の定義次第でその意味するものが変わっていくと言及しながら、対応次第では良くなっていくと述べています。
対応の中で、医療的アプローチには限界があり、中でも、不器用さ、学力、言葉の習得に関して個々に応じた教育の働きが大切であるとしています。
それでは、次に、著者の療育経験をもとに教育の重要性についてお伝えします。
著者の経験談
著者の経験で、療育(特に教育的側面)の重要性を実感することが強くあります。
そうした中で、教育的アプローチで著者が重要だと考えるものに、①発達の最近接領域と②興味関心からのアプローチがあります。
①発達の最近接領域について
発達の最近接領域とは、子ども一人でできること、そして、大人の力を借りればできること、という二つの状態を見極め、その差分を教育の力で伸ばしていくという考え方になります。
例えば、工作遊びで、剣を作りたい子がいた場合に、作る過程の中で切る・貼る・書くなどの操作能力や完成品をイメージして材料を選んだり、それぞれの材料を構成するなどの様々な力が必要になります。
こうした力の中で、その子一人ができるところ(例えば、ハサミで切るなど)と、大人がサポートしてできるところ(例えば、材料を構成する)を見極め、少しずつ手伝う所を減らしていくことが大切になります。
実際に、初めはほとんど大人が作っていた段階から、数年後、ほとんど一人でできるようになったという事例も多くあります。
先ほど、引用文でも取り上げたように、不器用さ、学力、言葉の習得などは特に教育的働きがとても大切だと感じます。
不器用だった子が、先ほどの工作の例でもあったように、道具の操作が少しずつできるようになるなど、不器用さが少しずつ良くなってきたという事例もあります。
関連記事:「発達支援の専門性について:発達の最近接領域から考える」
②興味関心からのアプローチについて
その他、教育で重要な視点として、子どもの興味関心を把握し、そこからアプローチしていくというものがあります。
先ほどの工作の例では、作るものが武器なのか、車なのか、虫なのかは子どもの興味関心によって変わってきます。
興味関心の入り口は異なってもその過程で、物を操作する能力、構成する能力、イメージを形にする力など、その中で共通する能力が育まれる点は多くあるかと思います。
興味関心からアプローチすることによって、子どもが何かを学びたい・作りたい・知りたいという動機づけが高まり、主体的に行動する様子が増えいくという実感があります。
関連記事:「【自閉症児への支援】興味の世界を広げるために大切な関わり方」
以上、発達障害の治療について、教育の重要性について述べてきました。
教育の方法は人の数だけあると思います。
また、長い時間をかけてじっくり取り組む必要があるため、ある種、忍耐も必要になってきます。
しかし、年数をかけて子どもの状態が良くなることは関わり手のモチベーションにもなりますし、その経験は欠くことのできない財産になります。
私自身、まだまだ未熟ではあるものの、年々、療育(教育的側面)の重要性を実感するようになってきています。
今後も、より良い発達理解と発達支援を目指して頑張っていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
杉山登志郎(2018)子育てで一番大切なこと:愛着形成と発達障害.講談社現代新書.
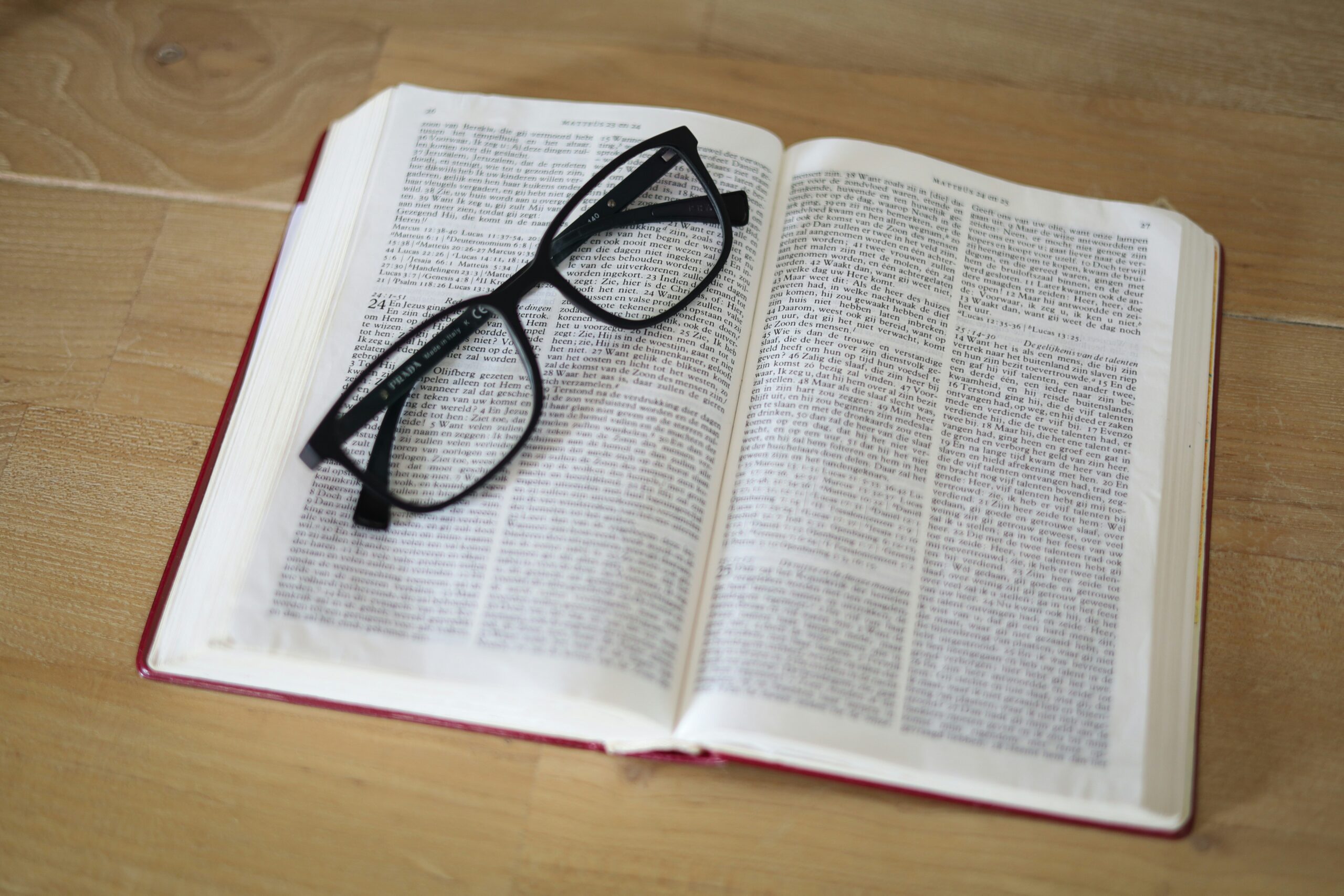

コメント