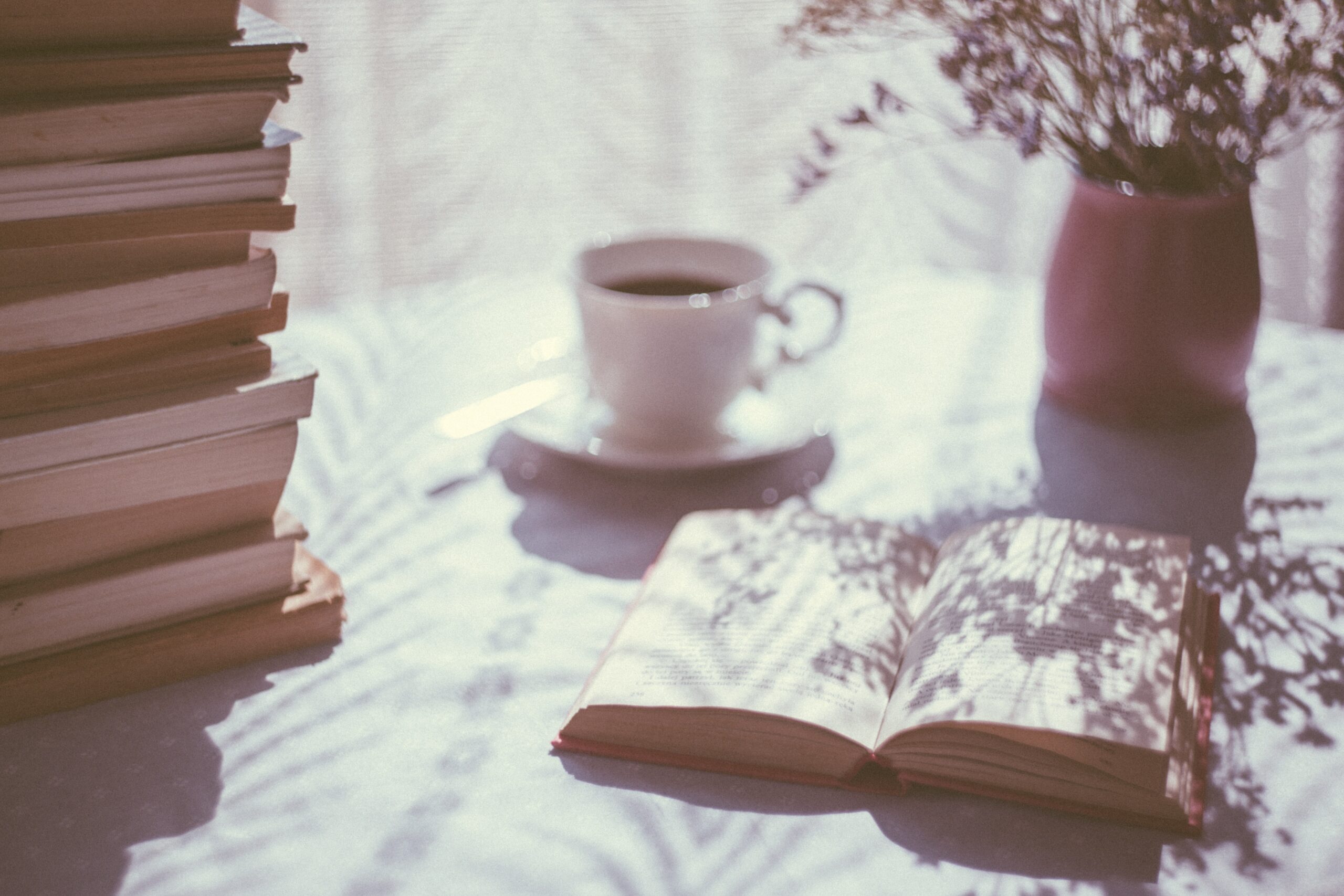
発達障害のお子さんを持つ保護者の人たちにとって、子育ての苦労は想像以上に大変なことがあります。
もちろん、人それぞれ大変さの内容や質は異なります。
苦労を少しでも和らげるためには、発達障害の子の特性や関わり方についてある程度の知識を持っておくことも一つの方法になります。
それでは、発達障害の子育てをより深く理解する上でどのような知識が必要になるのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害の子育てを理解する上で非常に参考になるおすすめ本8選【中級編】について紹介していきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
実際にこれから紹介する本を通して著者自身、発達障害の子育てに関する理解が深まった、支援の役に立った等、有益な知識を得ることができました。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
1~8の番号はランキングではありません。紹介内容を見て入りやすい本から手に取って頂けるといいかと思います。
1.赤ちゃん~学童期 発達障害の子どもの心がわかる本
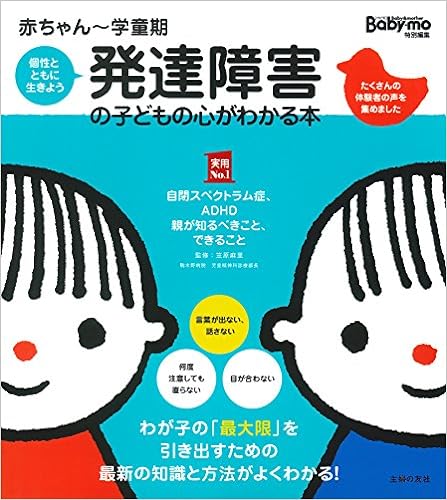
タイトルにあるように、赤ちゃんから学童期までのライフステージを対象に、発達障害に関する知識を分かりやすく解説した本となっています。
発達障害にも様々ありますが、本書では、自閉スペクトラム症とADHDの特性と関わり方が記載されています。
年齢別の対応編では、0歳~成人を迎える頃までが取り上げられているため、将来を見据えての関わり方や大切にしたい点について学ぶことができます。
最後の章では体験談とQ&Aも載っているため、実体験についても掘り下げて学ぶことができます。
イラストも多いため発達障害を学ぶ入門書だと言えます。
2.発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ
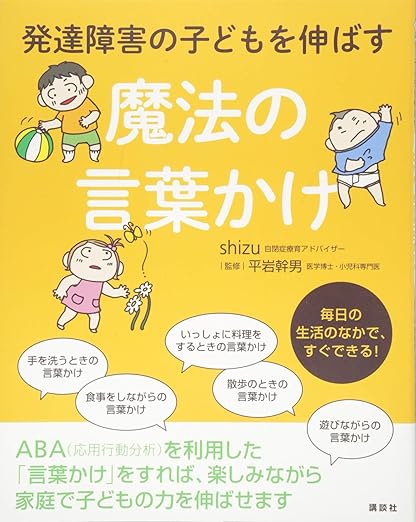
大人がかける言葉の積み重ねによって子どもの自信ややる気、その後の行動には大きな違い生じます。
本書では、ABAといった応用行動分析を活用した〝言葉がけ″の方法が豊富に解説されています。
日々の生活の中で実践できるもののため、今日から即行うことができます。
イラストも豊富にあり、実践のポイントなども分かりやすく説明されているため初心者の方にとってもお勧めです。
3.子どもの発達障害 子育てで大切なこと、やってはいけないこと
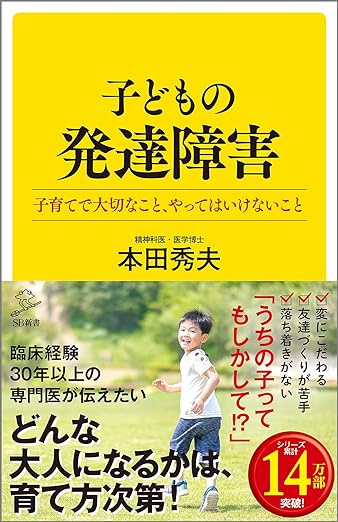
発達障害領域では大変著名な精神科医・医学博士の〝本田秀夫さん″が書いた本になります。
第一章では子育てを考えるクイズからはじまり、発達障害の概要、そして、褒め方・叱り方、暮らしの中で大切な場面別のポイント、などから構成されています。
様々な事例を取り上げながら、事例解説と対応方法が分かりやすく載っているため、子育て上で起こる困り事や対応についてヒットする内容が多く見つかると思います。
この本を読むことで、何を大切にして子育てをしていけば良いのかそのヒントを得ることができる本となっています。
4.子育てで一番大切なこと 愛着形成と発達障害
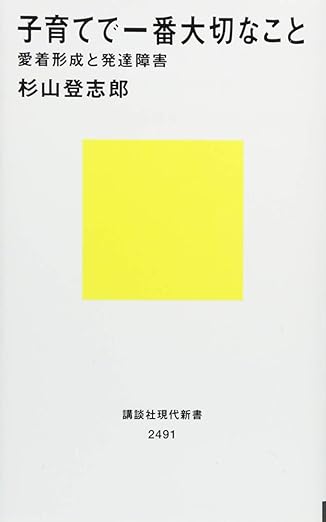
児童精神科医の〝杉山登志郎さん″が書いた本になります。
内容としては、現代の子育て、子育ての基本、発達障害と愛着障害、貧困問題、乳幼児期~小学生時期の子育て、社会で子どもを育てること、残された課題、などから構成されています。
中でも、タイトルにあるように、幼少期の愛着形成がその後の発達において非常に重要であることが強調されています。
この本を通して、現代の子育てについての概要と子育てをしていく上で大切にしたいことを学ぶことができます。
5.「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する
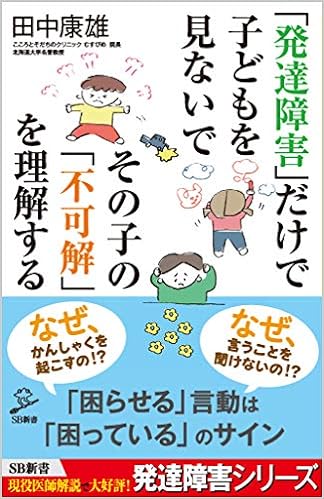
発達障害領域で大変著名な〝田中康雄さん″が書いた本になります。
この本は、タイトルにある通り、〝発達障害″といった診断名だけで子どもを見ずに、子どもが取る様々な行動・言動の意味を紐解いていくことの重要性が記載されています。
内容としては、乳児期から思春期といったライフステージにおいて、12のストーリー(不可解な問題)とそれに対する解説があります。
後半には、診断を超えてその子に近づく方法へのヒントが載っています。
〝診断名″という枠組みを外し子どもの理解に迫りたいと考えている方に特にお勧めです
6.「発達障害」と間違われる子どもたち
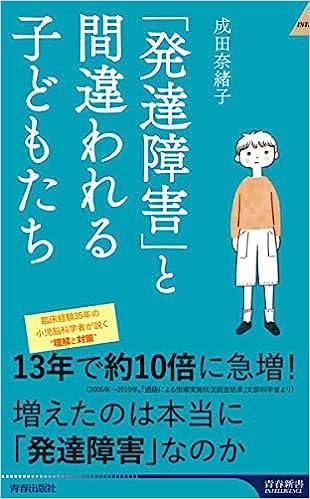
本書は、臨床経験30年の小児脳科学者〝成田奈緒子さん″が書いた本になります。
近年、発達障害が急増する中、なぜここまで増加したのか?本当に発達障害なのか?という問いに対してある種の見解を与えてくれる本です
発達障害と似た状態の人たちを〝発達障害もどき″から説明し、〝もどき″から抜け出す方法、そして、子育てにおける大切な関わり方について様々な示唆を与えてくれる本です
7.自分でできる子に育つほめ方り方
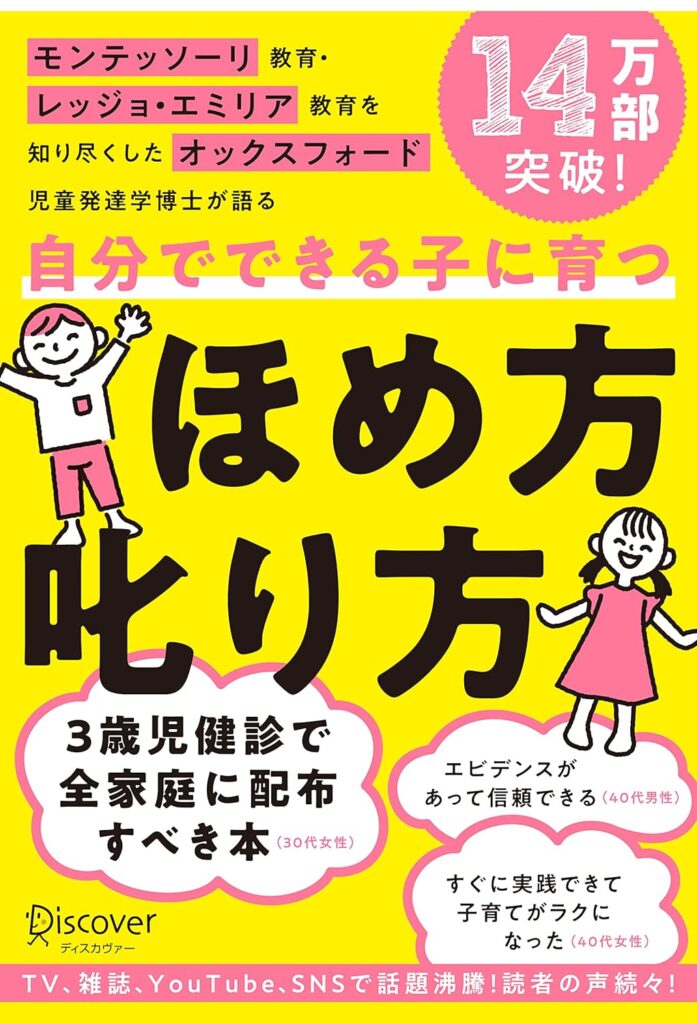
タイトルにある通り、モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育が基盤となっているほめ方・叱り方の本です。
子どもの主体性を引き出すためのほめ方・り方が豊富に記載されています。
子どもはただほめたり叱れば良いわけではなく、しっかりと自己肯定感を育んでいけるような声掛けの仕方があることを教えてくれる本です。
発達障害のある子どもも含め、子育て中のすべての大人の方にお勧めできる本です。
8.発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編

発達支援コンサルタントの〝小嶋悠紀さん”の本になります。
この本では、家庭・生活でよく起こりうる、発達障害グレーゾーンの子どもの困り事に対して、どのような声掛け・接し方が有効であるのかについて、非常に分かりやすく解説されています。
どのようにすれば子どもを叱らずに育てることができるのか?楽に関わることができるのか?について、多くのヒントを与えてくれる本となっています。
イラストも豊富なため、初心者の方にとってもとても読みやすいものとなっています。
関連記事:「発達障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「発達障害の支援に関するおすすめ本【初級~中級編】」










