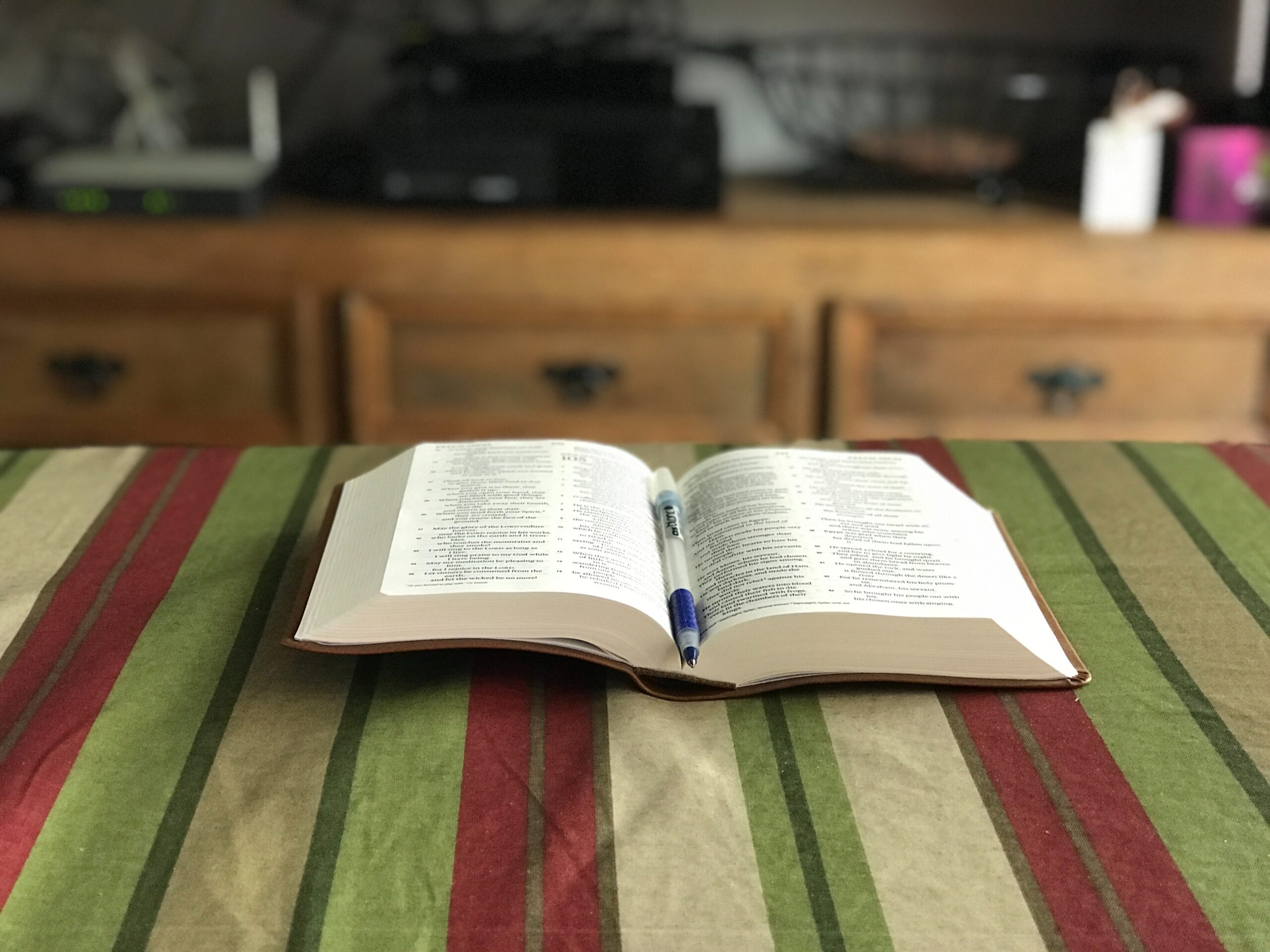
発達障害のある人たちが‟二次障害”を生じているケースは多いと感じます。
著者の療育現場で関わりの難しさを感じるケースの多くは二次障害が生じている、あるいは、二次障害傾向が見られる子どもたちだと感じています。
それでは、二次障害はどのような原因により発症するのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害の二次障害について、二次障害が生じる原因について考えを深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「齊藤万比古(編著)(2009)発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート.学研.」です。
発達障害の二次障害について【二次障害の原因とは何か?】
以下、著書を引用しながら見ていきます。
著書の中には、二次障害出現の悪循環の図が記載されています。
その図の流れを以下に記載します(〇→本人の心理・行動、●→周囲の心理、関わり方)。
発達障害の症状・気質
↓
〇社会的対処法の問題(乱暴さ、唐突、固執、孤立)
↓
●周囲の否定的対処の増加(しかる、ネグレクト、いじめ)
↓
〇自尊心の低下、無力感、空虚感、不安、気分の落ち込み、怒り
↓
〇否定的社会行動の増加(反抗、暴力、放浪、受動攻撃性、ひきこもり)
↓
●周囲の怒り、無力感、罪悪感、回避の増加
↓
〇社会的対処法の問題(乱暴さ、唐突、固執、孤立):初めに戻る
以上が、著書の中で二次障害が出現する負の流れになります。
最初に発達障害の症状・気質があります。
これは、ASDやADHDなどの発達特性があるということです。
次に、社会的対処法の問題(乱暴さ、唐突、固執、孤立)があります。
これは、発達特性への対処方が乱暴さやこだわり行動など、社会的に見て(周囲から見て)ネガティブへ方向へと働いた状態になります。
例えば、ADHD児が、やりたことがうまくいかない時に、言葉でその気持ちを周囲に伝えるのではなく、手が出てしまうなど攻撃行動で不満を示すなどが該当するかと思います。
次に、周囲の否定的対処の増加(しかる、ネグレクト、いじめ)があります。
これは、先のネガティブな対処方法に対して、周囲の関わり方が否定的な対応が増えていくというものです。
例えば、先のADHD児のネガティブな行動に対して、注意や叱責といった否定的な対応が増えていくということがあると思います。
次に、自尊心の低下、無力感、空虚感、不安、気分の落ち込み、怒りがあります。
これは、自分の行為に対して、周囲から否定的な関わりを受けたことで、自分に対して否定的な感情が湧いてくる、強まってくるということに繋がってきます。
例えば、周囲から叱責を繰り返されたADHD児が、〝自分なんてダメだ!“、〝ダメな人間だ”、〝何をやってもうまくいかない“、〝周囲は自分のことをわかってくれない”などの感情があるかと思います。
次に、否定的社会行動の増加(反抗、暴力、放浪、受動攻撃性、ひきこもり)があります。
これは、マイナス感情の増加を社会的に好ましくない形で表出するというものです。
例えば、ADHD児によくある傾向ですが、外在化と内在化があります。
外在化とは、ネガティブな感情を外に出すというもので、反抗や暴力などがあります。
一方、内在化とは、ネガティブを内に留めるというもので、不登校やひきこもりなどがあります。
次に、周囲の怒り、無力感、罪悪感、回避の増加があります。
これは、社会的に好ましくない行動の増加によって、周囲の注意や叱責がさらに増える一方、これでの関わり方が悪かったと感じる罪悪感、また、無力感や関わりを回避するなど、養育者の考え方や養育スタイルにもよりますが、周囲の様々な関わり方に違いが出てきます。
そして、上記に上がっている内容は、どれも負のスパイラルを増長することに繋がっていくように思います。
以上の流れが繰り返されることで、二次障害が悪化していくということになります。
以上、発達障害の二次障害について【二次障害の原因とは何か?】について見てきました。
二次障害の対応で非常に大切なのは、できるだけ早期に症状の悪化を防いでいくことです。
そのために、福祉・医療機関と早期に繋がりを持つことはとても意味のあることだと思います。
著者はこれまで二次障害が見られる人(その傾向がある人)を見てきましたが、関わってきて大切だと実感していることは、早期に支援機関と繋がり、その子にあった療育を受けることや、保護者が一人で抱え込まない環境を作っていくことにあると思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も二次障害を予防するために、そして二次障害への早期の対応ができるように、現場でできることを考えていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「発達障害の二次障害について【療育経験を通して考える】」
二次障害に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「発達障害の二次障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
齊藤万比古(編著)(2009)発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート.学研.









