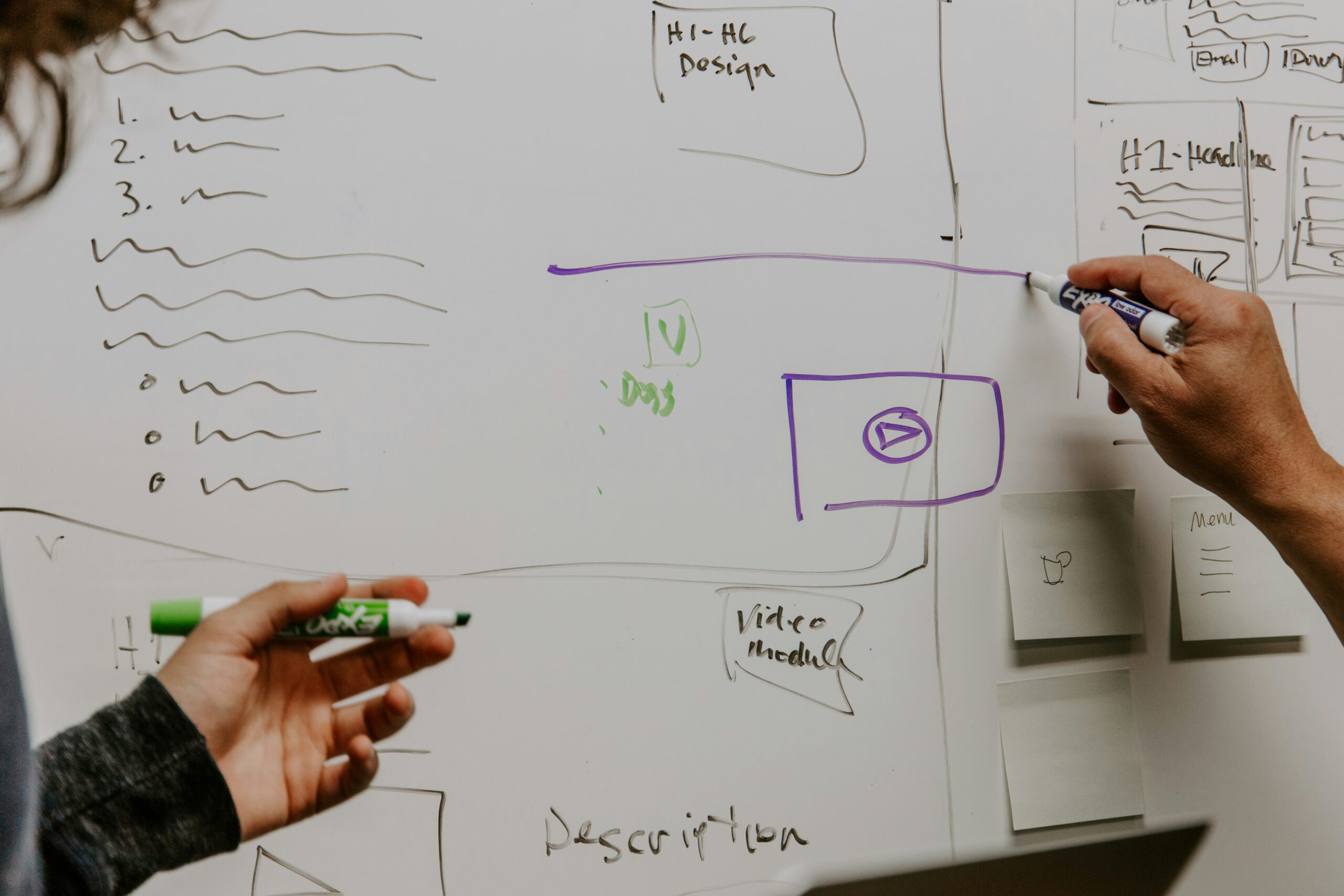
発達障害とは、自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如多動症(ADHD)・限局性学習症(SLD)などを主な症状としています。
日本では、書籍やメディアなどを通して、専門家や当事者、そして当事者の家族による発達障害の困難さや生きにくさに関する情報発信が増えてきています。
少子化が進む中でも発達障害の診断や疑いを受けた人は増加傾向にあります。
増加傾向の要因には、様々な諸説はありますが、その一つに発達障害が見逃されてきたケースが非常に多いと考えられています。
そこで、今回は著者の経験も交えながら、発達障害増加の原因とは何かについて、発達障害が見逃されやすいケースを例(自閉スペクトラム症を例)にお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は「岡田尊司(2020)自閉スペクトラム症:「発達障害」最新の理解と治療革命.幻冬舎新書.」です。
【発達障害増加の原因とは?】発達障害が見逃されやすいケースを例に考える
以下、著書を引用します。
発見が遅れやすいのは、運動や言語の発達に遅れがみられないケースです。学童期に不適応を起こして、ようやく気づかれることが多く、中には大人になっても気づかれないまま放置されるケースも少なくありません。
著書の内容から、発達の遅れ(運動・言語など)が顕著に目立たないケースが発見が遅れやすいということになります。
著者もこれまで、様々な発見に躓きのある子どもたちを見てきましたが、社会の中で理解や支援を受けにくいのは、発達に顕著に遅れがあるケースよりも、グレーゾーンや軽度の発達障害だと実感しています。
それは、関わってみるとなんとなく社会の中でやっていけそうだと思える点も多くあるからです。
一方で、こうした曖昧な状態は本人の生きにくさの理解とは解離しているため、理解や支援を怠ると二次障害に繋がるリスクも出てきます。
最近では発達障害への社会的な理解や診断の精度も高まっていますが、その前の世代、なかでもグレーゾーンや軽度の発達障害がある方(疑いのある方)が大人のケースで潜在的に非常に多いことが予測できます。
それでは、発達障害が見逃されてきた世代・割合などはあるのでしょうか?
以下、引き続き著書を引用します。
自閉スペクトラム症についての認識があまりなかった時代には、知的遅れなど、目立った発達の遅れがないケースは、ほとんど診断から漏れ、いまでは五十代、六十代に達していることも多いのです。約三分の二から四分の三のケースが見逃されていると言われています。
著書の内容では、知的遅れなど発達に顕著な遅れがなかった場合は、診断から漏れ(その可能性が高まり)、世代としては、50代以降にも多く存在しているとあります。
また、割合として、約三分の二から四分の三ということなので、半数以上を優に超えるということになります。
つまり、発達障害増加の原因として考えられる一つの要因は、これまで発達の顕著な遅れがないことで周囲に気づかれずに、大人になってから分かり始めた人が増加していることが想定されます。
著者のコメント
著者は成人期の発達障害の文献を調べていく中で、40代以降が非常に社会の中でうまくいかないケースが多いといったものを目にしました。
発達障害は何かの時点で急に症状としてでるものではなく先天性の症状なので、40代以降といってもそれ以前に、うまく行かない状態が度々あったことが想定されます。
この世代は発達障害に対する社会的な理解が進んでいなかったこともあり、本人及び周囲の理解も非常に遅れていることが多いと考えられます。
当然ですが、こうした発達障害そのものの理解が遅れていたことが、診断の漏れや、その後の社会での不適応状態の要因として考えられます。
その他にも、社会の中で求められる役割が増える(変わる)ことが一つの要因として考えられます。
例えば、結婚や子育て、職場の中で重要な立場を担いながら後輩の指導や育成など、非常にマルチタスクと高いコミュニケーション能力が求められるからです。
こうしたマルチタスクやコミュニケーション能力が求めれるのが現代社会ではとても必要とされるのがもう一つの要因だと考えられます。つまり、社会環境の変化です。
自閉スペクトラム症が増加したのは、社会環境がよりコミュニケーションやマルチタスクを必要とするようになったからだという専門家もおります。
著者の周囲にも成人の発達障害の方が多くおります。
こうした人たちと関わる中で大切だと実感したのは、社会の中で理解されてこなかった状態が続いていたということだと思います。
その人の困り感はその人になって見ないとわからないとよく言われますが、同調圧力の強い日本の社会構造そのものが発達障害を生んでいるとの見方もできます。
つまり、社会側の基準やルールで障害を生んでしまっているという視点が今後ますます必要になってくると思います。
これが、医学モデルから社会モデルへという考え方だと言えます。
多様性のある社会を目指すことは簡単ではありませんが、まず必要なのは当事者目線で物事を考えてみることだと思います。
そのために、日々の生活の中の小さな困り感を当事者の方と一緒になって考えてくことの積み重ねで、少しずつその生きにくさを実感できるように思います。
私自身、まだまだ未熟であり、発達障害への理解もまだまだ不十分ですが、今後も現場での実践を通して、子どもたちの困り感に寄り添いながら、一緒に日々を前進していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
岡田尊司(2020)自閉スペクトラム症:「発達障害」最新の理解と治療革命.幻冬舎新書.









