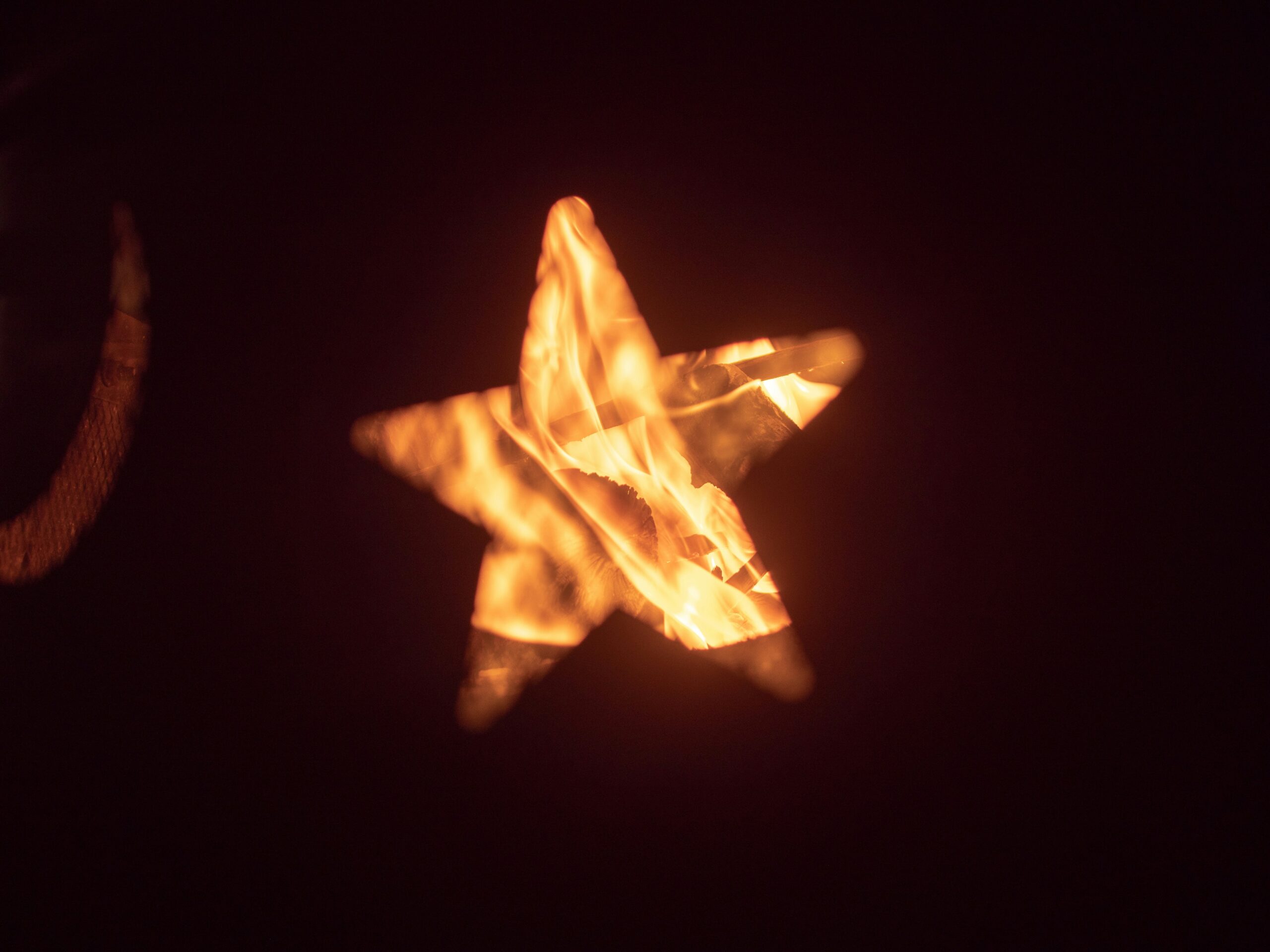
発達凸凹の子どもは、認知(物事を捉え方)の個人内差が定型発達児よりも顕著に見られる人たちのことを言います。
また、発達凸凹の中には、、AS(自閉スペクトラム症)やADH(注意欠如多動症)など様々な発達特性を持っており、その中には、発達障害(=発達凸凹+適応障害)の人たちもいます。
関連記事:「【発達凸凹とは何かについて】療育で必要なことについて考える」
それでは、こうした発達凸凹の子どもの対応として、子育てをする上でどのような点が大切となるのでしょうか?
そこで、今回は、発達凸凹の子どもの子育てにおいて大切なことについて、5つのポイントを通して理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「杉山登志郎(2011)発達障害のいま.講談社現代新書.」です。
【発達凸凹の子どもの子育てにおいて大切なこと】5つのポイントを通して考える
以下、著書を引用しながら見ていきます。
発達の凸凹への具体的な対応としては、どうやら個別の対応のほうが効果が高いようだ。つまり、親への心理教育がとても有効で、また必要である。
著書の中では、発達凸凹の子どもの対応として、親への心理教育、つまり、ペアレントトレーニングの有効性を指摘しています。
そして、子育ての中で、どのような点を大切にすれば良いのかも記載されています。
以下、再び著書を引用しながら見ていきます。
1.子どもがどんな体験世界にいるのか
2.子どもへの接し方、子どものための環境調整
3.愛着の形成がどのような経過をたどるのか
4.決してしてはならないことの知識
5.大まかな年齢ごとの課題
以上、5つを上げています。
それでは、次に、以上の5つそれぞれについて具体的に見ていきます。
1.子どもがどんな体験世界にいるのか
子どもの中の体験世界を知ることはとても大切です。
例えば、自閉スペクトラム症の子どもは興味関心が人よりも特定の物に向かいやすい傾向があります。また、物事のやり方や手順にこだわりもあります。
そのため、関わる人は子どもがどのような対象に興味を持っているのかを把握していきながら、子どもの興味関心の世界を共有・共感する関わりが大切になっていきます。
ADHDの子どもであると、注意が散漫になる一方、興味のある対象に過集中する傾向もあります(ASを合わせ持っているケースもあります)。
こうした子どもの様子を見ると、周囲の大人は時にはネガティブな印象を持たれる場合もありますが、こうした行動の背景には先天的な発達特性が影響しているという理解を持ちながら関わる必要があります。
また、発達凸凹の子どもは感覚過敏・鈍感さが見られるケースも多いため、好きな感覚・苦手な感覚を理解していくこともまた必要です。
2.子どもへの接し方、子どものための環境調整
基本的な生活リズムを整えるための環境整理が必要になります。
発達凸凹があると、様々な物事に関心をもったり、過度な集中から遊びが終わらないこともあります。
そのため、周囲の環境を整えて、子どもに接していくことが必要になります。
例えば、多くの情報がある場合には、情報量を減らすことや、その日の活動予定を事前に提示しておき、早めの切り替えを促すなど、周囲の大人が極力叱責しないような環境を作る必要があります。
3.愛着の形成がどのような経過をたどるのか
愛着形成は定型発達児より遅れて形成されることがあります。
一方で、何らかの障害があっても、すべての子どもは愛着を欲しており、愛着形成は可能です。
また、自閉スペクトラム症は、定型発達児とは異なる愛着形成を見せることもあります。
関連記事:「障害児との愛着形成について【定型児との違いはあるのか?】」
関連記事:「自閉症児との愛着形成は可能か【定型児との違いはあるのか?】」
少なくとも、小学校までは多くスキンシップをとなるなど、子どもとの情緒的な関わりを大切にする必要があります。
4.決してしてはならないことの知識
療育で大切なことは、問題行動の軽減や二次障害の予防です。
そのため、子どもに過度な注意や叱責をするなど、トラウマ体験を作らないようにすることが大切です。
自閉スペクトラム症の中には、記憶力が極端に優れている子もいるため、過度な注意や叱責が後々まで残ることがあります。
また、時折当時の記憶がフラッシュバックしてパニックや癇癪を起こすこともあります。
過度な叱責により、ASの子はこれまで持っていたこだわりが増長したり、ADHの子は、反抗挑戦症などに繋がるリスクを高めてしまいます。
そのため、繰り返しになりますが、トラウマになるような過度な注意や叱責を避けることが必要になります。
5.大まかな年齢ごとの課題
発達課題という言葉があるように、ライフステージごとに様々な課題があります。
幼児期であれば、基本的な生活習慣の確立や、安定した愛着形成などがあります。
学齢期であれば、集団生活が多く入ってくるため、学校でのルールを理解し守ること、仲間関係の中での自信の構築、学ぶことでの達成感を持つことなどがあります。
中学生以降であれば、第二次性徴など自分の性を受け入れることや、親との関わりも重要ながら、自分で意思決定していく力、得意なことを見つけ伸ばすことも必要になります。
関連記事:「療育で大切なこと-学童期の課題を例に考える-」
以上、【発達凸凹の子どもの子育てにおいて大切なこと】5つのポイントを通して考えるについて見てきました。
こうして振り返ってみると、発達凸凹の子どもへの子育ては何か特別な対応が求めれるというよりも、その子の興味関心やこだわり、注意の向け方などを理解していきながら、その子に合った環境を整えていくことなのだと思います。
著者も療育現場で働いているため、発達凸凹の子どもと関わる機会は多くありますが、何か特別な対応をしているというよりも、一人ひとりを理解し、その子が日々、安心して楽しく過ごせる環境を作っていくことを大切にしています。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も子どもたちのことを理解していきながら、保護者の方々ともしっかりと子どもの将来を見据えての対応・関わりができるように、日々の実践を大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
発達凸凹に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「発達凸凹に関するおすすめ本【初級編】」
杉山登志郎(2011)発達障害のいま.講談社現代新書.









