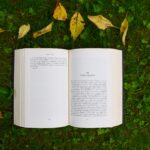放課後等デイサービスはここ近年急増しています。
そうして中で、今後はますます支援の質が重要になってきます。
放課後等デイサービスで療育(発達支援)を行い支援の質を高めていくためには、豊富な経験と知識の量とが必要になります。
それでは、放課後等デイサービスの支援の質を高めていくためにはどのような知識が必要になるのでしょうか?
そこで、今回は、放課後等デイサービスについての理解と支援の質を高めていく上で非常に参考になるおすすめ本7選【初級~中級編】について紹介していきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
実際にこれから紹介する本を通して著者自身、放課後等デイサービスに関する理解が深まった、支援の役に立った等、有益な知識を得ることができました。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
1~7の番号はランキングではありません。紹介内容を見て入りやすい本から手に取って頂けるといいかと思います。
1.放課後等デイサービスハンドブック
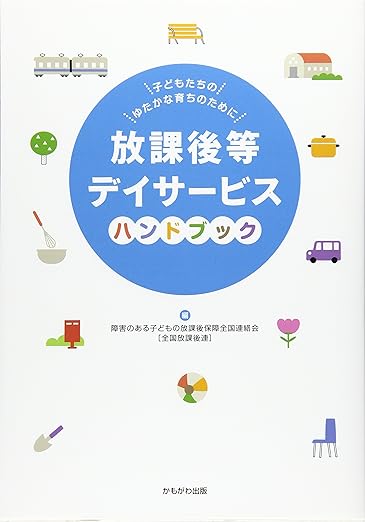
この本では、放課後等デイサービスについて、学齢期に求められる活動の特徴や制度のポイントなどが分かりやすく解説されています。
内容としては、放課後活動がめざすもの、放課後活動の実践、放課後活動の運営、放課後活動の歩みと放課後等デイサービスの課題、から構成されています。
放課後等デイサービスについての全体像が分かりやすくまとめられているため、初心者の方にとってもお勧めです。
2.障害のある子を支える放課後等デイサービス実践事例集
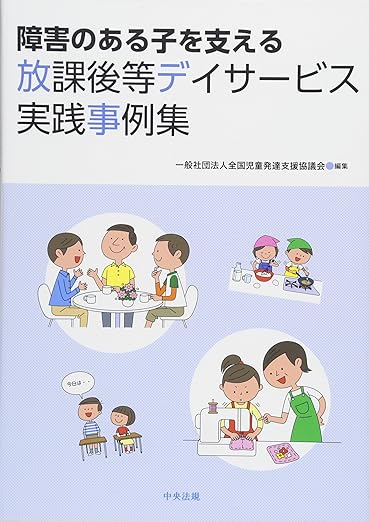
放課後等デイサービスには様々な子どもたちがいます。
そのため、子どもの状態像や困り感によって支援方針は異なります。
本書では、放課後等デイサービスでの実践が計12事例それぞれ詳しく解説されています。
それぞれの実践の内容としては、事例の紹介→個別支援計画→指導案→場面作り(複数)、の順から構成されています。
事例の内容も多岐にわたっているため、自らの放課後等デイサービスでの実践に何らかの形で活かせるかと思います。
現場の実践方法について具体的なヒントを得たいと考えている方にお勧めです。
3.放課後等デイサービスの豊かなあそびと発達支援: 個別支援の充実と地域での自立に向けて
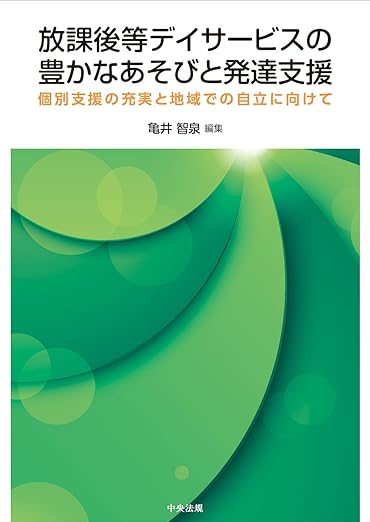
遊びは子どもの発達において必要不可欠なものです。
一方で、放課後等デイサービスで遊びを発想し、実践することは難しい場合もあります。
本書では、放課後等デイサービスでの質を高めるために、遊びをキーワードにどのような所を大切に実践していけば良いかのヒントが豊富に記載されています。
内容としては、放課後等デイサービスとは、こどもの理解とアセスメント、遊びを通した発達支援、あそびと学びの実践、本の力と発達支援、地域共生社会を作る、医療的ケアや体を理解する、感染症対策、災害対策、救急対応、から構成されています。
初心者の方にとっても分かりやすい内容となっているため、現場での遊びの実践に関する学びを得たい方にお勧めです。
4.新版 障害児通所支援ハンドブック 児童発達支援 保育所等訪問支援 放課後等デイサービス
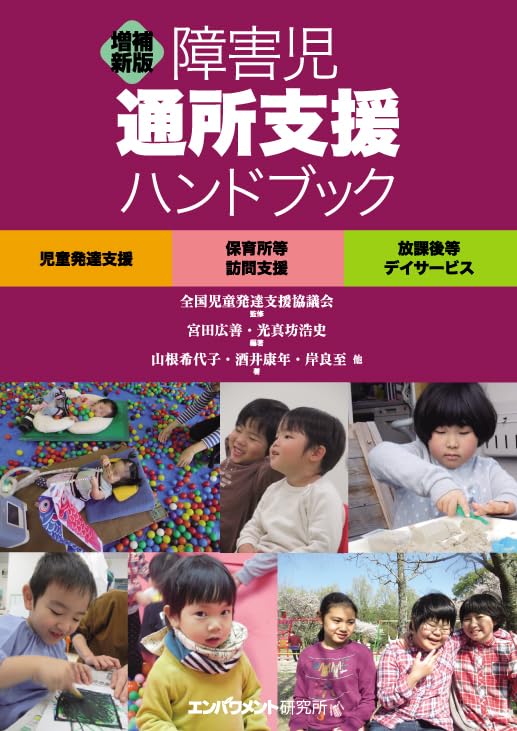
Version 1.0.0
本書では、通所支援に関するもの(児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス)から構成されています。
この本を通して、障害児の通所支援を概観できるとともに、放課後等デイサービスの事業の概要、事業の目的と重要性、事業の進め方について理解を深めることができます。
通所支援について学びたい方、放課後等デイサービスの事業に関する知識を得たいと考えている方にお勧めです。
5.社会貢献と安定収益を両立する 介護事業者のための児童デイサービスの始め方
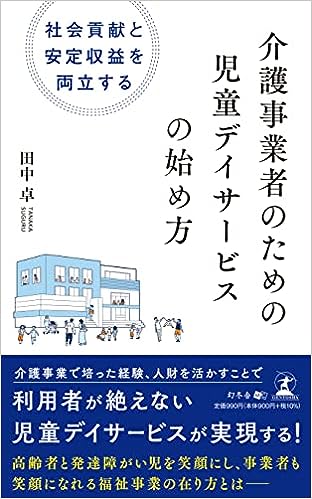
社会貢献を行うためには、安定した収益もまた必要不可欠です。
著者の〝田中卓さん″は、もともとは介護事業をされている方です。
本書は、介護事業のノウハウを活かし、児童デイサービスにその知見を活用し、利用者が途絶えない、介護事業と児童デイサービスの両輪の実現を目指すことを目的として書かれたものです。
そのため、放課後等デイサービスの事業運営についてのヒントを得たいと考えている方にお勧めです。
内容としても、新書本のため、少ない分量で分かりやすい内容となっています。
6.放課後等デイサービス 5領域に対応 療育トレーニング50
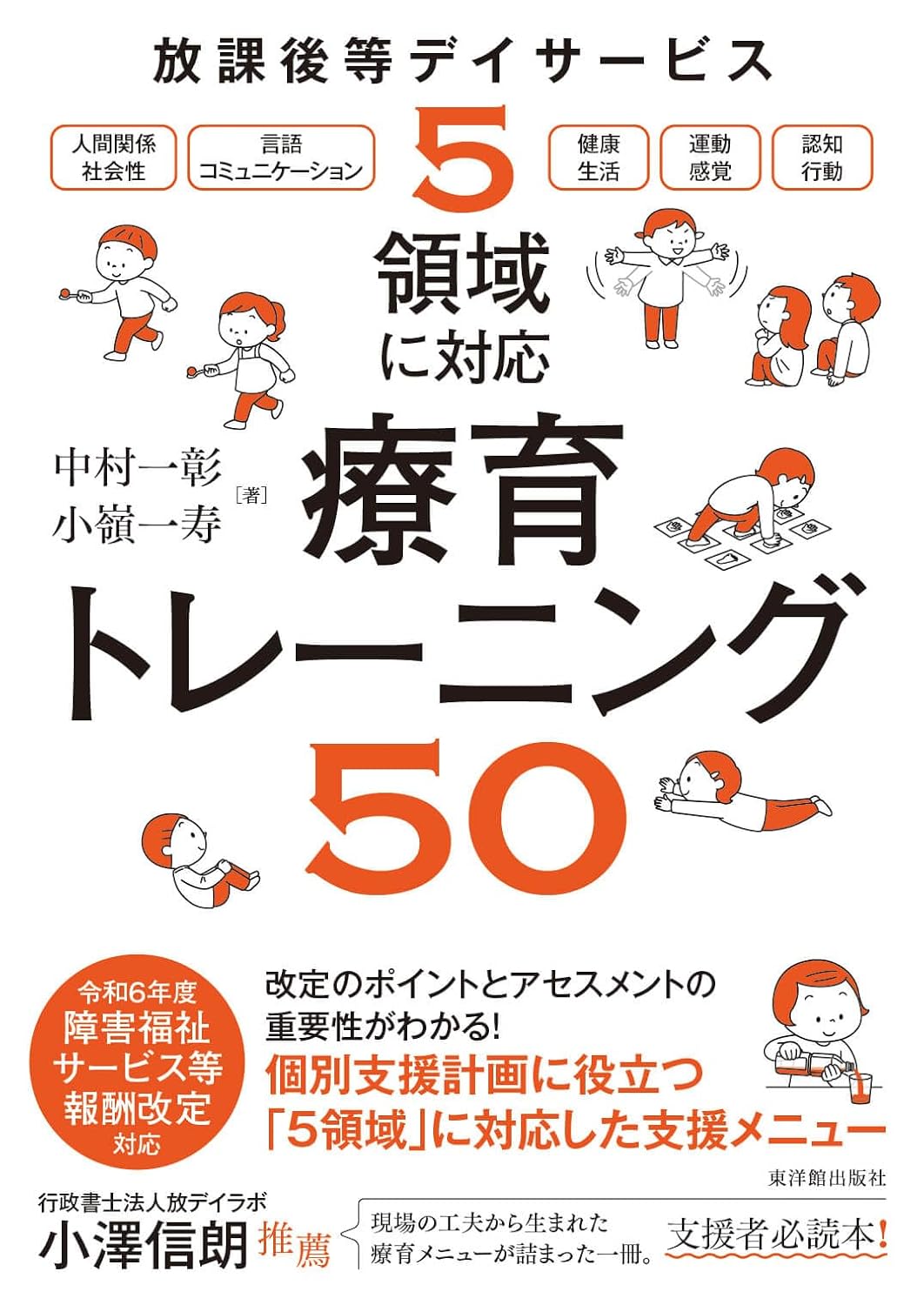
令和6年度に障害福祉サービス等報酬改定が行われました。
それに伴い、放課後等デイサービスにおける個別支援計画の記載内容も大幅に変更になりました。
中でも、〝5領域″に対応した個別支援計画作成が義務付けられています。
本書は、〝5領域″に対応した支援メニューが豊富に記載されています。
個別支援計画作成のさらなる充実、〝5領域”との関連性に対応した支援メニューを理解する上でとても参考になる内容になっています。
7.児童発達支援・放課後等デイサービスのための発達障害支援の基本
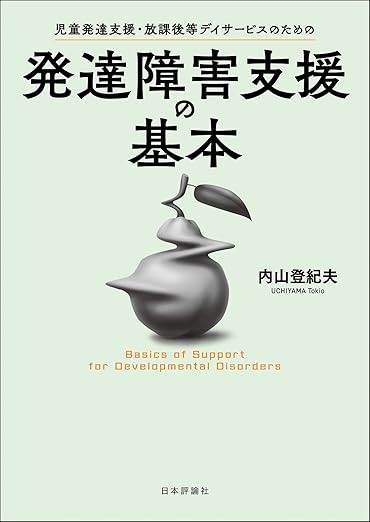
発達障害領域で大変有名な〝内山登紀夫さん“著の本になります。
主に、幼児・学童期の自閉症を中心とした発達障害支援の基本が集約されています。
発達障害の概要、自閉症の学習スタイル、感覚の問題、コミュニケーション支援、療育の原則、問題行動への対応、家族支援、思春期の課題、ストレスへの対応、医療との連携、障害児支援の仕組みと課題など、発達障害支援について広範囲な内容が最新の情報を踏まえて記載されています。
発達障害への具体的な支援の理解のヒントを学びたい人に大変お勧めです。
発達障害の概要を理解したい人にお勧めする記事は以下です。
関連記事:「発達障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
発達障害児の具体的な支援方法を知りたい人にお勧めする記事は以下です。
関連記事:「発達障害の支援に関するおすすめ本【初級~中級編】」
療育の概要や療育とは何かを考えたい人にお勧めする記事は以下です。
関連記事:「療育(発達支援)に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
療育で役立つ遊びを知りたい人にお勧めする記事は以下です。
関連記事:「療育(発達支援)に役立つ遊びに関するおすすめ本【初級~中級編】」