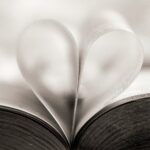愛着に問題を抱える人のケースが近年増加していると言われています。
その中で、愛着への支援方法なども増えています。
愛着障害への支援で大切な点は、〝心理的支援″です。
一方で、心理療法には、〝認知療法″といった認知(物事の見方・考え方)に働きかける方法もあります。
関連記事:「愛着アプローチとは何か【2つのアプローチから考える】」
関連記事:「愛着障害への支援:「愛情の器」モデルを例に」
それでは、カウンセリングなどで使用される認知療法といった方法は愛着に問題を抱えている人に効果はあるのでしょうか?
そこで、今回は、愛着障害への支援について、認知療法には効果はあるのか?といったテーマについてお伝えしていきます。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「岡田尊司(2016)愛着障害の克服:「愛着アプローチ」で、人は変われる.光文社新書.」です。
愛着障害への支援について【認知療法には効果はあるのか?】
以下、著書を引用しながら見ていきます。
愛着の安定化が十分でない段階で、認知を修正しようとすると、逆効果になることが多いということだ。(中略)むしろ、そうした修正を施さず、愛着の安定化だけにエネルギーを傾注した方が、認知もバランスの良いものに変化するということを、しばしば経験する。通常の認知療法なども、それがうまくいくのは、愛着が比較的安定した人である。
著書の内容から結論を先に言うと、認知療法で効果があるのは、愛着が安定している人(ある程度)だけであり、不安定な愛着(愛着障害など)の人には効果は期待できないということになります。
認知療法は、人の物の見方や考え方に働きかける方法です。
例えば、AさんがBさんの気になる言動で自分が否定されたと受け止めたとしましょう。さらに、Aさんは周囲の人は自分を否定的な目で見ると拡大解釈したとしましょう。
こうしたAさんに対して、認知療法では、例えば、Bさんは言動の意味は必ずしもAさんを否定したものではないことや、Bさんの物事の見方や考え方はAさんとは○○の点で違うなど、Aさんがもともと持っている人に対する見方を肯定的な方向へと修正していくことなどが例として考えられます。
こうした認知療法が効果を発揮する人は、もともと対人スタイルが安定した人に限ってであり、不安定な対人スタイルの人には効果は期待できないということになります。
それでは、何故、認知療法は、愛着が安定している人には効果があり、愛着障害など愛着が不安定な人には効果は期待できないのでしょうか?
著書の中では、その違いは「メタ認知」と「振り返る力」にあるとしています。
「メタ認知」とは、物事を第三者的により俯瞰的に客観的に考える力のことです。
そして、こうした「メタ認知」能力が高いと、自他の言動や行動の意図や意味を深く考える力、つまり、「振り返る力」に影響していきます。
安定した愛着の人は、自分の言動や行動を修正したり、他者の言動や行動の意図を推測し、対人距離をより安定した状態へと変化・修正することができます。
そして、物事の特定の部分に捉われ過ぎずに、様々な視点から物事を見ようとします。
一方で、不安定な愛着の人(愛着障害など)は、こうした力が弱いために、人の特定の言動に捉われ過ぎたり、何か嫌なことがあると過去のネガティブな体験と結びついてしまうなど、メタ的に物事を考えたり、振り返ることが難しいとされています。
そのため、認知に直接働きかけるだけでは、効果が弱い(あるいはない)と言えます。
関連記事:「安定型愛着スタイルの人の特徴【メタ認知と振り返る力から考える】」
以上、愛着障害への支援について【認知療法には効果はあるのか?】について見てきました。
私自身、愛着障害など愛着に問題を抱えている人とは、これまで関わってきた経験が多くあります。
こうした人との関わりで思うのは、○○のように考えたほうが良いなどの認知に働きかける方法はあまり効果がなかったように感じます。
それよりは、何を言ってもこの人は人格や生き方などを否定してこないといった安心感なのだと思います(出発点として)。
つまり、ボウルビィがいった「安全基地」を基盤とした心理的支援が大切なのだと思います。
もちろん、心理的支援による効果や改善には個人差があり、時間がかかるケースも多くあります。
しかし、現在の愛着障害への支援で効果があるのは心理的支援です。
近年、増加傾向のある愛着障害に対して、私自身も、療育の現場からできること、発信できることを探し、行動していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
岡田尊司(2016)愛着障害の克服:「愛着アプローチ」で、人は変われる.光文社新書.