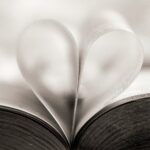愛着障害の子どもには、様々なタイプがあると言われています。
中でも、医学的診断名はないものの、ASD(自閉症スペクトラム障害)と愛着障害が併存しているタイプもあると考えられています。
関連記事:「【ASDを併せ持つ愛着障害のタイプについて】療育経験を通して考える」
著者もこれまでの療育経験の中で、ASD+愛着障害のタイプだと感じたケースは少なからず見てきたように思います。
そして、このタイプには、こだわり行動や感覚の問題、フラッシュバックなどを背景とした強い〝攻撃性″が見られる場合があります。
それでは、ASDと愛着障害併存タイプの子どもの攻撃性には、どのような対処法があると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、ASDと愛着障害併存タイプの子どもの攻撃性への対処法について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、〝逸らす″〝ずらす″支援から理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「米澤好史(2020)事例でわかる!愛着障害 現場で活かせる理論と支援を.ほんの森出版.」です。
【ASDと愛着障害併存タイプの子どもの攻撃性への対処法】〝逸らす″〝ずらす″支援を例に
以下、著書を引用しながら見ていきます。
攻撃行動と、密着しているネガティブな感情とを切り離すには、「引き剥がす」というやり方が最も抵抗されます。焦点化された認知とそれに密着した感情を「逸らす」「ずらす」支援が効果的です。
攻撃が激しく、どうしてもいったん収めないといけない場合は、前から抱きかかえるのではなく、「後ろから抱きしめる」方法を使います。
逸らすには、タイミングも重要です。
著書の内容から、ASDと愛着障害併存タイプの子どもの攻撃性への対処法として、ネガティブ感情を無理に引きはがすというやり方では逆効果となるため、必要なのはネガティブ感情に対して〝逸らす″〝ずらす″支援が効果的だと記載されています。
例えば、他者の言動に対して、急にイライラし始め、それが攻撃性へと転じた場合には、他者の言動に対する気持ちの受け止め方(何が嫌だったのか?○○と言われたことが嫌な気持ちの原因になったのか?などの気持ちの聞き取りや推測)などとはいったん距離を置き、他の情報を活用して視点を切り替えていく対応が必要だと言えます。
例えば、環境を一度変えてみる、その人が安心できるアイテムを提示する、好きな話題で気をそらす、他の人から他の活動に誘ってもらうなど様々なやり方があります。
また、著書には、攻撃性が高まっている場合には、前から抱きかかえるよりも〝後ろから抱きしめる″方法の方が良いと記載されています。
また、〝逸らす″〝ずらす″支援で活用した内容が、効果が無くても、別のタイミングで活用すると効果がでるなど、〝タイミング″も大切な視点だと記載されています。
著者の経験談
著者はASD+愛着に問題のある子どもたちと療育現場で関わる機会が多くありました。
こうした子どもたちは、何らかの刺激で急に不快感が高まり、攻撃行動が見られることがあります。
攻撃行動に対して、真正面から向き合うことには、ほとんど効果はなく(ASDの特性が強いと、特定の刺激に固執する傾向があるため、捉われていることへの認知を無理に書き換えることは難しい)、著書で見てきたように、〝別の刺激を入れる″ことで、一度、気持ちの安定化を図ることがとても重要だと実感しています。
〝別の刺激を入れる″ことは、〝逸らす″〝ずらす″支援のことであり、著者がよく活用する方法が、まずはクールダウンエリアへの誘導(静かで一人になれる環境に誘う)、そして、その子の好きなアイテムの活用(本やおもちゃ、動画や音楽など)、さらに、その子の好きな話題をふって、今捉われているネガティブ感情を逸らすことを心がけています。
また、前述しましたが、子どもに対応している大人以外の人が関わることで、気持ちが切り替わる場合もあると感じています。
対応している大人の場合だと、子どもはネガティブ感情を想起しやすく、その場にいなかった人が入り込むことで、〝別の刺激″となる場合があるからだと言えます。
以上の対応は、高い効果があると感じる一方で、その効果の出方は、ASD特性の強さ、そして、何よりも愛着障害の強さによって変化していくものだと思います。
例えば、愛着障害の程度が強いと、〝逸らす″〝ずらす″対応が難しかったり、また、落ち着くまでにも時間がかかる場合が多いと感じます。
大切なのは、子どもとの愛着形成を意識した関わりをしていくことが前提として重要となっていきます。
以上、【ASDと愛着障害併存タイプの子どもの攻撃性への対処法】〝逸らす″〝ずらす″支援を例にについて見てきました。
攻撃性への対処法は、まずは、気持ちを落ち着けることです。
そのためにも、今回見てきた〝逸らす″〝ずらす″支援はとても有効だと思います。
そして、気持ちが落ち着いた後の対応、さらには、常日頃からの愛着形成を意識した関わりも併せて必要だと言えます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も対応が難しい様々なケースに対して、支援の幅を広げていく視点を獲得していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
米澤好史(2020)事例でわかる!愛着障害 現場で活かせる理論と支援を.ほんの森出版.