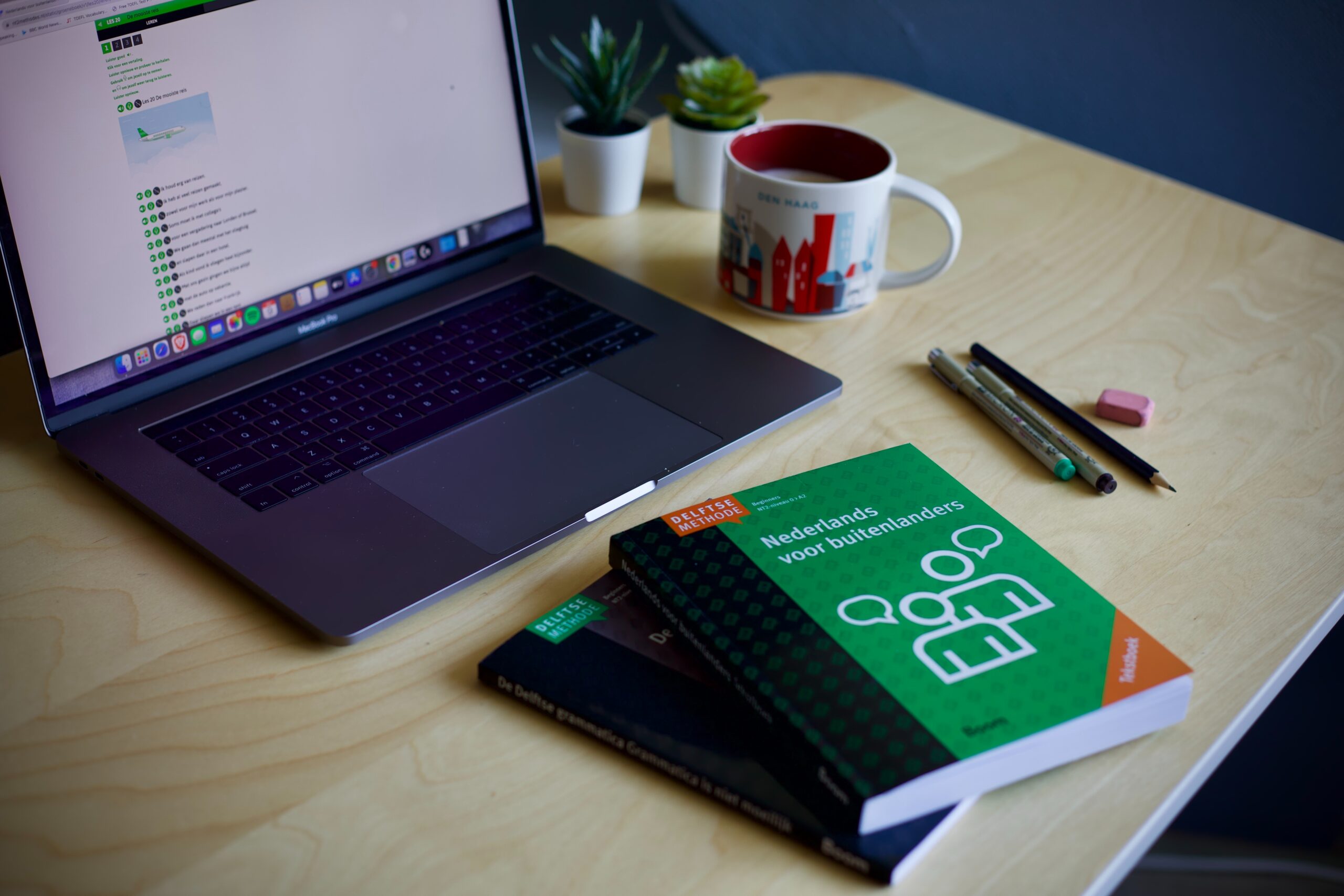
ADHD(注意欠如多動症)とは、不注意・多動性・衝動性を主な特徴としている発達障害です。
ADHDと言えば、忘れ物が多い、片付けができない、順番が待てない、他人が話しているときに急に話し出す、落ち着きがない、計画性がなく衝動的行動を取ってしまう、などが日常の困り感(周囲の困り感)として上がってくることが多くあります。
一方で、ADHD児には、言葉の発達にも困難さが見られることがあります。
それでは、ADHD児に見られる言葉の発達にはどのような特徴があるのでしょうか?
そこで、今回は、ADHDの言語発達の特徴について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「小椋たみ子・小山正・水野久美(2015)乳幼児期のことばの発達とその遅れ-保育・発達を学ぶ人のための基礎知識-.ミネルヴァ書房.」です。
ADHDの言語発達の特徴について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
ADHDの子どもの言語発達については、ことばの遅れとの関連で問題にされてきました。不器用さとも関連して、語音の発達が未熟であること(中略)、「発音が不明瞭」ということや、少しことばが遅れているということで相談に来られる保護者もみられます。
著書の内容から、ADHD児にも言語の遅れが見られるケースがあると記載されています。
そして、言葉の遅れの中には、不器用さとも関連して〝発音が不明瞭″といった特徴もあるようです。
ADHDには、不器用さが見られるという研究結果がこれまで多く出ていますが、発生器官も協調運動と言った運動機能が関連しているため、不器用さのあるADHDには〝発音の不明瞭″さが見られることが考えられます。
引き続き著書を引用しながら見ていきます。
コミュニケーションや微細運動の発達の遅れが、不全感などと関係し、行動面での特徴として現れているとも考えられます。
著書にあるように、言語発達や不器用さなどの遅れにより、不全感を招いてしまうこともADHD児への理解を深めていくためには重要となります。
ADHDの人は、不全感といった自己肯定感が低いこともまた特徴として多く見られます。
自己肯定感が低下する背景要因も、個々により異なりますが、不注意・多動性・衝動性といった行動特徴が、周囲から見るとマイナスと捉えられ、叱責される頻度が増えてしまうことが大きな要因として考えられます。
そして、言語発達の遅れも、自己肯定感の低下に繋がる大きな要因となるため、どのような面に遅れがあるのか、そして、遅れによりどのような困り感があるのかを理解していくことが大切となります。
著者の経験談
著者が関わる子どもたちや周囲の大人の中にもADHD児・者の人たちは多くいます。
こうした人たちには、不注意・多動性・衝動性の特徴が見られることも事実としてあります。
一方で、今回見てきた言語発達の遅れの特徴は特別目立った問題として上がってくることが少ないように感じています。
著者が関わってきた人たちの困り感の多くは、ADHDを代表する不注意・多動性・衝動性が影響して、社会の中で生きにくさが生じていること、そして、失敗経験による自己肯定感の低下などです。
そのため、潜在的には言語発達の遅れがあってもなかなか周囲には気づかれていない可能性もあります。
言語発達の遅れと関連する〝不器用さ″について見ても、他の発達障害にも併存している割合が高いことが知られていますが、表面上問題となって現れることは少ない印象があります。
そのため、著者なりに気を付けていることは、表面上問題となっている部分に目を向けながらも、表面下での問題にも目を向ける(問題となる可能性のある所)ように心がけています。
そのためには、現場の経験だけではなく、様々な文献や研究知見に触れるなど、知識の幅を広げていくことも大切だと考えています。
以上、【ADHDの言語発達の特徴について】発達障害児・者との関わりを通して考えるについて見てきました。
ADHDの人たちが持つ特性は、時と状況によっては強みに転じることも多くあります。
著者が関わる子どもたちの中にも、特性を強みに変えている、あるいは、今後強みにしていける可能性のある人たちが多くいると感じています。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も様々な発達への理解を深めていきながら、自分が関わる子どもたちにより良い療育をしていけるように日々の実践を大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【ADHDの言語発達への支援について】支援で大切な視点とは何か?」
ADHD・言葉に発達に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「ADHDに関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「言葉の発達の理解と支援に関するおすすめ本【初級~中級編】」
小椋たみ子・小山正・水野久美(2015)乳幼児期のことばの発達とその遅れ-保育・発達を学ぶ人のための基礎知識-.ミネルヴァ書房.









