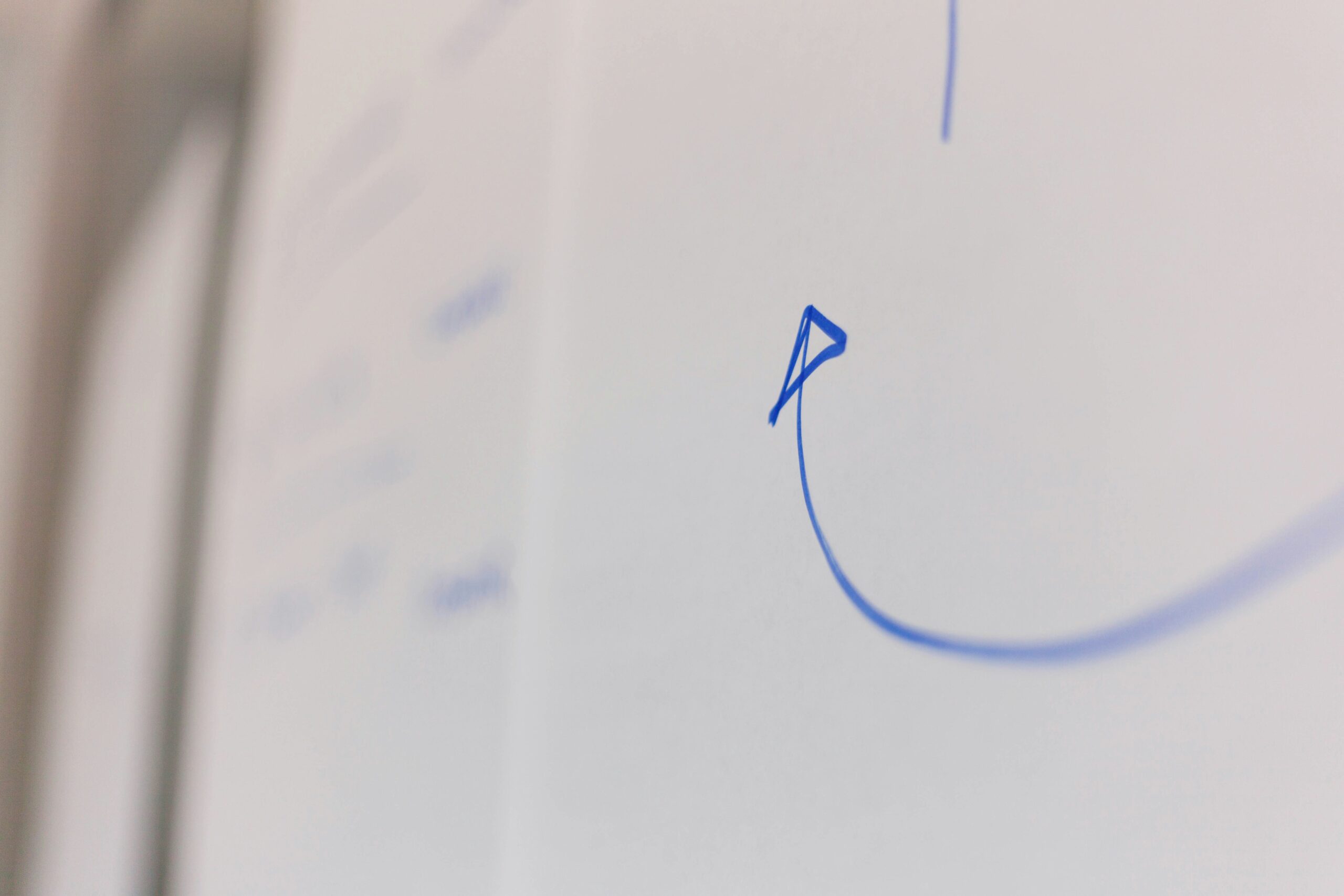
〝知的障害(ID)″とは、知的水準が全体的な発達よりも低く、かつ、社会適応上問題がある状態のことを言います。
一方で、〝境界知能″とは、〝知的機能が平均以下であり、かつ「知的障害」に該当しない状態″の人たちのことを指します。
IQ(知能指数)で言うと、70~84のゾーンに当たります(71~85と記載されている文献もあります)。
知的障害・境界知能の子どもの発達は全体的に〝ゆっくり″な特徴が見られます。
また、境界知能と軽度知的障害の状態像は似ていると言われています。
一般的には、知的障害・境界知能の子どもへの支援を考えた際に、課題のハードルを低く設定しながら、本人たちのゆっくりな発達を支えていくことが必要だと考えられています。
一方で、学習のやり方次第では能力の向上は可能だと言えるのでしょうか?
そこで、今回は、知的障害・境界知能の子どものIQは上がるのかについて、臨床発達心理士である著者の意見も交えながら、脳の可塑性をキーワードに理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「宮口幸治(2023)境界知能の子どもたち 「IQ70以上85未満」の生きづらさ.SB新書.」です。
【知的障害・境界知能の子どものIQは上がるのか?】脳の可塑性について考える
以下、著書を引用しながら見ていきます。
環境の変化を含めて慎重に検証する必要がありますが、IQは周りの大人との関わり方次第で変わる可能性も少なからずあるはずです。
それと脳には「可塑性」があります。脳は外界からの刺激などによって常に機能的な変化、構造的な変化を起こしているとされます。神経組織や回路が変化する性質があるのです。成長期の子どもの脳ならなおさら、常に変化してその能力を伸ばせる可能性があるのではないでしょうか。
著書の内容から、知的障害・境界知能の子どもにおいて、IQは上がる可能性があると記載されています。
もちろん、関わり手との関係性や学習のやり方など、IQに変化をもたらす要因には様々なものがあると想定できます。
そして、ここで重要なことは、〝脳の可塑性″です。
つまり、脳は変わり続けることができるといった性質があり、特に、成長期の子どもにとっては多くの変化の可能性があるのも事実だと言えます。
そして、現時点におけるIQ(知能指数)の変化に関する見解は、意見が分かれている(伸びる・伸びない)といった現状にあります。
注意点として、IQの数値を高めることを目的としないこと(あくまでも良い学習の結果として捉える)、また、IQの変化には、慎重な検証が必要なため、安易な結論付けには気を付ける必要があります。
著者のコメント
著者はこれまでの療育経験や様々な文献を読んだ結果、知能指数は大きく変化しないものだと考えていました。
もちろん、このように考えている専門家も少なからずいると思います。
一方で、IQの数値が向上した例もあると言えます。
実際に、著者の周りでも、IQの数字が変化した、例えば、10数年前の数値に比べて現在の数値が高まった例も見られています。
一方で、IQの測定は常に正確ではない場合もあると言われています。
例えば、検査を受ける時の状態(極度の緊張など)によっても、数値に変化が見られることがあります。
このように、IQの数値変動には様々な要因が影響している可能性があるのだと思います。
ここで大切なことは、〝脳の可塑性″です。
脳は変わる性質を持っていますが、なぜ変わるのか(変わったのか)を考えながらIQの数値変動を見る必要あると思います。
例えば、何かを学ぶためには、意欲のエネルギーが必要です。
意欲のエネルギーが無いと、自ら学ぼうとする意欲が湧かないため、進んで学習に取り組むことが難しくなります。
そして、次に、学びの目的と課題レベル、学習のやり方があります。
例えば、〝計算ができるようになりたい″といった目的を持っている子どもがいた場合、その子に合った課題設定や学習内容を工夫していくことで徐々に成果が見えてくると思います。
逆に、目的がはっきりしていない状態であっても、その子に合った課題レベルと、その子に合った学習のやり方を踏まえて計算練習をした結果、〝わかった″〝できた″といった感覚が得られる場合もあると思います(学習意欲の向上、目的が持てるようになるなど)。
大切なことは、日々の積み重ねによる成長の実感だと言えます。
そして、子ども自身が成長を実感できることで、自信が湧き、様々なことに意欲的に取り組もうとする姿勢が高まっていくのだと思います。
結果として、脳がプラスに変化して、IQの数値にもプラスな影響を及ぼす可能性もあると考えます。
以上、【知的障害・境界知能の子どものIQは上がるのか?】脳の可塑性について考えるについて見てきました。
繰り返しになりますが、IQの数値が高まったことは学習の結果であり、大切なことは、意欲的に学習に取り組み続ける姿勢や、学習によって得られる自信だと言えます。
最近は、IQといった認知能力以外の側面、つまり、非認知能力も重要だと考えられるようになってきています。
子どもたちが認知能力・非認知能力といった様々な能力を高めていきながら、、自己の世界を広げ、社会との様々な接点を持つ機会を増やしていくことが重要だと感じます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育現場で関わる子どもたちに、良い学びの機会を与えていけるような関わり方を試行錯誤していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「知能指数は変化するのか【発達障害を例に考える】」
知的障害・境界知能に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「知的障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「境界知能に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
宮口幸治(2023)境界知能の子どもたち 「IQ70以上85未満」の生きづらさ.SB新書.






