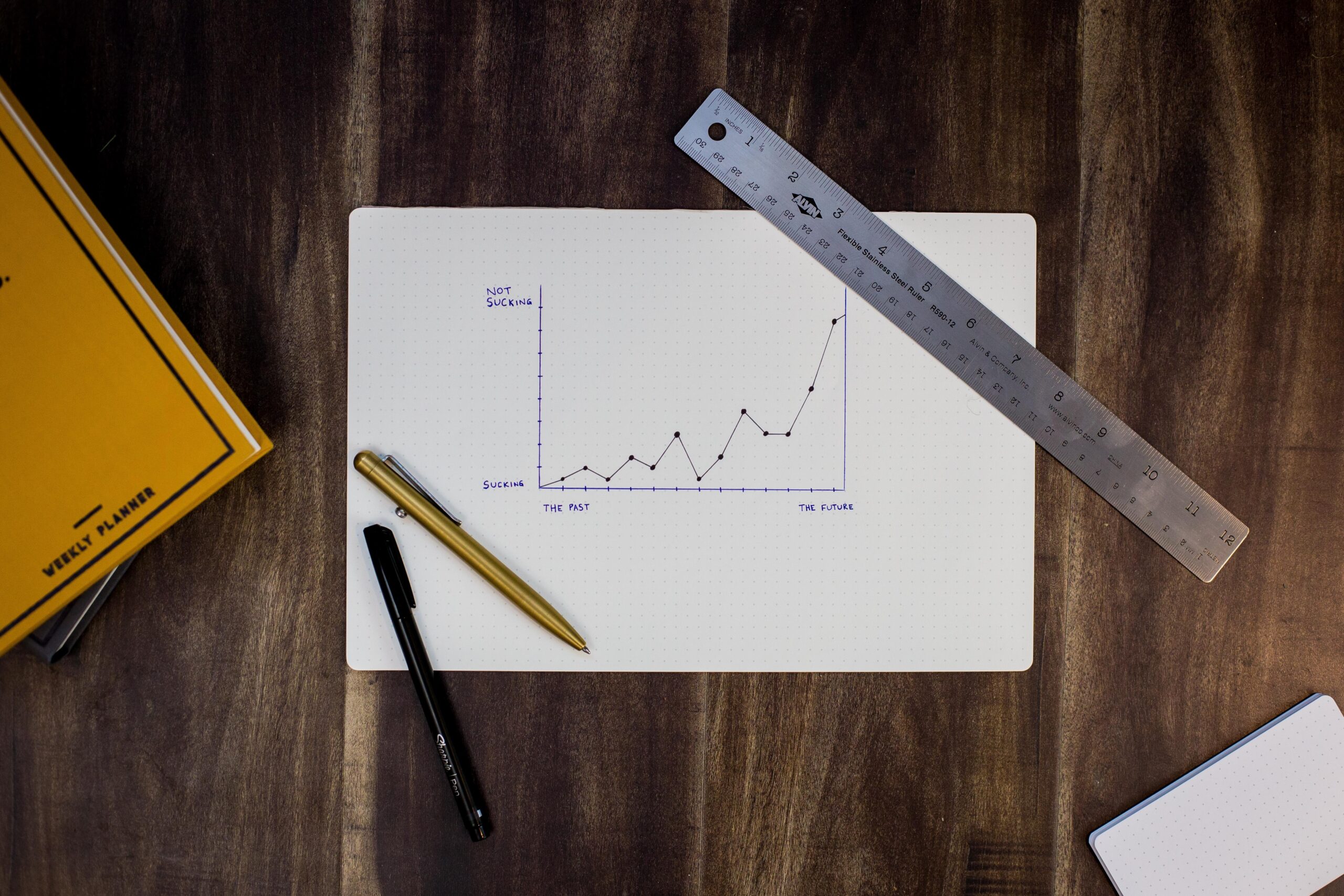
発達障害児支援をしていると子どもの〝問題行動″への対応に迫られることがよくあります。
〝問題行動″とは、他児への暴言やパニック・癇癪などその表出方法も様々あります。
多くの人たちは、〝問題行動″が起きたか・起きなかったのかという視点に議論がフォーカスされ、具体的な生起頻度には目を向けることは少ないように思います。
そういう著者も〝問題行動″の頻度などを具体的に把握することは少ないです。
一方で、〝問題行動″を具体的に測定する必要性を述べている方もいます。
〝問題行動″を具体的に測定することでその子の状態像を正確に把握することができる、そして、支援の手立てに繋げていくことができます。
それでは、〝問題行動″の測定の仕方にはどのような内容があるのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害児の〝問題行動″の測定の仕方について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「小嶋悠紀(2023)発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル.講談社.」です。
〝問題行動″の測定の仕方について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
問題行動のあと、再発を防ぎたい・行動の原因を取り除きたいと思ったら、一度は行動を「測定」して見なければなりません。
著書の中では、〝問題行動″を今後予防していくために、データを取っていく必要性があるとしています。
そして、以下の3点が「測定」には必要だと記載されています(以下、著書引用)。
①何回起こったか数を数える
②増減を把握する
③継続時間を測定する
著書には、〝問題行動″の「測定」内容として、
①何回起こったか数を数える
②増減を把握する
③継続時間を測定する
の3つを上げています。
②の増加を把握することは、例えば、〝問題行動″の生起頻度を一日単位、一週間単位、一か月単位、でまとめるなどの方法があります。
〝問題行動″の増減を把握することで、〝問題行動″といった現象面での理解の視点(例えば、○○の状況で問題行動が起こったなど)に加え、起こりやすい時間帯、時期、季節などの把握に繋げていくことができます。
著書の経験談
著者は以前、子どもの〝問題行動″を具体的な数値で測定し、数値の変動を追ったことがあります。
昔の著者は、感覚に頼ることが重要で、数値化する意味はそれほど必要ではないと感じていました。
しかし、実際に数値化することで、子どもの〝問題行動″の傾向が可視化されると長い期間でどのように変化しているのか、変化の要因は何であったのかを理解する大きな手立てになりました。
それ以降、行動をデータ化することもとても大切な視点であると考えるようになりました。
現在、療育現場で子どもたちの〝問題行動″を具体的なデータで測定することをしているわけではありませんが、〝生起頻度がどの程度(頻度、時期、長さ)あるのか″ということはできるだけ把握するようにしています。
こうした把握がより正確であればあるほど、子どもたちの実態に迫ることができると感じています。
つまり、〝問題行動″の傾向がつかめていくということです。
例えば、〝問題行動″は、○○時の時間帯によく起こる(強く生じる)、週末にかけてよく起こる(強く生じる)、夏場の暑い時期によく起こる(強く生じる)、学校行事が迫ってくるとよく起こる(強く生じる)などある種の傾向が見えてきます。
そのため今後も、著者は〝問題行動″の全てを数値化するまでとはいかなくても、できるだけ正確に測定していく必要性があると考えています。
以上、【発達障害児の〝問題行動″の測定の仕方について】療育経験を通して考えるについて見てきました。
人間の行動にはなんらかの理由があります。
〝問題行動″は周囲で関わる大人からするとできれば回避したい思いもあるかもしれませんが、その原因を把握し予防と対応に着手していかないと減らないことが多いと感じています。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育現場で問題行動への原因を把握していけるように、曖昧になっている行動を測定する視点も大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【発達障害児の〝問題行動″の理解の仕方について】療育経験を通して考える」
小嶋悠紀(2023)発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル.講談社.










