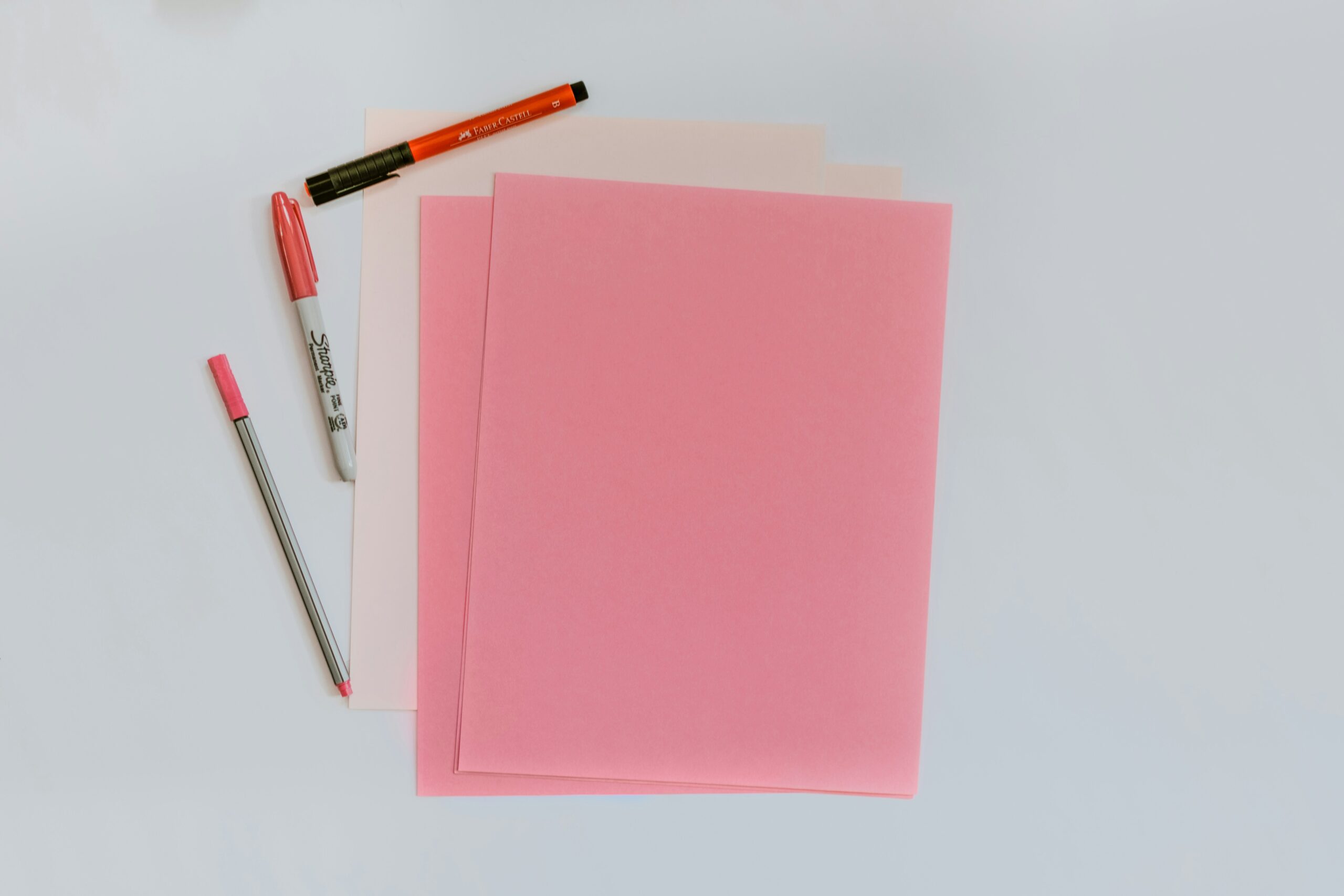
著者は長年、療育現場で発達障害など発達に躓きのある子どもたちへの療育をしてきています。
発達障害児の中には、背景要因は多様でありながらも、〝不安・緊張″が強い子どもがいます。
〝不安・緊張″が強いことで、活動への参加が制限されるなどデメリットが生じることがあります。
それでは、発達障害児に見られる不安・緊張が強いケースに対して、どのような対応方法があると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、発達障害児に見られる不安・緊張が強い場合への対応について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、3つのポイントを通して理解を深めていきたいと思います。
今回参照する資料は「岩永竜一郎(2022)発達症のある子どもの支援入門-行動や対人関係が気になる幼児の保育・教育・療育-.同成社.」です。
※幼児を対象として書かれた本ですが、学童期にも活用できる視点も含まれていると思います。
不安・緊張が強い場合への対応:3つのポイント
著書には〝不安・緊張が強い″場合への対応方法として、以下の3つのポイントが書かれています(以下、著書引用)。
保育者・療育者との安心できる関係を作る
園や療育施設での活動に見通しが持てるようにする
自信をつける機会を設ける
それでは、次に、以上の3つのポイントについて具体的に見ていきます。
1.保育者・療育者との安心できる関係を作る
以下、著書を引用しながら見ていきます。
保育者・療育者がマンツーマンで遊ぶ時間を作り、この先生と一緒にいたい、この先生といれば安心、という関係を作るようにすることが大切です。
著書にあるように、まずは関わり手との信頼関係の構築が大切になります(〝保育者・療育者との安心できる関係を作る″)。
そのため、その子にしっかりと向き合う時間の確保が必要になります。
著者も幼児期・学童期など様々なライフステージにおいて、不安・緊張が強い子どもと多く関わってきました。
彼らにとって、著者自身が安心・安全の基地になることがとても重要であり、信頼関係が徐々にできてくることで、子どもの表情や行動が非常にポジティブに変化していった(不安や緊張が和らいでいった)事例はこれまで多くあったように思います。
関連記事:「【発達障害児支援で大切な支援のスタンス】7対3の関係を通して考える」
2.園や療育施設での活動に見通しが持てるようにする
以下、著書を引用しながら見ていきます。
スケジュールを示したり、どこまですれば終了なのかを伝えたり、変更がある時には事前に伝えたりすることが必要になることがあります。
不安・緊張が強い子どもの特徴として、変化や新規なことに非常に過敏さ(苦手さ)があるといったものがあります。
特に自閉症児にはとてもよく見られます。
そのため、著書にあるように、まずはできるだけ前もって見通しを伝えていく対応が必要になります(〝園や療育施設での活動に見通しが持てるようにする″)。
著者は、幼児期・学童期の療育において、不安・緊張が強い子どもには、変化や新規なことにどの程度(強度や種類など)抵抗感や過敏さがあるのかをアセスメントすることを心掛けています。
保護者の情報等も参照しながらアセスメントしていくことで、少しずつ子どもにとって必要な見通しが分かってくることがあります。
関連記事:「【自閉症児への構造化で大切なこと】療育経験を通して考える」
3.自信をつける機会を設ける
以下、著書を引用しながら見ていきます。
対人的かかわりの中で安心感や自信が持てるような機会を作ると良いでしょう。
著者にあるように、自信をつけることも不安・緊張の軽減には大切です(〝自信をつける機会を設ける″)。
著者がこれまで見たきた子どもの中には、集団の中で自分が○○ならできる!得意である!といった自己肯定感が高まることで、以前見られていた不安・緊張の強さが軽減していったケースが少なからず見られることがあります。
特に、他者を意識するように、他者と比較して自分を見るようになると、できないことへの劣等感が増えていかないような関わり方・対応がとても大切だと言えます。
そのため、子どもの得意なこと、好きなこと、頑張って取り組んでいる過程、以前と比べてできるようになったことなどにフォーカスして対応することで少しずつ自信が積みあがっていくのだと思います。
関連記事:「療育で重要なこと-自尊心・自己肯定感の視点から考える-」
以上、【発達障害児に見られる不安・緊張が強い場合への対応】3つのポイントを通して考えるについて見てきました。
大切なことは、不安・緊張が強いことで、社会参加の経験が不足してしまうこと、そして、対人的な関わりの中で身に付く力が不足してしまうことを防いでいくことだと思います。
そのためにも、今回見てきた不安・緊張が強い場合への対応のポイントは、とても大切な視点だと言えます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も子どもたちが安心した環境の中で少しずつ自信を獲得していけるような取り組みを目指していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
岩永竜一郎(2022)発達症のある子どもの支援入門-行動や対人関係が気になる幼児の保育・教育・療育-.同成社.




