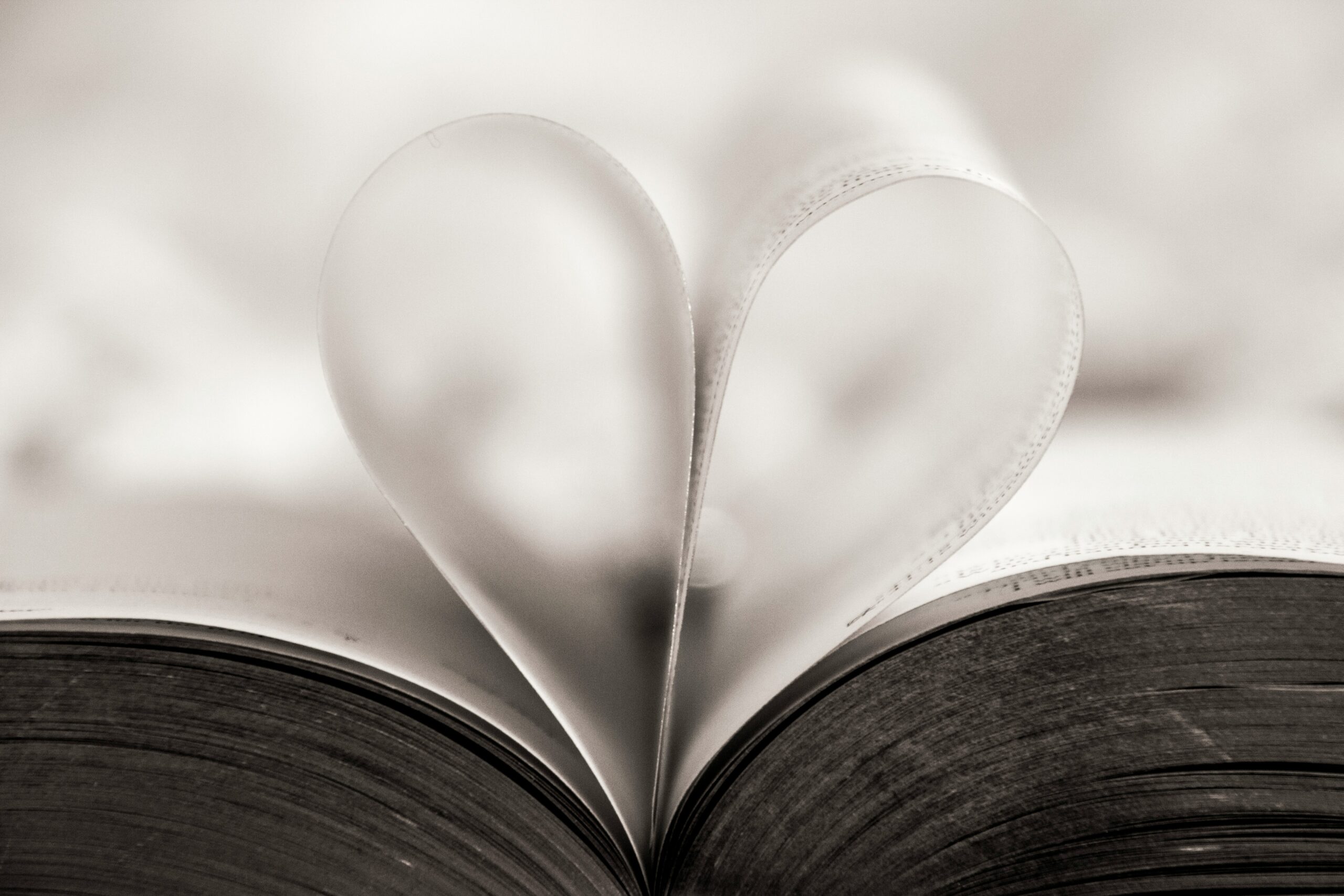
愛着障害の割合が増加していると言われている中で、どのような支援をしていけば良いかで思い悩んだことはありませんか?
著者のこれまでの療育経験を通して見ても、愛着障害あるいは愛着に問題を抱えている子どもは予想以上に多いと実感しています。
そうした中で、愛着障害には具体的にどのようなタイプがあり、何が根底的な背景要因であり、どのような支援を行っていけば良いかを考えることは非常に大切なことだと考えます。
かつての著者は愛着障害児との関わりにおいて、何を軸に理解・支援をしていけば良いか試行錯誤の連続でした。
今回は、現場経験+理論+書籍の視点から、愛着障害児への支援を進化させる視点についてお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
目次
1.愛着障害児への支援に迷走していた著者のエピソード
2.愛着障害を理解する理論・書籍
3.愛着障害児に関する支援の意味・効果が見えてきた著者の経験談
4.まとめ
1.愛着障害児への支援に迷走していた著者のエピソード
著者は長年、療育現場に携わってきていますが、過去に虐待ケースの多い児童相談所に勤務していた経験があったため、非常に早い段階から愛着障害児と接する経験が多くありました。
その後、療育施設、放課後等デイサービスで、発達障害児と関わる機会を持つことになりますが、こうした子どもたちの中には、発達障害以外の問題、つまり、愛着に問題を持っているのではないか?と感じられるケースが想像以上に多いと感じる機会を持つことになりました。
例えば、人への警戒心が非常に強い子ども、暴言・他害の多い子ども、誰彼構わずにスキンシップを求める子ども、他者との関わりをシャットダウンして自分の殻にこもることが多い子どもなどです。
こうした子どもたちに、発達障害を軸としたアプローチを取っても望ましい発達が見られないことが多く、そのこともあり、愛着からのアプローチの必要性をより強く感じるようになっていきました。
一方で、愛着からのアプローチといっても、まずは何を軸に支援をしていけば良いか手探りの状態でした。
こうした中で、支援の突破口を開くきっかけになったのが〝愛情の器モデル″といった愛着修復プログラムです。
ここから先は、〝愛情の器モデル″を踏まえて、著者が支援上非常に役に立った視点を見ていきます。
2.愛着障害を理解する理論・書籍
愛着障害への理解を深めていく上で、著者が非常に参考になった書籍を以下に紹介していきます。
以下の書籍は全て〝愛情の器モデル″に関連するものです。
書籍①「米澤好史(2015)発達障害・愛着障害:現場で正しくこどもを理解し、こどもに合った支援をする:「愛情の器」モデルに基づく愛着修復プログラム.福村出版.」
書籍②「米澤好史(2020)事例でわかる!愛着障害 現場で活かせる理論と支援を.ほんの森出版.」
書籍③「米澤好史(編著)(2019)愛着関係の発達の理論と支援.金子書房.」
書籍④「米澤好史(2024)発達障害?グレーゾーン?こどもへの接し方に悩んだら読む本.フォレスト出版.」
書籍⑤「米澤好史(2018)やさしくわかる!愛着障害 理解を深め、支援の基本を押さえる.ほんの森出版.」
以上の書籍を踏まえて、著者が支援上非常に参考になったキーポイントとして、1.愛着障害の支援に手遅れはない、2.愛着障害の3つのタイプ、3.叱る対応の問題点、4.愛着で大切な3つの基地機能、5.愛着障害の支援の目標です。
〝愛情の器モデル″は非常に奥が深く役立つ視点が豊富にあるため、上記の5つのポイント以外にも大切な視点が多くあります。
ここでは、その中でも、著者が療育現場で大変参考になったもの、そして、愛着に問題を抱えている人の支援をしている人に大変役立つものを取り上げていきます。
1.愛着障害の支援に手遅れはない
それでは、書籍①を引用しながら見ていきます。
愛着は「いつでも誰でも心理的支援で取り戻せる」のである。さらに、付言しておけば、愛着障害の症状である興奮状態を緩和するための医療支援、投薬治療は可能であるが、医療により愛着障害を治療することは不可能である。愛着障害が関係性の障害である以上、心理的支援以外の方法で治療できるはずがないのである。
著書の内容から、愛着の問題は〝いつでも、誰でも、支援的支援によって修復可能″だと言えます。
愛着形成は、誕生後~1・2歳の期間が重要だとされていますが、それを過ぎても可能です。
つまり、〝いつでも″修復が可能ですが、できるだけ早期の方が良いと考えられています。
愛着とは、特定の他者との情緒的な絆であるため、まずは、〝特定の他者(愛着対象)″との関係構築が非常に重要になっていきます。
この場合、〝誰でも″愛着対象になることは可能だと言えます。
つまり、親でなくても、施設の職員、学校の先生、時には子ども(条件付き)でも可能だと考えられています。
ここでの注意点は、必ず〝一対一″の関係からスタートすることを意識することです。
最後に、医療的支援での根本的な修復は不可能であり、〝心理的支援″といった関係性の修復が必須だと考えられています。
著者は、以上の〝いつでも″〝誰でも″〝心理的支援によって修復可能″といった3つのキーポイントは、愛着障害児への支援の根底を支える重要な観点だと学ぶことができました。つまり、愛着障害への支援に手遅れはないということです。
2.愛着障害の3つのタイプ
それでは、書籍②を参考に3つの愛着障害のタイプについて見ていきます。
①「脱抑制タイプ」(脱抑制対人交流障害)
誰に対しても無警戒で、フレンドリーで馴れ馴れしく、過剰な身体接触を特徴とします。不適切な行動をした場合は、それを叱ると、叱られてもかまってもらえたと思い、その不適切な行動がさらに増えます。
②「抑制タイプ」(反応性愛着障害)
人間不信で、誰に対しても警戒し、かかわろうとせず、人が近寄ってくると避けようとします。不適切な行動をした場合、それを叱ると、以後、人間関係が長期にわたって一度遮断されることがあります。
③「ASDと愛着障害併存タイプ」
このタイプは実際の診断にはありませんし、現在の精神医学界の診断基準では、ASDと愛着障害の併存診断は認められていません。
①「脱抑制タイプ」(脱抑制対人交流障害)と②「抑制タイプ」(反応性愛着障害)に関しては、医学的診断にあるものです。
③「ASDと愛着障害併存タイプ」に関しては、実際の医学的診断にはないものですが、愛着の器モデルを考案した米澤好史さんによれば、確実にこのタイプが存在すると述べています。
著者の療育経験を見ても、①~③全てのタイプは存在していると実感しています。
また、愛着の問題も〝スペクトラム″だと米澤好史さんは考えているため(自閉症など他の発達障害同様に)、愛着の問題が顕著に出ている人から軽微に見られるタイプまで連続していると言えます。
愛着障害の3タイプに加えて、その強弱をおさえていくことは、愛着の問題を深く理解していく手掛かりになると思います。
3.叱る対応の問題点
愛着に問題を抱えている子どもは、大人が望まない行動をとることが多くあります。
そのため、大人からの〝叱責″を受けやすいと言えます。
一方で、〝叱る対応には問題がある″と愛情の器モデルでは考えられています。
この点について、書籍③を引用しながら見ていきます。
「叱る」はたいていの場合、こどもが不適切で叱る必要を感じる行動を先にした後で叱るというように、「後手」のかかわりだからである。先にこどもがある行動をしてある感情を感じている事態で、後からの対応でその感情を変えるのはそもそも困難である。
「叱る」に自動的に他者の行動を変容させる機能はない
著書にあるように、〝叱る″対応がまずい点として、〝後手の対応″になっていること、それに加えて、〝叱る″対応には子どもの行動を根本的に変容させることができないからだと考えられています。
〝叱る″対応で行動の変容が可能な子どもは、そもそも自身の行動を変える修正能力があることを前提としていること、自他の感情理解が発達しており、状況理解が可能である場合です。
愛着障害の問題は、〝感情の問題″とも考えられており、他者との関わりにおいて、安定した情緒の基盤がないことで、不安・不快な気持ちが高じるとネガティブ行動に転ずることが多くあります。
ネガティブ行動に対して、〝る″対応は後手の対応であり効果はありませんが、大切なことは、〝叱る″対応を取らなくても良い状況を作る〝先手の対応″だと考えられています。
〝感情の問題″とは、感情が未発達であるため、厳しく叱って反省を促しても、自分の気持ちがよくわからないため(相手の気持ちもわからない)振り返りができないため行動改善の効果は薄いと考えられています。
そのため、問題行動が生じる前に〝こうしうよう″といった〝先手の対応″が鍵を握っていきます。
著者は、愛着に問題を抱えている子どもがトラブルになる前にいかにはやくその子の不安定な感情に気付き、別の提案や安定した環境を整えていくことが〝叱る″ことを回避し、子どもが安心・安定して過ごす上でとても大切なことだと感じています。
少なくとも、これまでの著者の経験上、〝る″対応を続けて愛着に問題が改善したケースは見たことがないと感じています。
仮に、厳しく〝叱る″人の言うことなら話をきく状態において、他の人の前ではネガティブ行動を依然として変わらず見られる場合には、支援はうまく進んでいないと考えられています。
4.愛着で大切な3つの基地機能
それでは、愛着障害児との関係構築上、どのような視点が必要になって行くのでしょうか?
ここでのキーポイントが〝3つの基地機能″です。
〝3つの基地機能″とは・・・
安心基地(ポジティブな感情の生起・心地良さを感じる基地)
安全基地(ネガティブ感情の回避・危機・不安を守ってくれる基地)
探索基地(確認・報告を取りながらいつでも安心・安全基地に戻ってこれる基地)
です。
以上の3つの基地を意識した関わりが非常に重要になります。
それでは、この点を深掘りしていくために、書籍④を引用しながら見ていきます。
この3つの基地機能こそが、愛着という「特定の人と情緒的に結ばれるこころの絆」の正体なのです。
実際には、①安心基地→②安全基地→③探索基地という順番でつくられていくことになります。
どの子にも共通した〝こうすればいい″というかかわり方があるのではなく、その子の特徴に合ったかかわりを見つけることが大切なのです。
その子に合ったかかわりとは、愛着という絆を結んでいける<安心基地><安全基地><探索基地>の働きを意識しながら、こどもにとって〝その基地機能を意識できるかかわり″と言えます。
愛着の修復とは、まさに、〝3つの基地機能″の形成だと言えます。
そして、〝3つの基地機能″には、①安心基地→②安全基地→③探索基地という順番があることも関係構築上重要な視点です。
子どもにとって、愛着対象は、いかにして3つの基地を意識して関わることができるようになっていくかが必要だと言えます。
基地機能は、あくまでも〝子どもが(子ども側から見て)安心・安全だと感じる″状態が必要だということです。
さらに、3つの基地機能の形成には、順番があるとしても、具体的に〝こうすればうまくいく″といったものはなく、子どもの性格や特徴に応じてより良い関わり方を見つけていく必要性があります。
さらに、〝3つの基地機能“は、〝一対一″での関係性が大切となるため、それを可能とする〝キーパーソン″の選定が必要だと考えられています。
著者は、これまでの経験上、〝安心基地″となる存在を意識して関わることで、子どもとの関係性が良い方向に進み始めたと感じるケースが多くあったと感じています。
例えば、どのような関わりを好むのか?どのような関わりに安心感を抱きやすいのか?どのような遊びをすると楽しいと感じるのか?など、安心基地を意識して関わるスタートを取ることで、その後の、安全基地→探索基地へとうまく発展していくことができたと感じています。
5.愛着障害の支援の目標
最後に、愛着障害の支援の目標についても見ていきます。
以下、書籍⑤を引用しながら見ていきます。
キーパーソンは、自分のやっていることは、不適切なことをやめさせようとしているのではなく、適切でプラスの感情を引き起こす行動を一緒にたくさんすることで、結果的に不適切な、してほしくない行動の生起確率を下げているのだという認識が必要です。
適切でプラスの感情を引き起こす行動が「過半数」を超えた瞬間、劇的に不適切行動が減るのです。ですから、「こころの過半数を目指す」と思って、それを目標にするのがいいでしょう。
ここで大切なことは、特定の他者(〝キーパーソン″)とポジティブな感情を豊富に共有していくことで、その結果として、ネガティブ行動の発生率を下げていくという長期的な視点を持つことです。
そして、著書にあるように、プラスの感情が一定数を超えると劇的にネガティブ行動が減少することから、愛着障害の支援の目標として〝こころの過半数を目指す″ことが良いと考えられています。
この段階になると、3つの基地機能で言う〝探索基地″としてキーパーソンと関わりを持つ様子が増えていくと言えます。
つまり、愛着障害児支援の目標とは、〝こころの過半数を目指す″こと、〝探索基地として関係構築を目指す″ことが必要だと言えます。
3.愛着障害児に関する支援の意味・効果が見えてきた著者の経験談
これまで見てきた〝愛情の器モデル″に関する知識を療育現場に取り入れていく中で、次のような支援の意味・効果が見えてきました。
まずは、子どもの状態像の理解がよりクリアになってきたことです。
これまで、なぜ○○のようなネガティブ行動を取るのか?わからずにいましが、少しずつ行動の意味・背景が理解できるようになることで、これまで発達障害への特性を重視した理解に加えて、感情発達への理解・関係性への理解といった幅が広がっていきました。
そのことで、これまで理解が欠けていた愛着の問題を踏まえた子どもの状態像の理解が少しずつ可能になっていったように思います。
次に、愛着障害児支援の道筋が見えてきたことです。
これまで、愛着に問題を抱えている子どもに対しては、仮に発達障害があったとしても、発達障害を重視した理解・対応だけでは支援の効果が薄いと感じていました。
今回見てきた5つのキーポイントを重視した関わりを持つことで、長期的に見て支援の意味・効果を感じる機会が格段に増えていったようい思います。
実際に、著者と子どもとの関係性が進んでいく前提として、プラスの感情共有経験の多さが影響して、著者の声掛けがよりスムーズに入りやすくなったこと、そして、何かをする際に、著者に確認して行動したり、行動後、著者に報告する様子が増えていったように思います。
また、困った際に、著者の近くに来たり、相談しにくる様子も増えていったように思います。
こうした変化は、子どもの中に、愛着対象が少しずつ構築されていったからだと思います。
このように、〝愛情の器モデル″を踏まえた愛着障害児支援を行うことで、具体的に何を大切にして支援を進めて行けば良いか?何を目指して支援をしていけば良いか?多くの示唆を得ることができたと感じています。
4.まとめ
愛着とは、〝特定の他者との情緒的な絆″なことです。
愛着障害児支援は〝いつでも、誰でも、心理的支援によって修復可能″です。
愛着障害には、脱抑制タイプ・抑制タイプ・ASDと愛着障害併存タイプの3つのタイプがあると考えられています。
愛着障害児支援において、〝る″対応は後手の対応のため効果がなく、〝こうしうよう″といった〝先手″の対応が必要です。
愛着形成において、3つの基地機能:①安心基地→②安全基地→③探索基地といった順番を意識した〝一対一(キーパーソン)″を基盤とした関わりが大切です。
そして、愛着障害児支援の目標とは、ポジティブな感情共有経験を基盤(感情の発達を促すこと)として〝こころの過半数を目指す″こと、〝探索基地として関係構築を目指す″ことが必要だと言えます。
書籍紹介
今回取り上げた書籍の紹介
- 米澤好史(2015)発達障害・愛着障害:現場で正しくこどもを理解し、こどもに合った支援をする:「愛情の器」モデルに基づく愛着修復プログラム.福村出版.
- 米澤好史(2020)事例でわかる!愛着障害 現場で活かせる理論と支援を.ほんの森出版.
- 米澤好史(編著)(2019)愛着関係の発達の理論と支援.金子書房.
- 米澤好史(2024)発達障害?グレーゾーン?こどもへの接し方に悩んだら読む本.フォレスト出版.
- 米澤好史(2018)やさしくわかる!愛着障害 理解を深め、支援の基本を押さえる.ほんの森出版.
愛着障害に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
愛着に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」









