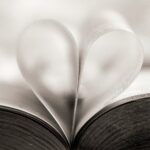愛着障害への支援で有名なものとして〝愛情の器モデル″があります。
関連記事:「愛着障害への支援:「愛情の器」モデルを例に」
〝愛情の器モデル″によれば、愛着障害への修復において、〝キーパーソン″の存在が必要不可欠だと考えられています。
キーパーソンとは、〝子どものことを一番よく知っている人″のことを言います。
一方で、特定のキーパーソンを求める子どもが複数存在することで、キーパーソンを取り合う状況に陥ることがあります。
それでは、2人の子どもが特定のキーパーソンを取り合う状況において、どのように対応していけばよいのでしょうか?
そこで、今回は、愛着障害の子どもの支援で必要なキーパーソンの取り合いへの対応について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「米澤好史(2019)愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解し、どう支援するか?アセスメントと具体的支援のポイント51.福村出版.」です。
愛着障害の子どもの支援で必要なキーパーソンの取り合いへの対応
以下、著書を引用しながら見ていきます。
一人の子には、キーパーソンが他の先生にあることを一緒にするよう目の前で依頼します。キーパーソンが主導して、その権限の一部を委譲委任する支援が効果的です。後で必ずキーパーソンから褒められ、認められる時間を作ります。これを交代して実施すればいいのです。
著書の内容から、キーパーソンの取り合いへの対応としてカギとなるのが〝キーパーソン″が〝サブキーパーソン″と子どもとを繋ぐといった支援方法です。
例えば、2人の子どもたちが特定のキーパーソンを取り合っている場合、そのうちの一人の子どもの活動を〝サブキーパーソン″に行ってもらうように依頼すること、そして、活動後に必ずサブキーパーソンと一緒に報告に来てもらい、キーパーソンが承認・褒めるといった対応を取るといったものです。
そして、次に同じ方法をもう一方の子どもに取っていきます。
このように、〝キーパーソン″が軸となって〝サブキーパーソン″に指示・依頼を出すこと、〝サブキーパーソン″がそれを受けて対応すること、対応後に〝キーパーソン″に報告するといったサイクルを回していくことが大切だと言えます。
間違っても対応してはいけない方法として、〝キーパーソン″を作らない対応、一人の子どもを強制的に引きはがすといったものだと記載されています。
引きはがされた子どもは、余計にもう一方の子どもに敵対心をもってしまいます。
著者の経験談:愛着障害の子ども以外にとっても大切な視点
これまで見てきた対応は、愛着障害の子ども以外にとっても大切な視点だと感じます。
それは、著者が療育現場で関わる子どもたちの中にも、愛着の問題の有無や程度の差はあれ、特定の支援者をめぐって2人以上の子どもが争うことがよくあるからです。
片方の子どもが○○さんと一緒に工作をして遊びたいと言っている一方で、もう片方の子どもが○○さんと体を使った遊びがしたいなど、〝○○さんと○○がしたい!″が交差する状況です。
著者はこうした状況において、他のスタッフ(子どもからの好感度が高い人)へと繋ぐことが最も効果的だと感じています。
そして次のステップとして、著者が見ていない活動内容についてもしっかりと活動後に他のスタッフから情報を得ること、そして、次にその子どもと関わる時間をしっかりと作っていくことです。
子どもは比較的短い時間でも(症状の程度により異なると思いますが)著者がしっかりと向き合ってくれたということを肌で感じていくものだと思います。
大切なことは、〝この人は自分のことをわかってくれている″という感覚を子どもが得られることだと思います。
そのためにも、他のスタッフとの連携作りがとても重要になってきます。
他のスタッフに任せてばかりいたり、キーとなる人物がいない支援は特に愛着障害など関係性に問題のある子どもの支援において効果が軽減されるように思います。
そして、子どもとの関係作りは、短期的には効果が得られないこともありますが、長期的に見るとポジティブな影響が出てくることが非常に多くあると感じてます。
以上、【愛着障害の子どもの支援で必要なキーパーソンの取り合いへの対応】療育経験を通して考えるについて見てきました。
今回大きくは触れていませんが、キーパーソンを作ると同時にいかにしてサブキーパーソンとなれる存在をつくっていくかもまた大きな課題だと言えます。
その理由は、著者は様々な福祉・教育の現場を見てきましたが、その中でも、キーパーソンへの比重がとても大きくなっているケースが多いと感じるからです。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育現場に愛着の視点を還元していけるように、愛着障害への理解と対応について学びを深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【愛着障害のある子どもへの支援で大切なキーパーソンとは?】キーパーソンの決定の仕方について」
関連記事:「愛着障害のある子どもに必要なキーパーソンを中心とした支援体制作りについて解説する」
愛着・愛着障害に関するお勧め関連書籍の紹介
関連記事:「愛着障害に関するおすすめ本【初級~中級編】」
関連記事:「愛着(アタッチメント)に関するおすすめ本【初級~中級編】」
米澤好史(2019)愛着障害・愛着の問題を抱えるこどもをどう理解し、どう支援するか?アセスメントと具体的支援のポイント51.福村出版.