〝境界知能″とは、〝知的機能が平均以下であり、かつ「知的障害」に該当しない状態″の人たちのことを指します。
IQ(知能指数)で言うと、70~84のゾーンに当たります(71~85と記載されている文献もあります)。
〝境界知能″の人たちには、様々な特徴が見られると言われています。
それでは、境界知能の人たちに見られる特徴・特性には、どのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、境界知能の特徴について、7つの特徴を通して理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「梅永雄二(2024)教師、支援者、親のための境界知能の人の特性と支援がわかる本.中央法規.」です。
境界知能の7つの特徴について
著書には、〝境界知能″の状態は、〝軽度知的障害″に近いと想定することで、状態像が理解しやすくなると記載されています。
以下、著書を引用しながら〝境界知能の7つの特徴″について見ていきます。
先の見通しを立てられない
理解力・記憶力が弱い
勉強が全般的に苦手
生活面の困り事がある
感情のコントロールが難しい
援助要求がうまくできない
幼少期は無自覚で、思春期以降は隠そうとする
それでは、次に7つの特徴について具体的に見ていきます。
先の見通しを立てられない
いわゆる〝実行機能の弱さ″の問題です。
〝実行機能″とは、〝遂行能力″や〝やり遂げる力″とも言われています。
この力が弱いと、物事を計画的に進めていく困難さが生じます。
また、状況に応じて、臨機応変に対応することも難しいと言えます。
支援のポイントとしては、まずは他者の力を借りること、視覚情報などを活用したスケジュール管理などがあります。
理解力・記憶力が弱い
いわゆる〝ワーキングメモリの弱さ″の問題です。
〝ワーキングメモリ″とは、情報を記憶し、処理する能力のことを指し〝脳のメモ帳″とも言われています。
この力が弱いと、人が話している様々な言語情報や視覚情報などを、一時的に記憶して処理することが難しくなります。
支援のポイントとしては、苦手な情報を得意な情報で補ったり(言語情報が苦手な場合、視覚情報で補う)、情報量を少なく簡潔に提示するなどがあります。
勉強が全般的に苦手
国語・算数・理科・社会といった勉強に躓きが見られることが多くあります。
小学校2~3年生頃からついていけないことが増えていきます。
実技系(体育・音楽・図工)に関しては、個人差があるようです。
支援のポイントとしては、本人に合った学習方法を工夫していくこと(電子機器の活用による苦手な所を補完する取り組みなど)、本人のペースで学習を進めていくなどがあります。
生活面の困り事がある
生活の困り事の例として多いのが〝時間管理″〝金銭管理″〝身だしなみ″の問題です。
例えば、遅刻や忘れ物が多い、必要以上に物を買ってしまう、シャツが出ているなど服装がだらしないことが上げられます。
支援のポイントとしては、他者に少しのサポートをもらうことで改善できることが多いと考えられています。
感情のコントロールが難しい
感情のコントロールの難しさには、〝衝動性″の問題や〝自己肯定感の低下″による二次的な問題があると想定されています。
そのため、本来的に境界知能の人が感情のコントロールに問題があると断定することは難しいと言えます(二次的な影響もあるため)。
支援のポイントとしては、自己肯定感を低下させないように、本人が安心できる環境調整や自己肯定感を維持できるような働きかけをするなどがあります。
援助要求がうまくできない
著書には、援助要求ができない背景の一つとして、〝いつ・誰に相談すればよいかわからない″といった問題があるとされています。
もう一つの背景として、これまで人を頼ってもうまくいかなかったといった経験から〝人を頼ってはいけない″と考えてしまっている問題があるとされています。
支援のポイントとしては、相談先の情報を伝達することや援助要求スキルの獲得などがあります。
幼少期は無自覚で、思春期以降は隠そうとする
幼少期は自己理解も進んでいないため、自他ともに見ても〝特徴が目立たない″ことが多いと言えます。
それが、小学校以降に年齢が上がっていくにつれて、少しずつ周囲との間に〝違和感″が出てくることがあります。
そして、思春期以降になると、〝できない自分を隠そう″といった気持ちが強くなることがあります。
支援のポイントとしては、相談できる相手を早めに持つこと、目標設定のハードルを下げること、他者を頼りながら困り感を解消していくなどがあります。
以上、【境界知能の特徴について】7つの特徴を通して考えるについて見てきました。
境界知能の人たちは、勉強面、生活面、就労面など様々な場面で困り感が生じる可能性があります。
困り感の背景となる特徴が今回見てきた7つの特徴だと言えます。
人によって、苦手なこと、困り感は異なるため、個々に合った対応方法を工夫していくことが必要だと言えます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も境界知能の人の理解を深めていきながら、実際の支援の方法も併せて学んでいきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【境界知能の定義について】起こりやすい問題の例も踏まえて考える」
境界知能に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「境界知能に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
梅永雄二(2024)教師、支援者、親のための境界知能の人の特性と支援がわかる本.中央法規.

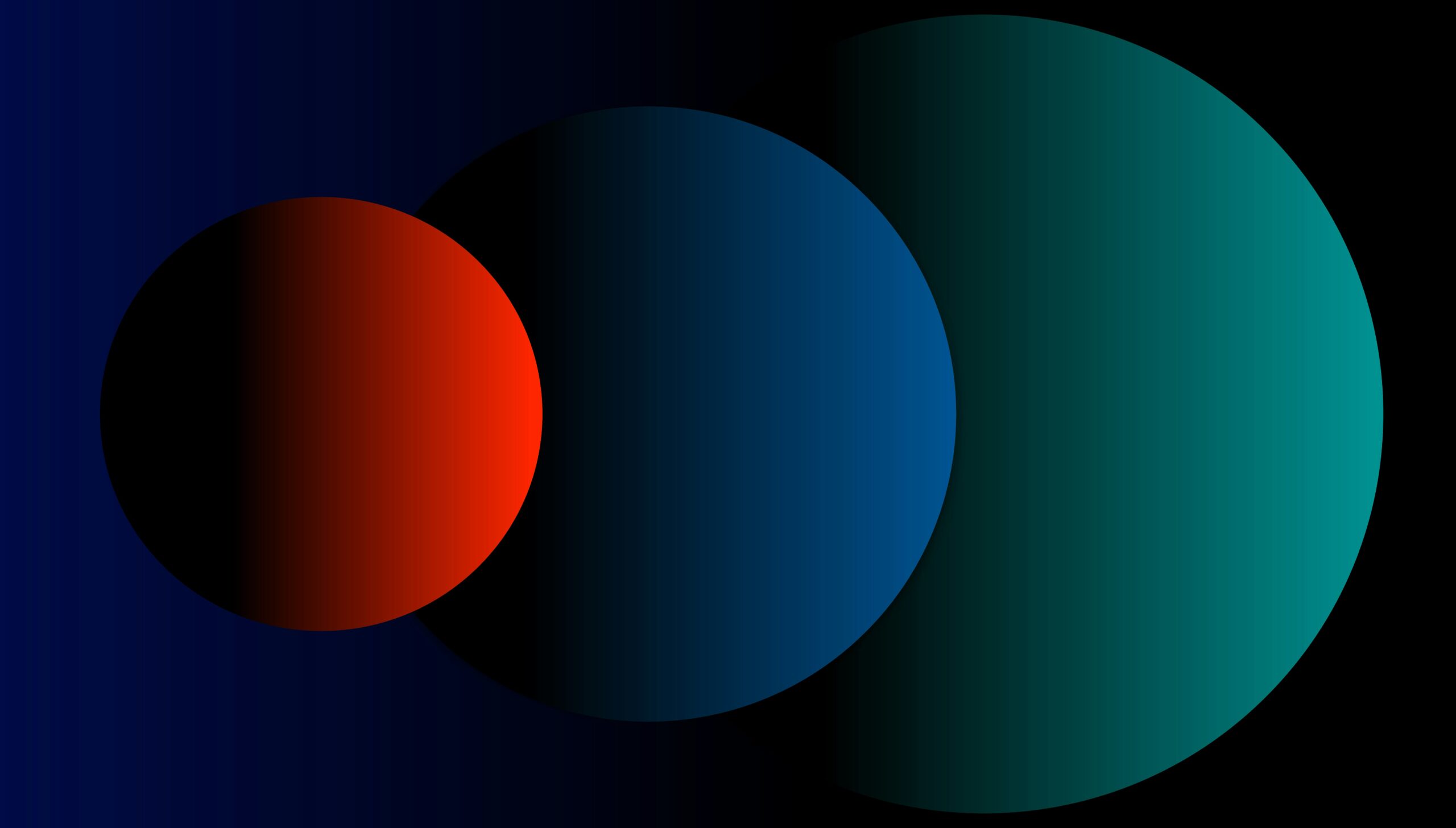

コメント