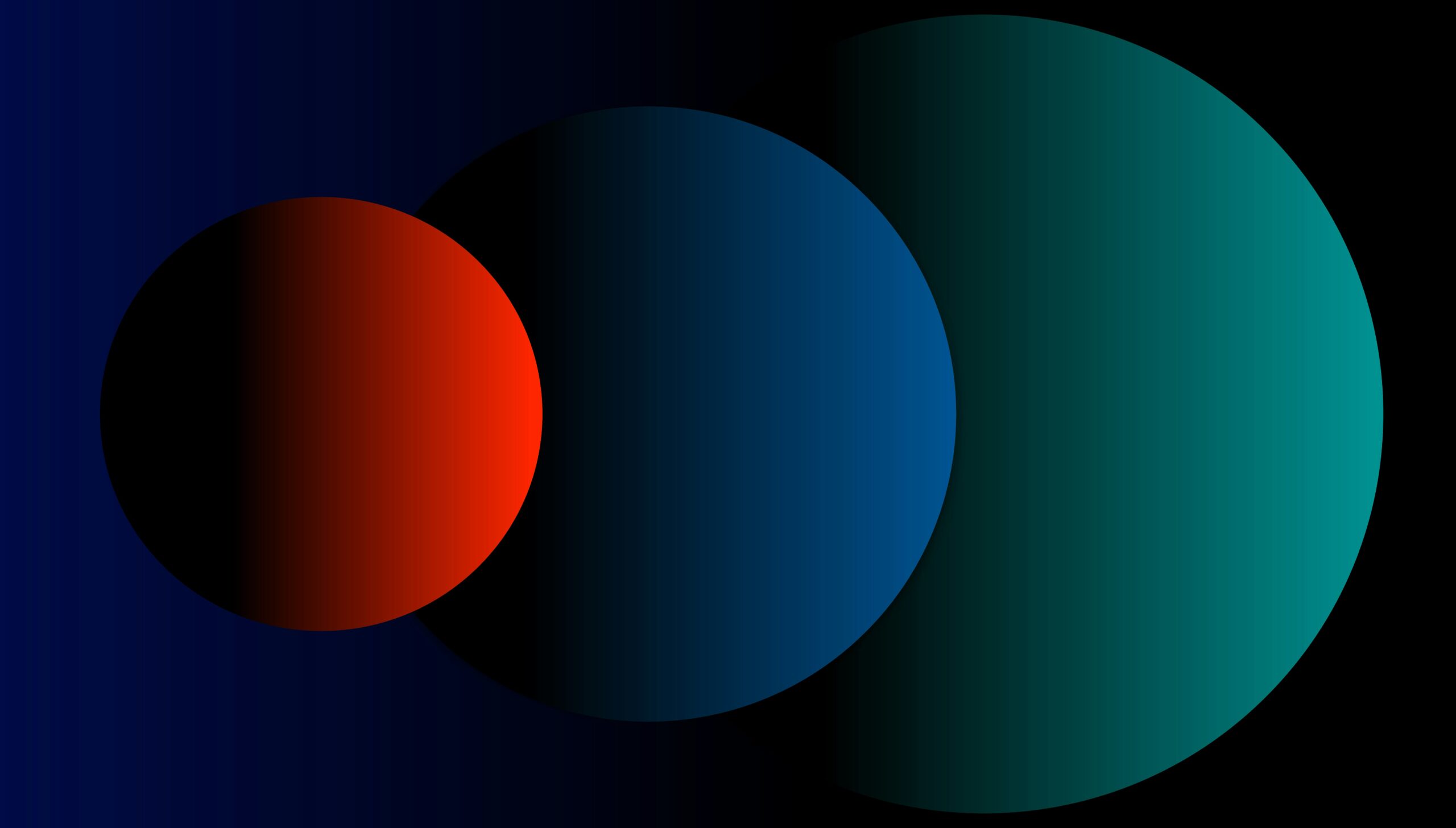
〝境界知能″といった言葉がよく聞かれるようになってきています。
その一方で、まだまだその言葉の正確な意味について、社会の中に浸透していない現状があります。
また、境界知能の人への支援についても多くの難しさがあるのが現状です。
それでは、境界知能とは一体どのようなものなのでしょうか?
そこで、今回は、境界知能の定義について、起こりやすい問題の例も踏まえて理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「梅永雄二(2024)教師、支援者、親のための境界知能の人の特性と支援がわかる本.中央法規.」です。
境界知能とは何か?
以下、著書を引用しながら見ていきます。
一般的には、知的機能が平均以下であり、かつ「知的障害」に該当しない状態を境界知能と考えます。
境界知能には明確な定義がなく、文献によっては「IQ71以上」「IQ85以下」などと書かれていることもあります。
医学的な診断がつくこともありません。
著書の内容から、〝境界知能″には、明確な定義はなく、状態像として、IQが70~84(71~85と記載されている文献もある)のゾーンの人たちのことを指します。
一般的なIQは85~114、知的障害のIQは70未満だと言われているため、〝境界知能″は、それらの境界域(間)に属しているといったことになります。
〝境界知能″の人たちは、発達障害や知的障害などと異なり、〝医学的な診断がない″とされています。
そのため、対応が必要となるケースが多いものの(潜在的なニーズも含めて)、診断を受けることができないことなどから、理解や支援の遅れに繋がる可能性が示唆されています。
起こりやすい問題の例について
著書には、境界知能の人への〝支援の不足によって起きている問題の例″が記載されています(以下、著書引用)。
生活の問題→非行、殺傷事件、特殊詐欺など
学習の問題→学業不振、不登校など
性の問題→性被害、売春など
就労の問題→就職の失敗、早期離職など
子育ての問題→特定妊婦、児童虐待など
以上の内容から、〝境界知能″の人たちは、非常に広範囲にわたって、様々な問題が生じる可能性があると言えます。
中でも、ライフステージを考えて見ても、〝学習の問題″が最初の躓きとして見られることが多くあります。
いわゆる〝学業不振″ですが、ここで境界知能のある子どもへの理解が進まないと、単に努力不足と捉えられることがある一方で、本人の精一杯の頑張りから問題が表面化しにくいことも出てきます(将来的にリスクを抱える可能性が高くなる)。
このように、周囲の理解不足(叱責などもありえる)や本人が抱える無力感などが高じると〝二次障害″に繋がるリスクが高まっていきます。
その結果、〝不登校″や〝非行″など、様々な問題へと発展することがあります。
また、正しく情報を理解する力がないと〝性の問題″を抱えたり、他者に頼る力がないと〝子育ての問題″を引き起こす可能性も出てきます。
〝就労の問題″に関しても、診断を受けることができない境界知能の人たちは、周囲からのサポートを得にくいことが多くあります。
仕事ではある程度の、業務への理解力、対人コミュニケーション能力、作業スピードなどが平均的な基準値として求められます。
全般的な遅れのある境界知能の人たちは、就労においても躓きやすく、就労が定着しにくいことがあります。
以上の内容は、境界知能の人への〝支援の不足によって起きている問題の例″ですが、こうした内容にも、状態像の違いから、人によって様々な異なる問題の例があると言えます。
以上、【境界知能の定義について】起こりやすい問題の例も踏まえて考えるについて見てきました。
境界知能には明確な定義はなく、また、診断を受けることもできないと言えます。
一方で、発達障害や知的障害などと比べて見ても、支援が行き届かないことが多く、その結果、様々な問題が起きるリスクがあると言えます。
そのため、今後ますます、境界知能の人たちへの理解と支援の必要性が高まっていくことが必要になっていきます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も境界知能の人への深い理解と、様々な支援方法について学びを深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【境界知能とは何か?】知的障害との違いと著者の経験を通して考える」
境界知能に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「境界知能に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
梅永雄二(2024)教師、支援者、親のための境界知能の人の特性と支援がわかる本.中央法規.









