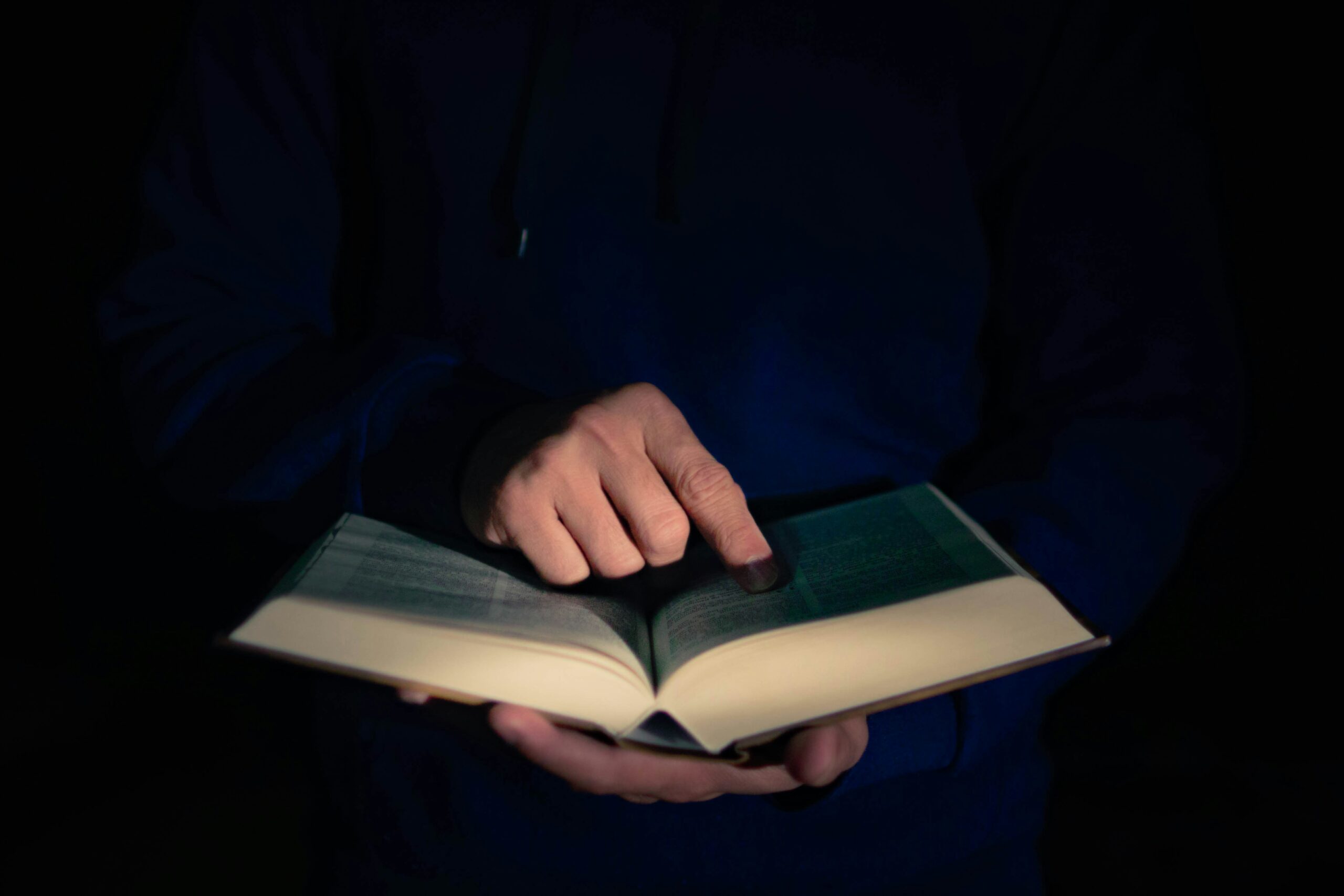
〝境界知能″とは、〝知的機能が平均以下であり、かつ「知的障害」に該当しない状態″の人たちのことを指します。
IQ(知能指数)で言うと、70~84のゾーンに当たります(71~85と記載されている文献もあります)。
〝境界知能″の人たちは、日常生活において様々な困難さが生じる可能性が高い一方で、社会の中での認知度は低く、支援の対象とはないにくいことが現状としてあります。
それでは、そもそも境界知能が起こる要因として、どのようなものがあると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、境界知能の原因について、臨床発達心理士である著者の意見も交えながら、起こりうるリスク要因について理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「古荘純一(2024)境界知能 教室からも福祉からも見落とされる知的ボーダーの人たち.合同出版.」です。
【境界知能の原因について】起こりうるリスク要因を通して考える
以下、著書を引用しながら見ていきます。
知的障害は(中略)その原因は不明であることが多いとされています。ましてや境界知能の原因を追究することは難しいでしょう。
それでも推定要因がまったくないわけではなく、リスクが高い子どももいます。その要因は生後早期の環境にあると指摘されることがあり、たとえば低体重で生まれた子ども、長期に入院した子ども、家庭環境が複雑で養育者が頻繁に代わったり施設に預けられた子ども、両親が境界知能もしくは知的障害であり家庭での養育に困難さがある場合などは、発症のリスクが高いという研究があります。この場合は、両親のIQの低さが子どもに影響するかどうかも関係します。
著書の内容から、知的障害及び境界知能の原因は現在のところ不明だとされています。
一方で、境界知能に関するリスク要因としては、生後早期の環境(低体重、長期入院、養育環境など)に加えて、両親が知的障害・境界知能だった場合における養育の困難さ、および両親のIQの低さが子どもに与える影響などがあると記載されています。
現状において、境界知能に至る原因は分かっていませんが、境界知能が起こりうるリスク要因については上記の内容があるとされています。
著者のコメント
著者これまで発達障害のある当事者、そして、境界知能のある人との関わりを通して、発達障害や境界知能がなぜ生じるのか?といった問いを持つことが、これまで少なからずありました。
ここで著者が大切にしている視点として、障害が発症する原因を追究するということ以上に、障害が起こりうるリスク要因を事前に把握しておくことで(もちろん、分からない点が多いことも踏まえて)、発達障害・知的障害・境界知能の〝早期発見・早期支援″に少なからず繋げていくことができるといった考えを持つことを大切にしています。
実際に、著者がこれまで療育現場や著者の身近な人との関わりにおいて、親が発達障害の特性を有している場合において、その子どもにも似たような特性が見られることが思いの他多いと感じることがあります。
また、知的障害や境界知能に至っても、親の知的水準が子どもに影響している場合もあると感じることがあります。
もちろん、発達障害・知的障害・境界知能に至る根本的な原因は分かっていませんが、起こりうるリスク要因を踏まえて、いかに早く発達の躓きに気づいて行けるかどうかがとても大切だと思います。
それも、実際に著者の身近にいる障害を持つ当事者において、今から見れば、明らかに障害を持つリスク要因があったにもかかわらず、〝早期発見″が遅れたことで、その後、様々な躓きや二次的な問題が増大したケースもありました。
今にして思えば、もっと早く気づいてあげることができれば、〝早期支援″に繋いでいくことができたと後悔が残ります。
それに加えて、障害を否定したいといった気持ちもまた〝早期発見・早期支援″の阻害要因になるのだと思います。
もちろん、安易な思考でレッテル貼り(○○だから○○の障害があると断定するなど)をすることはよくないと言えますが、細心の注意を払いながら、発達における躓きがないかどうかを見極めることは早ければ早いほど良いと思います。
そして、そのためには、専門機関への相談を早めることが鍵になると言えます。
今は昔とは異なり、発達障害・知的障害・境界知能(→ここに関してはまだまだ支援が不足している状況)に関する理解も高まっています。
そのため、信頼のおける専門員・相談員を探していく中で、障子を持つ保護者(あるいは障害の可能性のある保護者)が少しでも安心しながら子育てができる環境を整えていくことが必要だと思います。
以上、【境界知能の原因について】起こりうるリスク要因を通して考えるについて見てきました。
最近では、発達障害の誤診も多いと言った情報や生活習慣の乱れ・愛着形成の問題などによって発達障害のように見えてしまうこともあると指摘されています。
境界知能においては、他の発達障害との併存がなければ、逆に見落とされてしまう人たちだと言えます(困難さが見えづらいため)。
そのため、今回見てきたリスク要因なども踏まえて、早期の発見に繋げていくことがとても必要だと言えます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も境界知能に関する様々な情報を集めてきながら、早期発見・早期支援に繋げていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「発達障害の原因について機能的結合の視点を通して考える」
関連記事:「【〝発達障害もどき″とは何か?】発達障害を疑われる人たちの特徴について考える」
関連記事:「疑似ADHDとは何か【ADHDの背景には愛着障害が潜んでいる】」
境界知能に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「境界知能に関するおすすめ本【初級編~中級編】」
古荘純一(2024)境界知能 教室からも福祉からも見落とされる知的ボーダーの人たち.合同出版.









