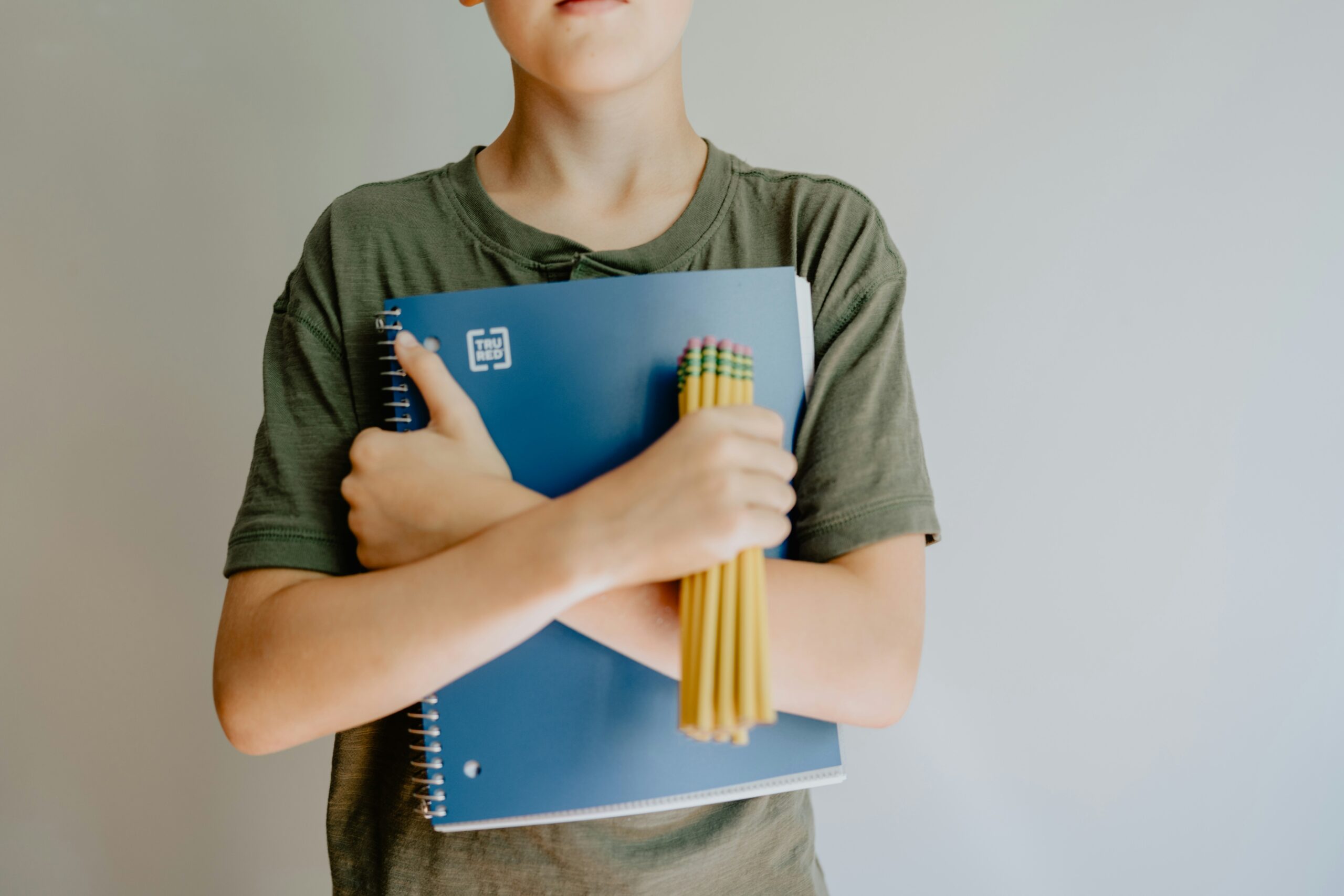
少子化の中でも不登校の児童の数は年々増加していることが分かってます。
子どもが学校に行かないことに親は強い不安を感じるかと思います。
その理由の一つに将来についての不安があります。
子どもがこの先、中学・高校へと進学していけるのだろうか?
学校卒業後に就職できるのかだろうか?
といった将来への不安感です。
それでは、不登校の子どもは将来どのような経過を辿ると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、不登校の子どもの将来について、臨床発達心理士である著者の意見も交えながら、進学率・就職率を通して理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「下島かほる(2019)健康ライブラリーイラスト版 登校しぶり・不登校の子に親ができること.講談社.」です。
進学率について
不登校の子どもが高校ないしは大学に進学することは難しいと考えている方も多いのではないでしょうか?
学校に行かないと、それだけ授業の遅れなど勉強での躓きが出てくる可能性があります。
それでは、以下に著書を引用しながら不登校児の進学率について見ていきます。
文部科学省の調査によれば、不登校経験者の進学率は、10年ほどの間に大幅に上昇しています。不登校経験者の5人に1人は、高校からさらに大学などへも進学しています。
この調査は、文部科学省の「平成26年 不登校に関する実態調査」です。
この調査結果を見ると、不登校経験者の進学率は上昇していることがわかります。
つまり、一概に不登校経験あり=進学率の低さ、とは言えない可能性があります。
仮に、子どもが不登校になったとしても、将来の進学率にはあまり影響がないといった事実を知ることで、先の不安感が軽減されるのではないかと思います。
就職率について
次に、就職率についてです。
不登校を経験した場合には、将来的に就労せずにひきこもりになる可能性が高くなると考えている方もいるのではないでしょうか?
この点についても、以下、著書を引用しながら見ていきます。
20歳の時点で就労も就業もしていない人は、18.1%(前回調査では22.8%)と報告されています。その後に、就労あるいは就業する人もいるでしょう。ずっと家に閉じこもったまま、という人は少ないと考えられます。
著書の内容から、不登校経験者が就労や就業をしていない割合は思いのほか少ないということがわかります。
そのため、一概に不登校経験あり=就職率の低さ、とは言えない可能性があります。
この点に関しても、それほどネガティブな結果とはなっていないため、先に見た進学率と同様に、こうした事実もまた将来の不安を軽減してくれるものだと思います。
著者のコメント
学校嫌いの人たちは世の中に多くいます。
また、学校は好きでもある要因が引き金となっていけない場合もあるかと思います。
不登校経験者がたくさんいる中で、著名人など仕事で成果を上げ世に認められた人たちも多くいます。
また、前述したように、不登校の経験があっても、進学率や就職率に思いのほか大きな影響が及ぼさないことも見てきました。
こうした事実を知ることで、将来の不安感を少しでも軽減していくことに繋がり、子どもの不安感に素直に寄り添う心の余裕が生まれるのだと思います。
大切なことは、子どもの心のエネルギーをしっかりと回復する対応をしていくことです。
必死になって学校に生き続けたとしても、エネルギーが枯渇した状態において、そこから人生を前向きに生きようとする意欲は生まれないように思います。
むしろ、ネガティブな経験を多く積んでしまうリスクさえあります。
しっかりと心の充電期間を設けることで、〝勉強したい!″〝友達と遊びたい!″〝○○のスポーツをしたい!″〝将来は○○の仕事をやってみたい!″といった意欲が引き出されることが大切です。
そのためには、著書にもありますが〝なんとかなる″といった考えを持ち、子どもを追いつめない関わりを心がける必要があります。
以上、【不登校の子どもの将来について】進学率・就職率から考えるについて見てきました。
将来の不安は誰にでもあります。
特に不登校など、多くの人たちとは異なる行動を取ることは将来の不安に繋がります。
一方で、今回見てきたように不登校経験者の事実を知ることで切迫した対応を取らなくても大丈夫だといった心の余裕を持つことが重要なのだと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も不登校経験者のケースも学んでいきながら、不登校支援についての理解を深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「【不登校・登校しぶりへの対応方法】3つのポイントから考える」
不登校に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「不登校に関するおすすめ本【初級編~中級編】」









