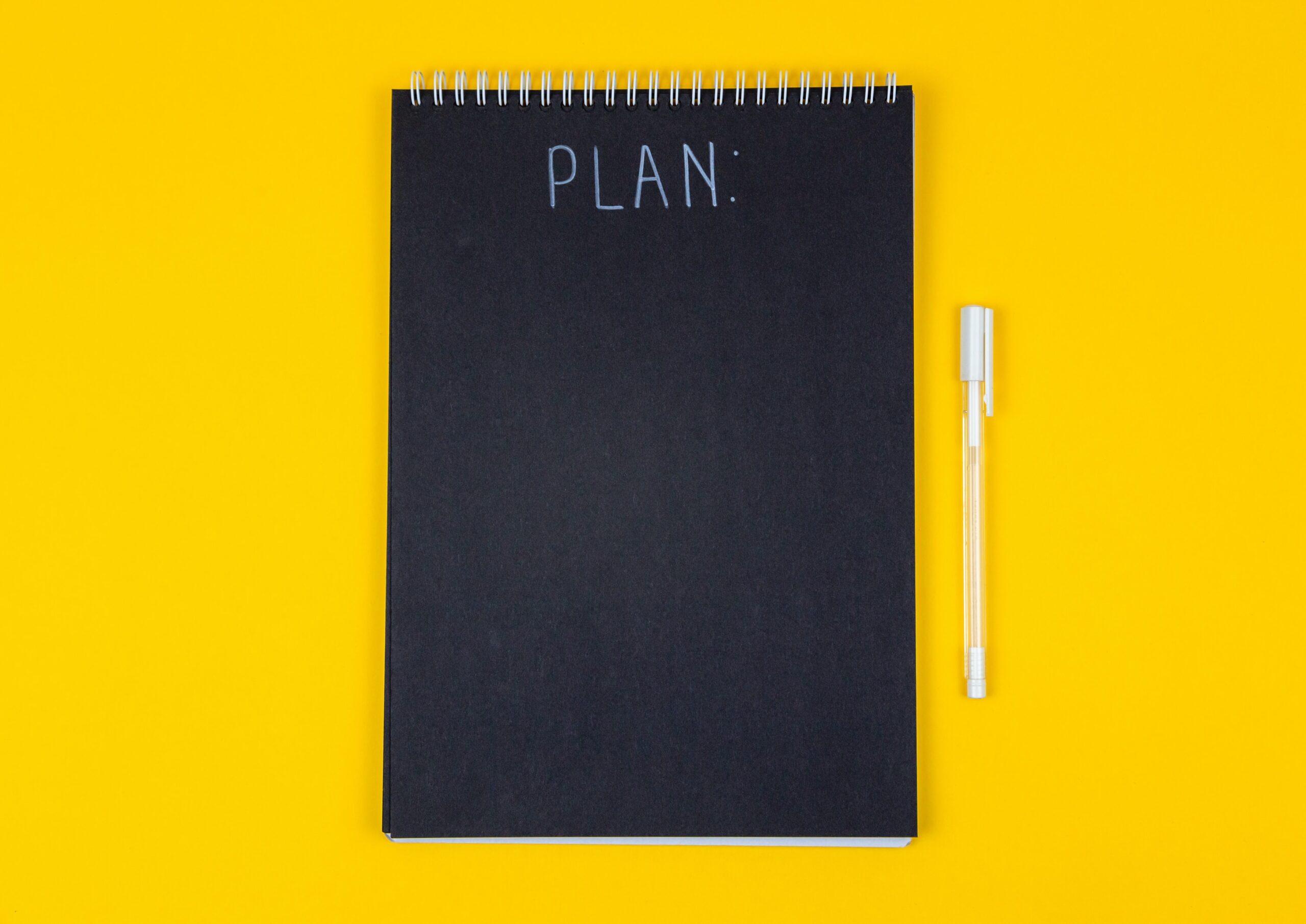
〝ゲーム依存″やネット依存が最近話題となることが増えています。
〝ゲーム依存″になるゲームの使用時間についてはまだわかっていません。
関連記事:「【ゲーム依存にならないためのルール作りについて】療育経験を通して考える」
大切なことは、過度なゲームの使用に繋がらないためのルール作りも一つの方法だということです。
一方で、ルールを決めても守れないこともあります。
それでは、ゲームの使用について一度決めたルールを守れないときにはどのような対応方法が必要になるのでしょうか?
そこで、今回は、ゲーム依存への対応方法について、ルールを守れない時の対応について理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「森山沙耶(2023)専門家が親に教える子どものネット・ゲーム依存問題解決ガイド.Gakken.」です。
ゲーム使用のルールを守れない時の対応について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
できなかったことを責めるのではなく、一定期間様子を観察してルールを守れたときに十分にほめてあげることやポイントなどを活用して達成感を得られるような工夫をしてみるとよいでしょう
著書の内容では、ゲーム使用のルールを守れない時の対応として、まずはできなかったことを責めたり、罰を与える対応は効果的ではないとしています。
そのため、必要な対応としては、加点方式での関わり方を重視するというものです。
つまり、決めたルールを完璧に守ることを目指すのではなく、ルールを守れたときにしっかりと評価をしていく関わりを取ることです。
そのためには、ルールを守れなかったとしても、その後の、子どもの様子をよく観察し続ける必要があります。
長期の観察を行うことで、子どもがルールを守れた場面があればすかさず褒める機会を増やしていくことができます。
こうした〝加点方式を重視した関わり方″は、子どもの望ましい行動を強化するといった視点に基づいています。
また、一度、ルールを作った後も、ルールのモニタリングやそのルールが子どもに合っているのかを見直し、修正していくことも必要な取り組みです。
以上が、〝加点方式を重視した関わり方″になります。
その他にも著書にはいくつかポイントが記載されています(以下、著書引用)。
ルールを守りやすい環境を考える
スケジュールを工夫する
守れなかったときの約束を事前に決めておく
著書にある〝ルールを守りやすい環境を考える″や〝スケジュールを工夫する″ことは環境調整の視点として大切です。
例えば、目の前にゲームを置いておかない、宿題を終えた後にゲームをすることを習慣化していくなどです。
人間は目の前に好きなものがあると無意識的に手にとってしまいたくなります。
そのため、できるだけ視覚から取り除くような環境調整が必要です。
また、好きなゲームをスケジュールの後に持ってくるようにした方が、過度なゲーム行為に繋がることを減らすことができます。
また、著書にあるように〝守れなかったときの約束を事前に決めておく″ことも方法としてあります。
この方法は、子どもが望む欲求を得られなくすることで、大人が望む行動(子どもに望む姿)を強化するといった視点に基づいています。
この中で大切なことは、〝事前に約束を決める″ことです。
〝子どもに事前に合意を得る″といったことですが、まずい対応としてやりがちなものは〝事前に約束をせずに罰を与える″といった方法です。
例えば、ゲームをやりすぎているので勝手に取り上げるなどがあります。
あくまでも、事前に約束を行いないながら、環境調整と加点方式を重視した関わり方を心がけることが大切です。
以上、【ゲーム依存への対応方法】ルールを守れない時にどのように対応すればいいのか?について見てきました。
子どもがゲームをやりたくてルールを破ることは少なからず見られるものだと思います。
大切なことは、ルールを絶対視せずに、子どもの思いを尊重しながら、少しずつルールの定着を図っていくことだと思います。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後もゲームなどメディアとの付き合い方について、療育現場でできる対応を考え、工夫していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
森山沙耶(2023)専門家が親に教える子どものネット・ゲーム依存問題解決ガイド.Gakken.









