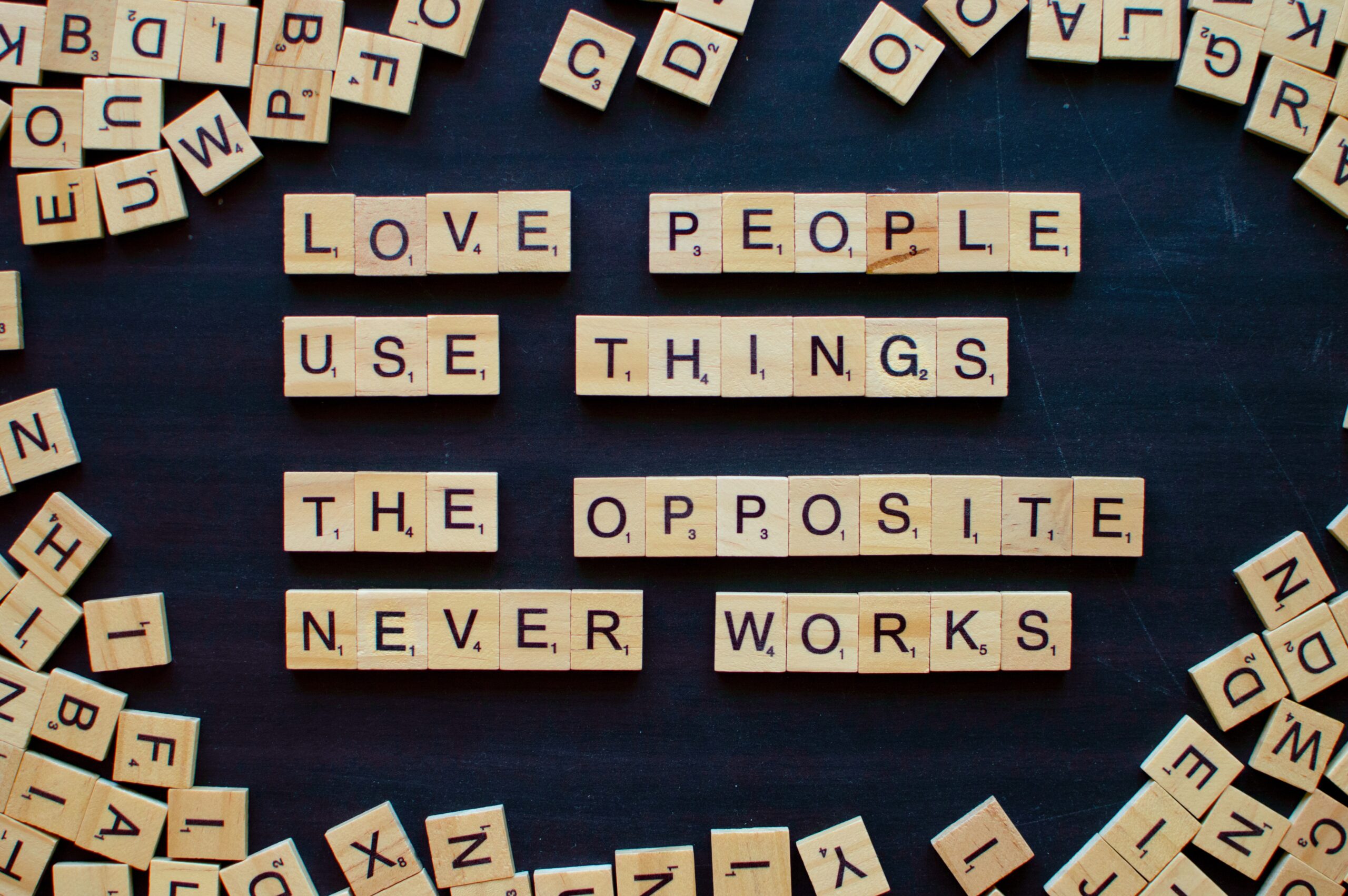
知能検査で代表的なものに、ウェクスラー式知能検査(WISC)があります。
WISCで測定できるものに、言語理解、知覚統合(知覚推理)、ワーキングメモリー、処理速度の4つの群指数と、これらすべての合計得点から算出される全検査IQがあります。
関連記事:「ウェクスラー式知能検査とは【発達障害の理解と支援で役立つ視点】」
それでは、発達障害の中で、ASD(自閉症スペクトラム障害)によく見られるこだわり行動の強さと関連する指標などは知能検査から推測することができるのでしょうか?
もちろん、知能検査(発達検査)自体、こだわり行動などの発達特性を測るものではありませんが、傾向として関連するものはあるのでしょうか?
そこで、今回は、知能検査から見た言語理解の高さの特徴として、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら、言語理解とこだわりの関係について理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「岡田尊司(2022)発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法.SB新書.」です。
知能検査から見た言語理解の高さの特徴【言語理解とこだわりの関係】
タイトルにある通りに、こだわりの強さと関連する指標に言語理解の高さ(詳しくは、言語理解>知覚統合)があります。
以下、著書を参照しながら見ていきます。
筆者が注目しているのは、発達検査で調べることができる「言語理解」と「知覚統合(知覚推理)」の比率だ。言語理解が高く、それに比べて知覚統合(知覚推理)が低い傾向があると、自閉スペクトラム指数(AQ)のなかの、「注意の切り換え」の困難さを示すスコアが高い傾向を示す。
著書の内容から、言語理解の高さがこだわりといった注意の切り換えの悪さと関連しているといった記載があります。
この場合のポイントが、言語理解>知覚統合(知覚推理)といった傾向がある場合に、ASDによく見られるこだわりの強さと関連性で出てくるということです。
知覚統合(知覚推理)とは、視覚情報から物事の全体像や関連性などをイメージ・推論する能力です。
そのため、知覚統合(知覚推理)が低く、それに比べて言語性が高いと、言葉によって、物事の全体像よりも部分に着目した理解や推論をする傾向が出てきます。
こうした情報処理の仕方が、こだわり行動と関連してくるということです。
それでは、次に上記の内容について著者の経験談から見ていきます。
著者の経験談
著者の周囲にもASDの方、こだわり行動が強い方がいます。
確かに、こうした人の情報処理の仕方を振り返ってみると、言語理解が高く、それに比べて、全体像よりも部分に着目しやすい傾向があるように思います。
例えば、その日の活動のスケジュールをスタッフ全員で考える際に、優先順位を踏まえて予定を相談するときなど、全体を見据えてというよりも、その人にとって目につく・目につきやすいことから優先的に予定を立てようとする傾向があるように思います。
療育での活動を見ても、全体の子どもたちの動きから自分の役割や動きを考えるというよりも、特定の子どもの行動などに着目しがちです。
一方で、部分に着目しそれを言葉にする力が高いため、周囲がなかなか気づけないようなことを発見するなどの強みもあります。
子どもへの対応が一つ一つ丁寧、子どもが興味を示していることへの気づきも細かい点を含めて多くあるように思います。
こうしてみると、状況により、人間の短所は長所になり、長所は短所になるのだと改めて考えさせられます。
それでは、最後にこうしたこだわり行動を抜け出すには、どのような取り組みが考えられるのかについて見ていきます。
こだわりから抜け出すためには何が必要か?
ちなみに、こだわり行動(言語有意な状態)から抜け出すために、著書は以下の行動を推奨しています(以下、著書引用)。
こだわりすぎるのを脱するためには、言葉で考えすぎるのをやめて、イメージや身体感覚を活性化したり楽しんだりする取り組みを増やすとよいようだ。
頭の中に浮かんでくる様々な思考を停止させるには、身体を動かすことがいいということをよく聞くことがあると思います。
こだわり行動を一時的に中断するためには、身体を使うことを意識してみてもいいかもしれません。
確かに、人は身体を夢中で使ってる時には、頭で考えている余裕などないかと思います。
以上、知能検査から見た言語理解の高さの特徴【言語理解とこだわりの関係】について見てきました。
先にも述べましたが、ASDによく見られるこだわり行動自体は知能検査(WISC)で測定するものではありませんが、傾向として言語理解>知覚統合(知覚推理)といった状態に、こだわり行動はよく見らえることは知っておいてもいいと思います。
人を理解するには、様々な情報が必要不可欠です。
知能検査から分かることも非常に多くあるように思います(もちろん、拡大解釈には注意が必要です)。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も知能検査といった客観的指標からも人を理解するヒントを学んでいきながら、療育の現場に活かしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
発達障害のアセスメントに関するお勧め書籍紹介
関連記事:「発達障害のアセスメントに関するおすすめ本【初級~中級編】」
岡田尊司(2022)発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法.SB新書.









