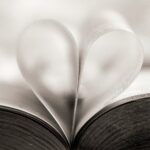私は障害児保育や放課後等デイサービスなどで子供たちの発達をサポートする仕事をしてきました。今もしております。今回はその経験から人の発達に携わる仕事の難しさや、やりがいなどについて書いていこうと思います。
私は障害児保育歴4年、放課後等デイサービスなど学童を対象とした発達支援を3年以上にわたり行ってきました。その中で、今回は学童期での経験から見えてきた発達特性に的を絞り難しいと感じる点から述べていこうと思います。
発達支援を行う上で非常に難しくかつ大切なことは相手を理解することだと思います。特に自分が携わる仕事では、相手とうまく意思疎通ができないコミュニケーションの問題、見通しを立てて行動することが苦手、集団活動が苦手、他児とすぐにトラブルになる等といったお子さんたちが多いです。こういった行動にはそのお子さんたちが生得的にもっている発達特性が関与している可能性があります。例えば、自閉症児の場合は、相手の意図をくみとって行動することが難しい、自分なりの手順にこだわるなどの特性があります。また、注意欠如/多動性障害児であれば、気が散りやすく注意の持続が難しい、複数の情報の取り込みが難しい、段取りを組むのが難しい、順番が待てないなどの特性があります。当然、人に応じて特性の出方や強さに違いはありますが、本人ではコントロールが難しい面が多いです。その意味で、本人の特性にあった環境調整が重要になってきます。例えば、相手の意図のくみ取りが難しいのであれば、相手は「〇〇の場面において、○○しようとしていた」など論理で伝えたり、手順へのこだわりでは事前に約束やルールなどを決め本人が安心できる環境を早めに整えておく、気の散りやすさや情報の取り込みの難しさには、静かな環境で要点を絞って伝える、段取りを組む難しさは早めに本人と予定を確認し適宜どこまで進んだか確認をとる、順番待ちではルールの確認を事前に決めたり確認するなどの配慮が必要になるかと思います。
ここに挙げたのは特性の一部であり、比較的私の現場で多く見られるものになります。相手を理解するためには発達特性の理解とそれに伴う配慮が大切です。そして、子どもたちだけではなく、現場で関わる人たちやご家族など支える側へもお互いの取り組みをねぎらうことを忘れてはいけないと思います。特性の理解や配慮は即時的な対応では効果は少なく、長期的な取り組みの中でこそ効果が出るものだと思います。
次に、これまでお話ししてきた経験から得られたやりがいについて書いていこうと思います。
まずは子供たちの成長が見れるということです。成長の過程を見るのは長期的な関わりが重要となりますが、その中で、これまで予定の変更にうるさかったお子さんが少しの説明で合意が取れるようになった、相手を配慮して行動する機会が増えた、大人や子供たち同士でルールを話し合い遊べることが増えた、遊びのレパートリーや質が変化したなど様々な事例がありました。私の中では、何か興味のあるものがあり、それに没中できる体験を小さい頃から積み重ねることが非常に重要だと思っていますので、大人側がそれを保障する環境を作れるかが支援のキーポイントだと思っています。
また、こうした体験を保護者や他の職員と共有できたという経験もやりがいの一つです。発達支援は一人でできるものではなく、複数の人間が連携しチームで行動することがとても重要になってきます。そのためにはお互い建設的なコミュニケーションをとっていくことが重要になると思います。気が付いたら子供たちの良い点、成長の発見があったということを他者と共感できるのは大きな喜びと次への原動力になります。
最後に、私の最大のモチベーションである人の理解を深めるという視点もやりがいの一つです。現場では多くの疑問を子供たちは私に投げかけてくれる存在です。現場経験から生じた問いを解くことは、多くの情報収集や試行錯誤を要します。その過程から過去の自分は知らなかったということが多くあります。何かを知る喜び、わからないことが多くあるという実感は人生を歩んでいくうえで重要だと思います。
今後も、自分の好奇心を大切に、他者と疑問や発見を共有する機会をしっかりと持ちながら日々学んでいこうと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。