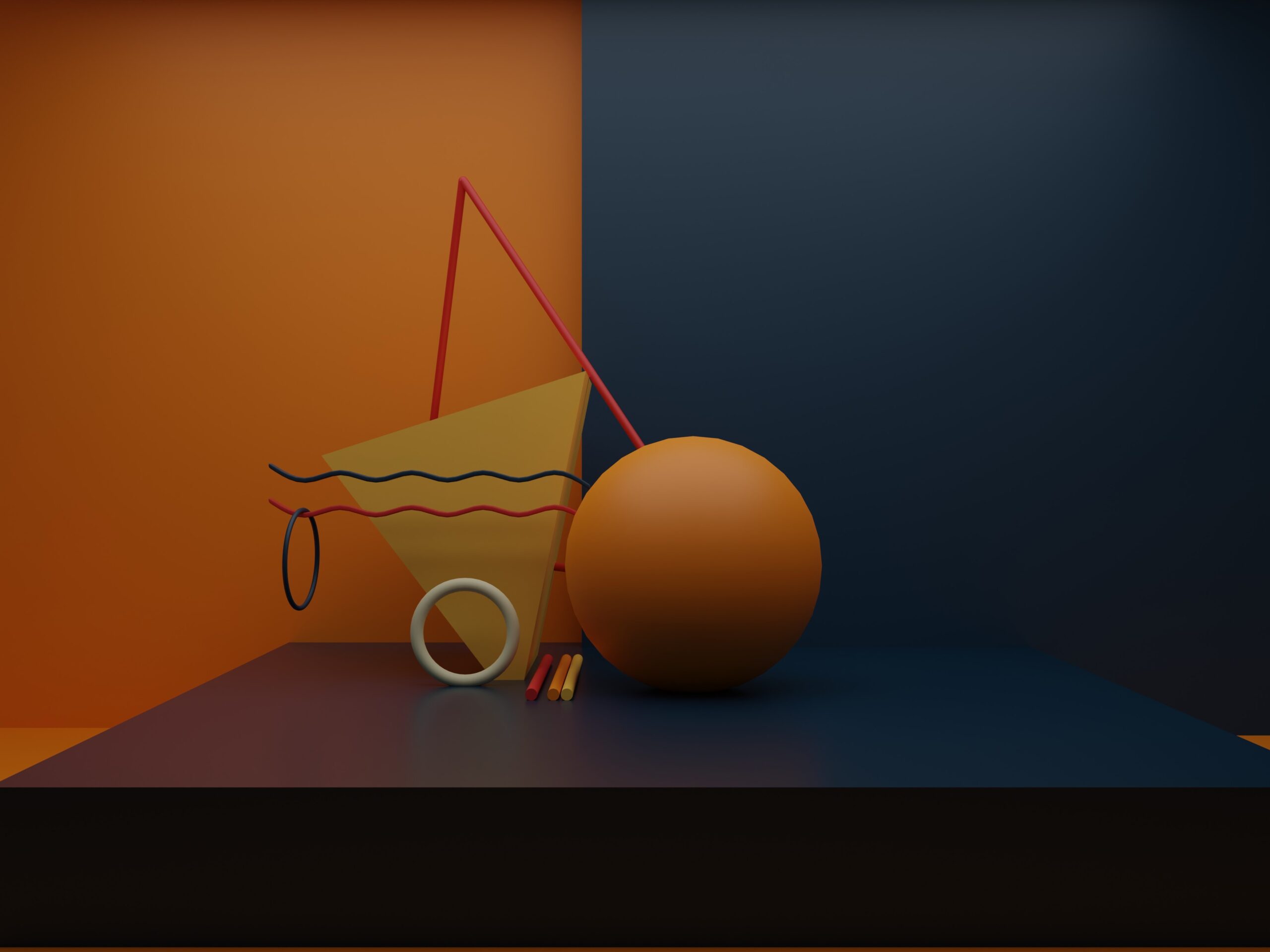
自閉症(自閉症スペクトラム障害:ASD)の人たちは、物事の全体像を理解することよりも、物事の細かい部分、つまり、細部知覚に優れていると言われています。
全体知覚が〝木を見て森を見ず″といった状態であるのに対して、細部知覚は〝森の中から木を見抜く″ことに優れていると言えます。
それでは、自閉症の人たちはなぜ細部知覚に優れているのでしょうか?
そこで、今回は、自閉症の人たちはなぜ細部知覚に優れているのかについて、弱い中枢性統合の視点を中心に理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「千住淳(2014)自閉症スペクトラムとは何か-ひとの「関わり」の謎に挑む.ちくま新書.」です。
自閉症者が細部知覚に優れている理由について
以下、著書を引用しながら見ていきます。
自閉症者が、なぜ「森の中から木を見抜く」能力に優れているのかについては、研究者によって意見が分かれています。
著書の内容から、自閉症者が全体知覚よりも細部知覚に優れている点について研究者によって異なる仮説があるとされています。
そして、その仮説は以下のものがあります(以下、著書引用)。
ある研究グループは、脳の発達の違いにより、細かい部分の情報を把握する脳の働き(「局所処理」と呼ばれています)がより強くなっている
自閉症者は、物事の全体像や関係性を把握する脳の働き(「中枢性統合」と呼ばれています)が苦手である
単に細かい部分に注意を向けるのが「好き」なため、結果的に細かい部分を把握する傾向が強い
以上、様々な仮説があります。
要約すると、①局所処理といった脳の働きの違い、②弱い中枢性統合、③単に細部に注意を向けることが〝好き″が仮説として考えられています。
①~③は互いに独立したものではなくリンクする点も多くあるように思います。
中でも面白いのは、③の自閉症者は全体知覚が苦手でもなく、細部知覚が得意でもなく、単純に細かい点に注意を向けることが〝好き″といった仮説です。
著者の周囲の自閉症児・者を見ていても、物事の細部の話をしている時にとても生き生きしているようにも見えます。
例えば、アニメのキャラクターの話、電車や車の話、植物の話など、これらの話は非常にマニアックな知識を有している場合が多くあり、その特徴は細部を掘り下げていくといった印象があります。
弱い中枢性統合の視点から考える
そして、現在、様々な書籍で自閉症の優れた細部知覚の特徴を説明しているものが②の〝弱い中枢性統合″になります。
〝弱い中枢性統合″とは、物事の様々な部分同士を関連づける苦手さを特徴としています。
これは、繰り返しになりますが〝木を見て森を見ず″とも言い換えることができ、例えば、アニメのストーリー性やアニメに登場する人間関係といった全体に視野を向ける力のことを指します。
自閉症児・者が見せる〝弱い中枢性統合″には、アニメで言えば、特定のキャラクターの情報を膨大にもっている、アニメのストーリーの特定の部分に強い興味関心を向けるなどが例としてあります。
著者の周囲の自閉症児・者を見ていても、こうした特徴はよく見られるように感じます。
一方で、全体知覚が苦手な一方で、細部知覚に優れていると感じることがあります。
例えば、先ほど見てきたアニメでは特定の部分に関して異常なまでの知識を有していることがあります。
また、文章の内容や作業内容での細かいミスに気づきやすいことも利点してあるように思います。
特に、正確性を要する作業、緻密な作業においては、細部知覚に優れている方が強みとして業務に活かされるように思います。
以上、【自閉症の人たちはなぜ細部知覚に優れているのか?】弱い中枢性統合の視点から考えるについて見てきました。
細部知覚に優れている自閉症の特徴には様々な仮説があり、今も研究が進んでいます。
そして、細部知覚に優れているという能力を著者は社会の中でどのようにうまく発揮していくことができるのかを考えていくことが大切であると考えます。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も自閉症の特徴について学びを深めていきながら、そこで得た知見を療育現場に活かしていけるように日々の実践を大切にしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「自閉症の中枢性統合/全体的統合について:療育経験を通して考える」
関連記事:「【弱い中枢性統合仮説とは何か?】自閉症の特徴について考える」
千住淳(2014)自閉症スペクトラムとは何か-ひとの「関わり」の謎に挑む.ちくま新書.









