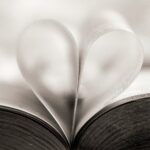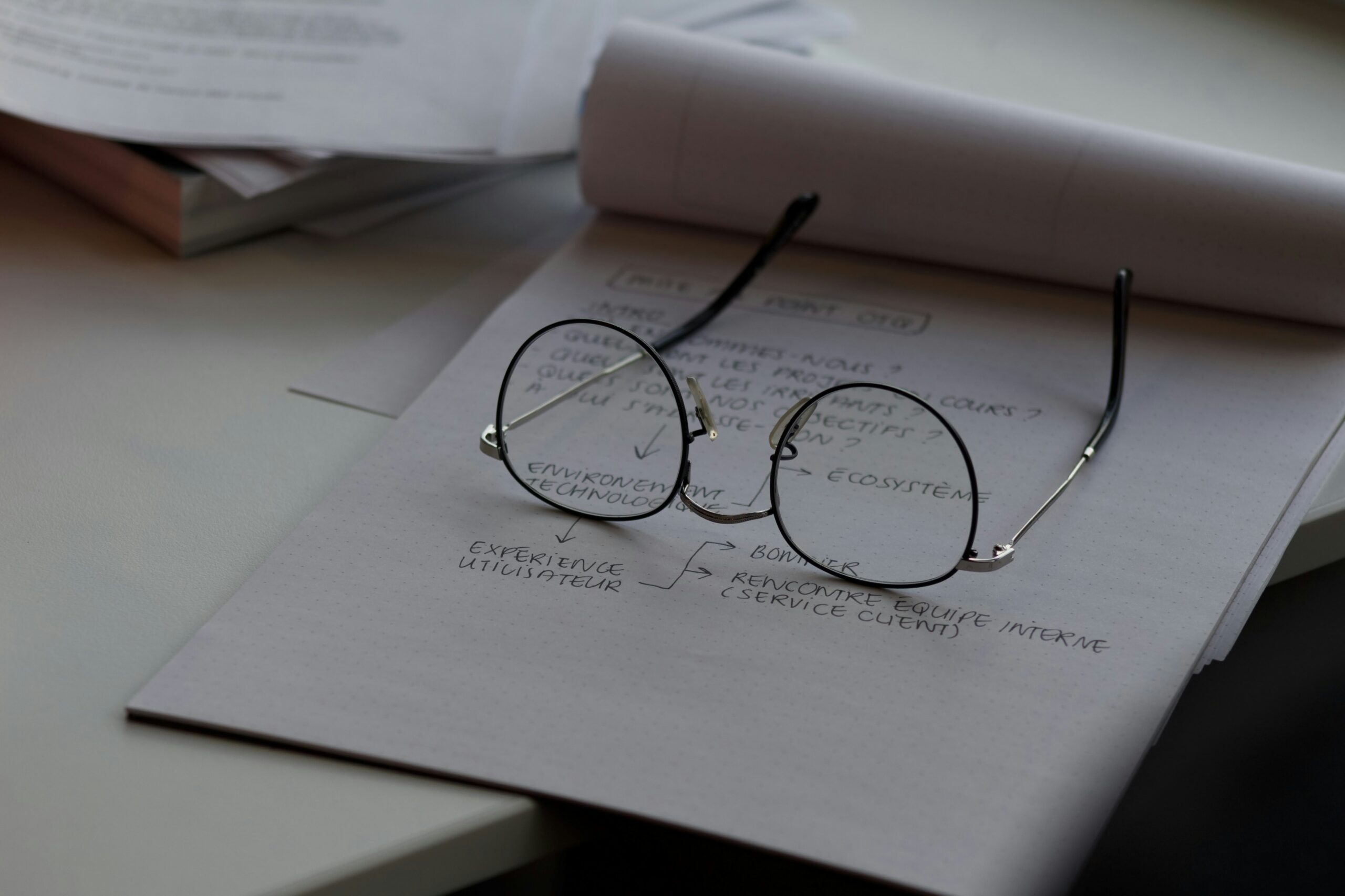
ADHDは先天的な脳の機能障害が原因だと考えられています。
一方で、最近、ADHDとよく似た特徴として〝疑似ADHD″があることがわかってきています。
″疑似ADHD”には、〝愛着障害″など環境要因が影響している場合もあります。
それでは、ADHDと愛着障害の違いには、どのようなパターンがあると考えられているのでしょうか?
そこで、今回は、ADHDと愛着障害の違いについて、ADHDの背景要因を通して理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は「岡田尊司(2020)ADHDの正体:その診断は正しいのか.新潮社.」です。
ADHDと愛着障害の違いについて【ADHDの背景要因から考える】
それでは、ADHDの背景要因について以下著書を引用しながら見ていきます。
①発達障害による本来のADHD
②本来のADHDが、愛着障害を含む養育・環境要因によって悪化している場合
③主に愛着障害を含む養育要因によって疑似ADHDを生じている場合
④主に養育要因以外の原因により疑似ADHDを生じている場合
以上、著書の中では、ADHDの背景要因には4つの要因が想定できるとされています。
この中で、愛着障害が関連しているのは、②と③です。
それでは、次にそれぞれ具体的に見ていきます。
①発達障害による本来のADHD
冒頭に述べた通り、発達障害は先天性の脳の機能障害が原因だと言われています。
そのため、「生まれつき」の特性だとされています。
また、ADHDの特徴は発達期に行動特性として徐々に見られるようになります。そのため、大人になって急に見られるものではありません。
発達障害自体スペクトラムですので、ADHDの特性には強弱が見られます。
また、不注意優位型、多動・衝動優位型、混合型など様々なタイプがあります。
②本来のADHDが、愛着障害を含む養育・環境要因によって悪化している場合
ADHDが一次障害として、その後の環境要因によって二次障害として、本来の特性が悪化しているケースです。
二次障害が発症すると、そもそもの一次障害であるADHDが見えにくくなる場合もあります。その中で、支援・対応で重要なのは二次障害への理解と支援です。
つまり、愛着障害から介入を行うことが症状の改善において重要だということになります。
③主に愛着障害を含む養育要因によって疑似ADHDを生じている場合
著書の岡田さんは成人のADHDの人の中で、ADHDと特徴がよく似た疑似ADHDの人が増加していると述べています。
その要因は、養育者との関係性にあると言われています。
両者の違いを見分けるポイントなど詳細は以下の記事に記載しています。
関連記事:「疑似ADHDとは何か【ADHDの背景には愛着障害が潜んでいる】」
④主に養育要因以外の原因により疑似ADHDを生じている場合
養育環境以外の要因について以下著書を引用して見ていきます。
情報環境や食品添加物などの生活環境の影響が挙げられる。たとえば、学業・仕事が忙しかったり、スマートフォンやゲームに熱中したりして、睡眠不足が続き、不注意が目立っているという場合がある。ただし、④のみで起きていることは少なく、発達障害や愛着障害と絡まり合っていることが多い。
著書の内容から、情報環境や食品関係からもADHDと似た疑似ADHDの特徴が見られる場合があります。
しかし、著書にもある通り、発達障害や養育環境などの影響と関連している場合が多く、④のみ単独で起こることは少ないと考えられています。
以上、ADHDの背景要因を4つ見てきました。
こうした背景要因がある中で、大人のADHDにはある特徴があることが研究結果からわかっています。
大人に多い疑似ADHDについて
それでは、引き続き著書を引用します。
中でも成人ADHDについては、(中略)一連のコホート研究の結果より、その九割以上が①でも②でもなく、③または④だということが明らかになっています。
これまでの研究結果から、大人のADHDの多くは(ADHDだと診断されている)、本来生まれ持ってのADHDではなく、生まれた後の養育環境や環境要因(情報環境や食品関連)などの影響により、ADHDと似た疑似ADHDであるとされています。
そのため、生育歴など子どものときの行動特徴を調べることが非常に大切になります。
本来のADHDであれば、発達期のどこかの時点でADHDの特徴が見られはじめ、その特徴が持続していることになります。
ADHDか愛着障害か、あるいは両方あるかを見極める必要性は、支援・対応方法が異なるからです。
疑似ADHD(愛着障害など)の人にADHDの理解と対応をしても効果は期待できません。
大切なことは、困り感の要因を、発達的視点をもって正確に分析することです。
以上、ADHDと愛着障害の違いについて【ADHDの背景要因から考える】お伝えしてきました。
私自身、療育現場でADHDの子や愛着に問題を抱えている子どもたちを見ています。
その中で感じるのは、できるだけ情報を多く集め、正確な見立てを行うということです。
見立てが間違ってしまうとその後の支援がうまく進まないことが多くあるからです。
私自身、まだまだ未熟ですが、今後も子どもから成人まで多くの発達に躓きのある人への理解を深めていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
岡田尊司(2020)ADHDの正体:その診断は正しいのか.新潮社.