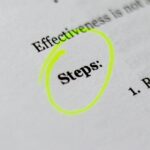著者はこれまで多くの自閉症児・者と関わってきています。
自閉症児の多くは〝感覚過敏″が見られます。
もちろん、〝感覚過敏″の種類や強度は人によって違います。
著者は〝感覚過敏″が強い自閉症の人たちは〝時間へのこだわり″が強いと感じたことがこれまでの経験上よくあったと思います。
それでは、自閉症の人たちの感覚の過敏さは時間感覚と関連性はあるのでしょうか?
そこで、今回は、自閉症の感覚過敏について、時間感覚との関連性を通して理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「井手正和(2022)発達障害の人には世界がどう見えるのか.SB新書.」です。
自閉症の感覚過敏と時間感覚との関連性について
著書では実験を通して時間感覚を測る指標として〝時間分解能″という用語を使用しています。
〝時間分解能″の高さとは、著書によれば〝正確に時間順序を判断する能力″の高さであると記載されています。
つまり、〝時間への感度が高い″と言い換えてもいいかと思います。
それでは、自閉症の時間感覚にはどのような特徴があるのでしょうか?
以下、著書を引用しながら見ていきます。
結論からいえば、「時間分解能には個人間で大きな差がある」ということがわかりました。
「高い時間分解能を持つASD者は、日常生活においてより強い感覚過敏を経験している」(中略)これは定型発達者には見られない(時間分解能が高いからといって、その人は感覚過敏ではない)結果でもありました。
著書の内容から、自閉症の人の感覚過敏さと時間感覚には関連性があるといった記載があります。
つまり、感覚過敏が強いと、時間への感度も高いということです。
一般的には、時間感覚には個人差があります。
そして、定型発達の人たちでは、時間感覚と感覚過敏との間に関連性はない中で、自閉症の人たちには関連性があるという違いが見られています。
著書のコメント
小学生Aさんの事例
Aさんは自閉症の特徴が強く見られる子どもであり、〝人″への関心は乏しく、〝もの″への関心が強い傾向がありました。
当時のAさんは、一人遊びを好み、できるだけ静かな空間で工作をしたり絵を描いたり、読書をして過ごすことが多くありました。
Aさんには、感覚の問題の中でも〝聴覚過敏″が日頃から強く見られていました。
例えば、工事の音、他児の泣き声、突発的になるアラームなど、他の人よりも過敏に反応する様子が多くありました。
そして、こうした刺激が多いと必ず状態が崩れたり、その環境を未然に避けようとすることがよくありました。
例えば、活動中に他児集団や大きな音がする場所をできるだけ避けて、一人で静かに過ごす様子が多く見られるなどです。
一方で、Aさんには、〝時間へのこだわり″も強くありました。
帰りは決まった時間に絶対に帰りたい、少しでも遅れるとイライラ状態や癇癪を起こす一方で、物の貸し借りなどにおいては時間を守って使う様子もありました。
当時のAさんは時間への感度が高く、時間をしきりに気にする様子が多くあり、帰りの時間も体内時計で把握しているようにも思えるほど、著者が時間を伝える前に行動に移す様子がよくありました。
それは好きな遊びに没頭していても、それ以上に時間を優先するというイメージです。
この時のAさんを振り返って見ると、〝感覚過敏″の高さと〝時間感覚″の高さとが非常に関連していると、今回取り上げた著書も踏まえると推察することができます。
そんなAさんでしたが、ここ最近、〝もの″よりも〝人″に興味を示すようになってきました。
そして、何故か〝聴覚過敏″も減り(減ったように見え)、それに付随するかのように〝時間へのこだわり″も軽減していったように感じます。
もちろん、〝こだわり″自体はなくなったわけではなく、その対象が変化したのだと思います。
その対象とは、当時気にしていた〝時間″ではなくなり、〝人″に切り替わってきたように思います。
そして、帰り時間になっても帰ろうとしない様子(もっと遊びたい!という思いの強さから)も見られるなど、〝時間″へのこだわりから、〝興味のある対象を共有したい人″へとこだわりの対象が移行したように見えます。
もちろん、この内容は著者の仮説ですが、ここ数年の変化を通して感じるAさんの成長・発達なのだと考えています。
このように、感覚過敏と時間感覚とは関連しているのだとこれまでのAさんとの関わりを通して感じることができます。
以上、【自閉症の感覚過敏について】時間感覚との関連性を通して考えるについて見てきました。
人間の感覚は成長・発達すると言われています。
感覚の過敏さが高い世界とは、ある種の不安に満ちた混沌とした状態なのかもしれません。
一方で、Aさんの事例を踏まえて言えば、人への興味や安心が増したことで、外界の世界に対する不安や恐怖が減り、そのことが感覚過敏の低減(時間感覚の低減も含め)に繋がったのかもしれません。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も療育現場において、子どもたちの安全・安心の基地になれるように子どもたちの気持ちに寄り添っていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
関連記事:「自閉症の感覚過敏とこだわり・コミュニケーション障害の関係について」