〝ワーキングメモリ(working memory)″とは、情報を記憶し、処理する能力のことを言います。〝脳のメモ帳″とも言われています。
ワーキングメモリの機能として、〝言語性ワーキングメモリ(言語的短期記憶)″と〝視空間性ワーキングメモリ(視空間的短期記憶)″とがあり、両者を統合する司令塔的役割が〝中央実行系″と言われています。
それでは、ワーキングメモリの機能として非常に重要な視空間性ワーキングメモリとは一体どのような機能なのでしょうか?
そこで、今回は、視空間性ワーキングメモリとは何かについて、学習活動との関連性から理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「湯澤正道・湯澤美紀(2017)ワーキングメモリを生かす効果的な学習支援―学習困難な子どもの指導方法がわかる!.学研.」と「トレイシー・アロウェイ・ロス・アロウェイ(著)湯澤正道・湯澤美紀(監訳)上手幸治・上手由香(訳)(2023)ワーキングメモリと発達障害[原著第2版]: 教師のための実践ガイド.北大路書房.」です。
視空間性ワーキングメモリとは何か?
以下、著書(湯澤ら,2017)を引用しながら見ていきます。
- 視空間領域
- 視空間的短期記憶・・・・・・形や位置などの視覚情報を覚えておく 記憶
- 視空間性ワーキングメモリ・・視空間情報を処理しながら保持する 記憶・処理
著書の内容から、〝視空間性ワーキングメモリ″とは、視空間領域に含まれ、情報を記憶し処理する働きのことを指します。
視空間的短期記憶が〝記憶″に特化したものであるのに対して、視空間性ワーキングメモリとは、情報の〝記憶と処理″が含まれます。
例えば、図形問題について考えると、図形を見たままに記憶することが視空間的短期記憶であるのに対して、視空間性ワーキングメモリとは記憶した図形を頭の中で回転させるなど視覚情報の操作も含まれます。
よく学校のテストで、図形の展開図やAの図を180度回転させるとどのような状態になるのかを問う問題がありますが、こうした問題は視空間性ワーキングメモリの力を使っていると言えます。
それでは、視空間性ワーキングメモリと学習活動にはどのような関連性があるのでしょうか?
次に、この点について見ていきます。
視空間性ワーキングメモリと学習活動との関係性について
著書には、視空間性ワーキングメモリを要する学習活動の例が4つ紹介されています(以下、トレイシーら,2023を引用)。
頭の中で算数の問題を解くこと
黒板の文を正しく書き写すこと
写真やイメージを用いてお話すること
順番に並んだ数字の中で抜けている数字を見つけだすこと
以上の4つの内容は、視空間性ワーキングメモリに〝弱さ”があると学習上の困難さとして現れるものだと考えられています。
言語性ワーキングメモリの弱さとは異なり、数や写真、図形など視覚情報を多く使用する情報処理に困難さがでるということです。
例えば、計算問題の苦手さや、数字の桁の間違い、数の大小やイメージの理解の難しさ、文字を飛ばして読む、字が汚い、板書の苦手さや漢字の書き取りの困難さなどがあると言われています。
また、不器用さとの関連性も指摘されています。
例えば、ハサミや定規、コンパス、リコーダー、ピアノなどの道具の使用の難しさもまた視空間性ワーキングメモリの弱さと関連すると言われています。
不器用さと視覚情報処理の困難さを抱える子どもに関しては以下の記事で紹介しています。
関連記事:「発達性協調運動障害と視覚情報処理に困難を抱える子どもたちへの理解と対応」
以上、【視空間性ワーキングメモリとは何か?】学習活動との関連性について考えるについて見てきました。
視空間性ワーキングメモリもまた学習を支える上で大切な力となります。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後もワーキングメモリについての理解を深めていきながら、療育現場で関わる子どもたちに対してワーキングメモリの観点からどのような支援ができるのかを考えていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
非常に関連性の高い記事として、ワーキングメモリに概要と言語性ワーキングメモリに関する記事を以下で紹介しています。
関連記事:「ワーキングメモリの概要:活用されているモデル・学習や発達障害との関連性について」
関連記事:「【言語性ワーキングメモリとは何か?】学習活動との関連性について考える」
ワーキングメモリに関するお勧め書籍紹介記事は以下になります。
関連記事:「ワーキングメモリに関するおすすめ本【初級~中級者向け】」
湯澤正道・湯澤美紀(2017)ワーキングメモリを生かす効果的な学習支援―学習困難な子どもの指導方法がわかる!.学研.
トレイシー・アロウェイ・ロス・アロウェイ(著)湯澤正道・湯澤美紀(監訳)上手幸治・上手由香(訳)(2023)ワーキングメモリと発達障害[原著第2版]: 教師のための実践ガイド.北大路書房.
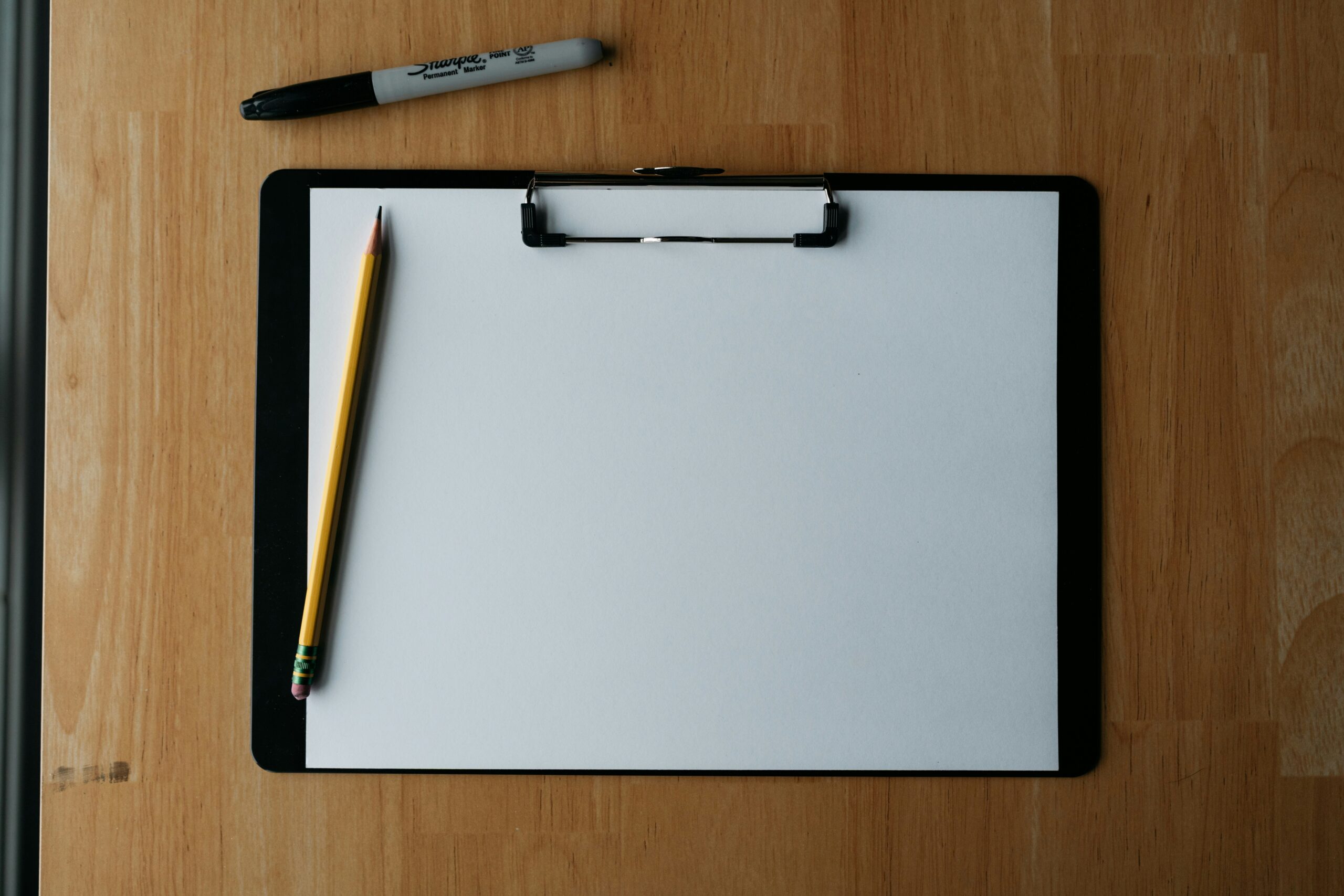

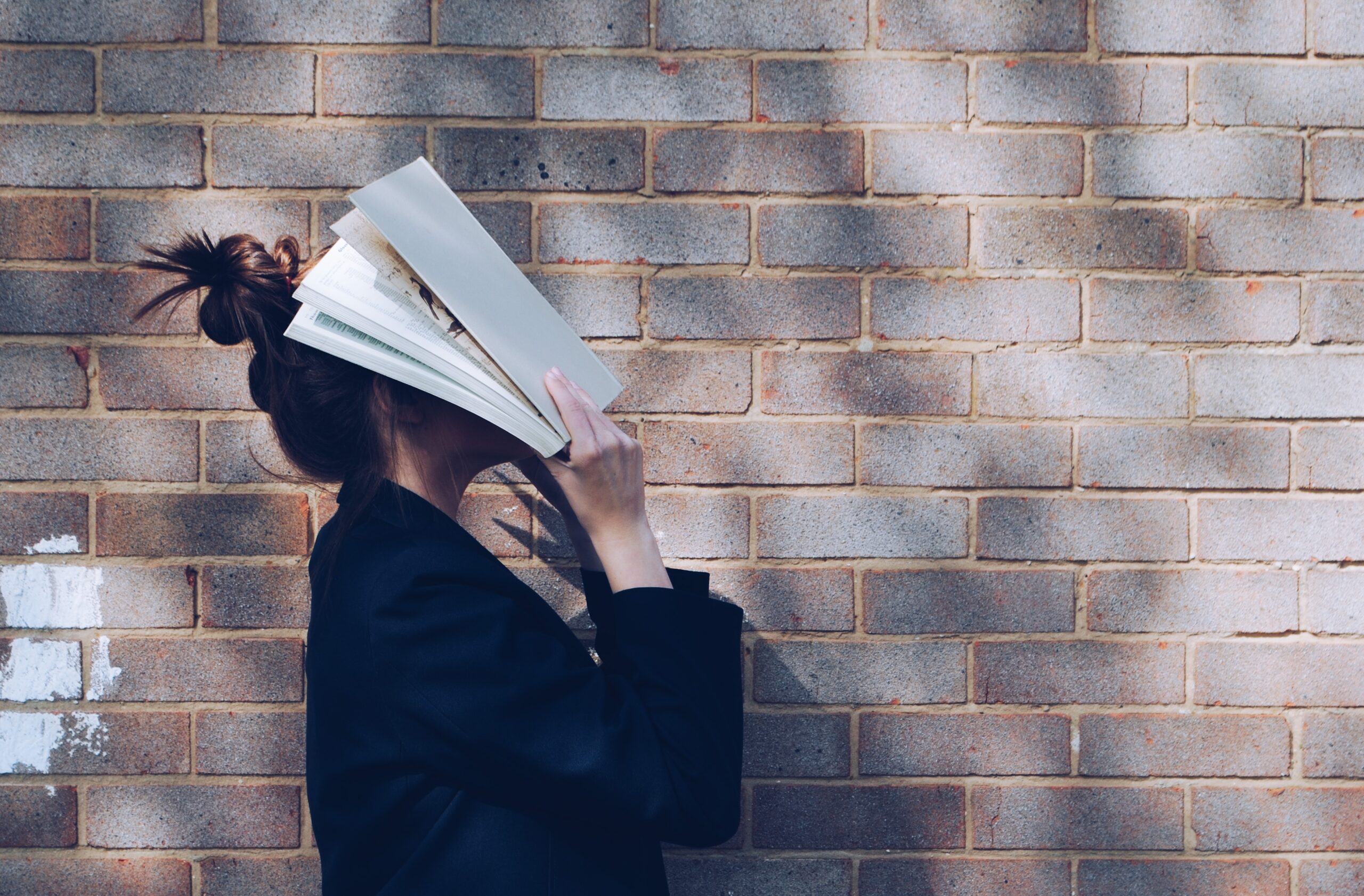
コメント