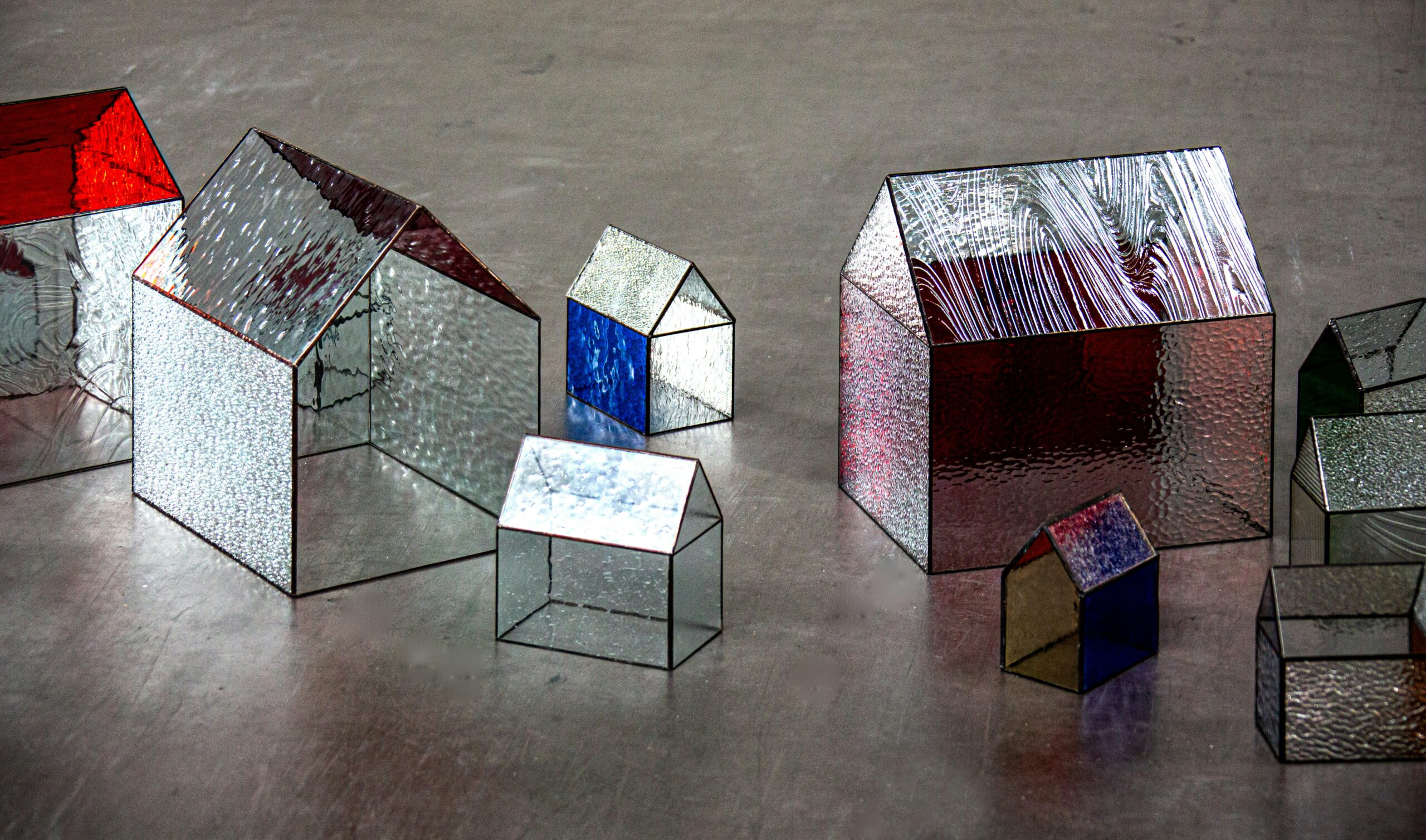
言葉の発達で大切なものに〝象徴機能″があります。
〝象徴機能″とは、〝あるものを別のものに置き換える機能″のことを言います。
例えば、〝車″と言った際に、実際の〝車″のイメージを〝くるま″といった言葉に置き換えるなどがあります。
また、実際の〝車″のイメージを、ブロックを〝車″に見立てて遊ぶことにも〝象徴機能″の働きがあります。
このように、〝象徴機能″は、言葉の発達において大切な役割があります。
それでは、象徴機能を育てていくためにはどのような支援が必要となるのでしょうか?
そこで、今回は、言葉の発達で大切な〝象徴機能″を育てるために必要なこととして、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら考えを深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参照する資料は「小椋たみ子・小山正・水野久美(2015)乳幼児期のことばの発達とその遅れ-保育・発達を学ぶ人のための基礎知識-.ミネルヴァ書房.」です。
〝象徴機能″を育てるために必要なこと
著書の中では、認知機能に困難さを抱えているASD(自閉症スペクトラム障害)への支援として〝象徴機能″からの支援を取り上げています。
ASDの人たちは、ごっこ遊びや見立て遊び、模倣遊びなどを苦手としています。
こうした遊びの背景には、〝象徴機能″といった認知機能(認知発達)が関与しています。
以下、著書を引用しながら見ていきます。
認知発達の観点から象徴機能の発達に向けた支援を行うことがとても大切になってきます。
さらに、著書には、〝象徴機能″の発達への支援において、象徴遊びを通して、子どもが他者を意識し、他者との共有体験から象徴化能力の発達が見られると述べています。
また、ASDの人たちは、様々な情報を統合することにも苦手さがあるため(中枢性統合の弱さ)、こうした点への支援も合わせて行うことが大切だとされています。
以下、引き続き著書を引用しながら見ていきます。
日常の経験の全体性から個々の意味を抽象化し、それを他者と共有することによって、全体の中での子どもが関心を持つパーツをつないでいき、「考える」という面の発達支援となっていきます。それは、自閉スペクトラム症以外の発達障がいのある子どもにとっても大切です。
著書の内容では、他者との共有体験をもとに、その意味を取り出していきながら、それらの部分的な意味としてのパーツを繋いでいくことも大切だと記載されています。
つまり、象徴遊びにより、日常の経験から様々な意味を取り出していきながら、それらの意味を統合していくことも合わせて必要だということです。
著者の経験談
著者の療育現場には、ASDの子どもたちをはじめ、様々な発達に躓きのある子どもたちがいます。
その中で、ASDの子どもたちは、象徴機能といった認知機能に困難さを抱えているという実感があります。
一方で、少しずつですが日々の療育を通して象徴機能の発達が見られることも感じています。
例えば、ごっこ遊びで最初は一人でおもちゃを並べたり、自分なりのストーリーで遊びを進めていた子どもが、大人がその遊びに加わることで、少しずつ大人との共有体験が深まり、遊びが展開していったというものです。
遊びはじめは、子どもの世界観を知るという所からのスタートでしたが、徐々に大人からの提案も混ぜていき、子どもと大人間で様々なイメージを共有していきながら、ごっこ遊びの幅が広がり、ストーリーも多様化していきました。
遊びの中で、子どもの内部には、大人の提案や大人が教えたことが取り込まれていくという感じです。
また、はじめは部分として遊びが完結していたことが、徐々に部分同士が関連性を持ち、ストーリー性が出てきたり、他の人のアイディアや考えなどが取り込まれ繋がっていくといった変化も見られるようになってきました。
このように、象徴機能を育てるために必要なことは、関わる子どもたちの興味・関心をきっかけに、そこから大人と様々な共有世界を広げていけるような関わり方が重要であると感じています。
象徴機能の育ちに大きく貢献する‟ごっこ遊び”ですが、ごっこ遊びを通してイメージ力をうまく引き出すことができたアプローチを著者なりにまとめた記事を以下で紹介しています。
関連記事:「【経験×理論で読み解くごっこ遊び】発達障害児のイメージ力を引き出すアプローチ」
以上、【言葉の発達で大切な〝象徴機能″を育てるために必要なこと】療育経験を通して考えるについて見てきました。
著者は日々の療育で様々なごっこ遊びといった象徴遊びを子どもたちと楽しく行っています。
遊びを通して、子どもたちの中には、イメージする力が高まったり、大人とだけでなく、子ども同士でもイメージを共有したり、新しい遊びのアイディアを提案してくれる子どももいます。
象徴遊びは、子どもたちの内面世界を非常に豊かなものにしていくために不可欠な遊びだと感じています。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も発達支援の現場から、子どもたちと様々なイメージを共有し、イメージする力を育てていけるような取り組みをしていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
象徴機能の発達についてまとめた記事を以下で紹介しています。
関連記事:「【象徴機能の発達について】象徴遊びを捉える3つの視点を通して考える」
象徴機能と関連性の強い言葉の発達を理解する上で役立つ書籍に関する記事は以下になります。
関連記事:「言葉の発達の理解と支援に関するおすすめ本【初級~中級編】」
小椋たみ子・小山正・水野久美(2015)乳幼児期のことばの発達とその遅れ-保育・発達を学ぶ人のための基礎知識-.ミネルヴァ書房.







