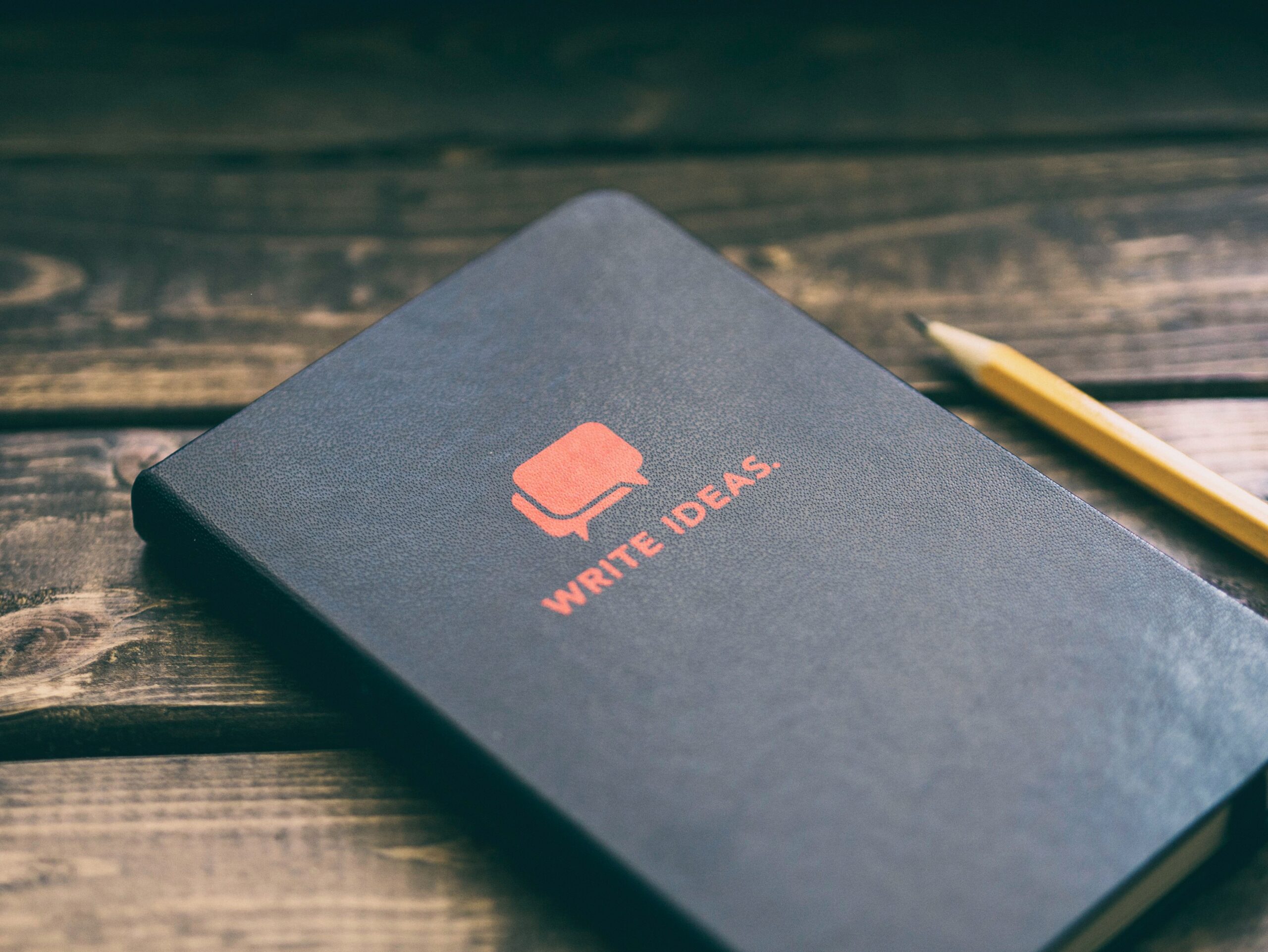
著者は発達障害など発達に躓きのある子どもたちへの療育をしています。
療育での実践を重ねていく中で、子どもたちの発達への理解が年々深まってきているという実感があります。
一方で、療育に関連する知識の収集もまた子どもたちの発達を理解する上で必要不可欠なものだと実感しています。
それでは、実践を重ねていく中で、理論の持つ意味にはどのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、実践を深掘りする理論の重要性について、臨床発達心理士である著者の療育経験から考えを深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
実践を深掘りする理論の重要性について
〝実践″とは、ある対象に〝働きかける″ことです。
一方で、〝理論″とは、まとまった知識の体系のことです。
そのため、〝実践″と〝理論″は、対比的なものとして考えられることもあります。
関連記事:「【理論と実践の関係について】療育現場での実践を通して考える」
著者は療育現場で直接的に子どもたちに〝働きかける″といった経験が多くあります。
こうした療育経験は年数を重ねることで、〝実践知″として自分の中でまとまった知識体系となっていく部分もあります。
一方で、実践だけでは子どもたちの理解が難しいと感じることも多くあります。
例えば、特定の感覚処理が苦手なケース、関係性の構築が難しいケース、行動の背景理解が難しいケース、問題行動を起こす背景要因の理解が難しいケース、遊びを通して子どもたちの発達の意味を理解すること、など様々あります。
以上の例は、理論など、まとまった知識と統合していくと、順に、感覚統合理論、愛着理論、発達障害の特性理解、二次障害の理解、一人遊び集団遊びの意味、と関連づいていきます。
理論を学ぶ前の著者は、子どもたちの理解や対応が難しいケースに対して、経験側的対応を取っていたことが多ったと思います。
また、断片的な知識の学びはしていましたが、浅い知識だけでは子どもたちの理解について、腹落ちした感覚を得られないという感じを長年持ち続けていました。
そして、現場での実践と関連づく理論を見つけても、それを実践経験と統合していき、自分の中で納得できる形となるまでには、時間がかかることも実感としてあります。
しかし、少しずつですが、実践と理論とが統合されていく中で(試行錯誤の中で)、子どもたちの行動の背景を説明する方法が増えてきたこと、そして、新たな問題や課題を見出す力がついてきたなど、自分の実践に自信がもてるようになってきたことも事実としてあります。
子どもたちは個々によって多様な発達が見られます。また、年代や環境・時代の影響も強く受けます。
そのため、どこまで行っても問題や課題は出てくるのだと思います(逆に、周囲が勝手に問題を生んでしまっている側面もあるかもしれません)。
しかし、問題や課題を発見し、その解決方法を見出していくために、実践だけではく、日頃から様々な知識(理論)を学んでいくことが大切だと思います。
日頃から、知識をアップデートしていくことで、実践を深掘りする力、実践から意味を見出す力、実践をまとめ上げていく力、などが加速していくのだと思います。
こうした取り組みの継続が、本当に現場で活用できる〝実践知″となるのだと思います。
以上、【実践を深掘りする理論の重要性について】療育経験を通して考えるについて見てきました。
療育現場での実践を理論と統合していくには、多くの時間がかかるのだと思います。
しかし、統合していく過程の中で得られたものは、自分の中で生涯残り続ける財産になります。
それは、人間の発達への深い理解と問題への解決方法の多さです。
私自身、まだまだ未熟ではありますが、今後も実践と理論の双方を大切にしていきながら、両者を意識的に統合していくためのアウトプット力を鍛えていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。








