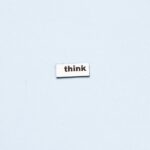発達支援など対人支援に関わる現場で、人と人とが意思疎通をはかりながら共同で取り組んでいくことは、問題解決の場面やより良い職場を作っていくことにおいて大切です。
私自身も発達支援という現場において、他の職員と常に意思疎通をはかりながら問題解決をしているわけですが、その中で後輩へのアドバイスや指導など難しい点もあります。
今回は、発達支援の現場において私の経験から後輩との関わりにおいて大切にしていること気をつけていることなど経験をもとにお伝えしていこうと思います。
私自身、後輩という感覚はあまりなく仲間という意識の方が強い感じがしています。一般的には、職場の経験が自分より短いということから後輩という言葉を使うようにも思いますが、私はあまり先輩や後輩などを意識することが少ないです。そういった中でも、自分より経験値の少ない、あるいは自分の領域に対してあまり詳しくない人たちに対しては、自分の中で必要かつ大切な情報を伝えていくことで相手に対してあるいはお互いにとって有益になるという観点から助言しています。
まずは、私がこれまで後輩と関わる上で苦労した点、うまくいかなかった点を最初にお伝えしていきます。
私が前の職場(療育現場)で、クラスリーダーとしてクラスをまとめる立場での体験です。一緒にクラスを担任していた後輩職員がいましたが、その方(Aさんと仮にします)は私の指示待ちということが多く自分から動くことが少なかった印象でした。こういったことは、私が逆の立場であれば先輩などからそのようにも見られている可能性もあり、先輩後輩間でよくあることだと思います。
Aさんがなかなか自分から動こうとしないことに対して、私は助言(具体的な指示)を多く与えました。そうすると、指示待ちになることが増え、逆に、自由に考え行動できるように助言の量を減らすと何をしていいのかわからなく動きが止まる様子が増えました。
療育現場はクラスにもよりますが、体制的に決して余裕のある状態ではなく、一人が自分で考え声を掛け合いながら動かないと全体としてうまく機能しないことが度々起こります。そのため、自分で考え行動するということが大切になります。それは、新人でも求められる能力でもあります。
また、Aさんはあまり自分から発信することが少なく、一見何を考えているのかわからないことが多くありました。何に興味あり、得意なことは何かなど見えにくい印象でした。
Aさんへの指導に悩み、なかなか活路が見いだせずにいたわけですが、そういった悪循環が数か月続き、私はAさんが自発的に考え行動してもらうにはどうすべきか他の職員の力も借りながら考えました。
そうした中で意識して取り組んだこととして、以下のことがあります。この内容はやりながら修正した点も多くあり、結果としての面が強いかもしれません。
①一緒に考えていこうという姿勢を見せる。具体的には、自分の疑問点や感じたことなどを積極的に発信する。
②後輩の意見を引き出してそれに耳を傾ける。その際、大切なことは否定しない、否定ではなく提案をする。
③何かできそうなものを最後まで任せてみる。その際、大切なことは頑張った過程を褒める、失敗を追求しない、失敗した時には解決方法を一緒に考える。
④成長していく過程には個人差があることを認識する。焦らずじっくりと見守る。
⑤自分が困った時は他の人に頼る。他の協力抜きには自分も不安定になる。
⑥雑談を大切にする。
こうした内容を事前・事後的に大切にしてきたわけですが、こうした取り組みを通してAさんがどう変わったかをお伝えしていこうと思います。
Aさんとは、とにかく雑談を大切にしました。以外に思われるかもしれませんが、雑談以上に効果があったものはなかったのではと後々振り返ることがあります。特に子供たちとその日にあったエピソードを面白可笑しく話すとAさんの子供たちに対する優しさや、Aさんなりの視点などが見えてくることがありました。
それをもとにAさんの考えを深堀したり、クラスとして何をやっていきたいのかなど話を発展させていきました。もちろん、一緒に考えるという姿勢を大切に提案することをベースとしました。
Aさんに大きな変化を感じたのは、ある活動をAさんに完全に任せたことでの成功体験です。その過程をポジティブにフィードバックすることで、自分から動こうとする様子も増えてきました。
それを見て、人それぞれ得意なところや強みがあり、それを時間をかけて伸ばしてあげようとする姿勢が大切であると実感しましたし、私自身に心の余裕がないといけないとも思いました。それは、現在の自分の限界を知ることでもあります。そして、人に相談し頼ることでもあります(私も多くの職員に支えていただきました)。
こうした後輩とのやり取りを通して痛感するのは、人を育てることの難しさです。人の成長はそれぞれの速度があります。私自身が気をつけないといけないのは、そうした成長の邪魔をしないような関わりをするということです。そして、私自身がまだまだ未熟だと感じ、日々前進する姿勢を示しているかということも大切です。
人は経験値が増えると、それをもとに判断すること増え、新しいことへの挑戦などが少なくなることがあります。後輩に向けて自分が最大限にできることは、何かに全力で取り組む姿勢を見せ続けることなのかもしれません。そのような状態でいれるように今後も挑戦する姿勢を忘れないようにしていきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。