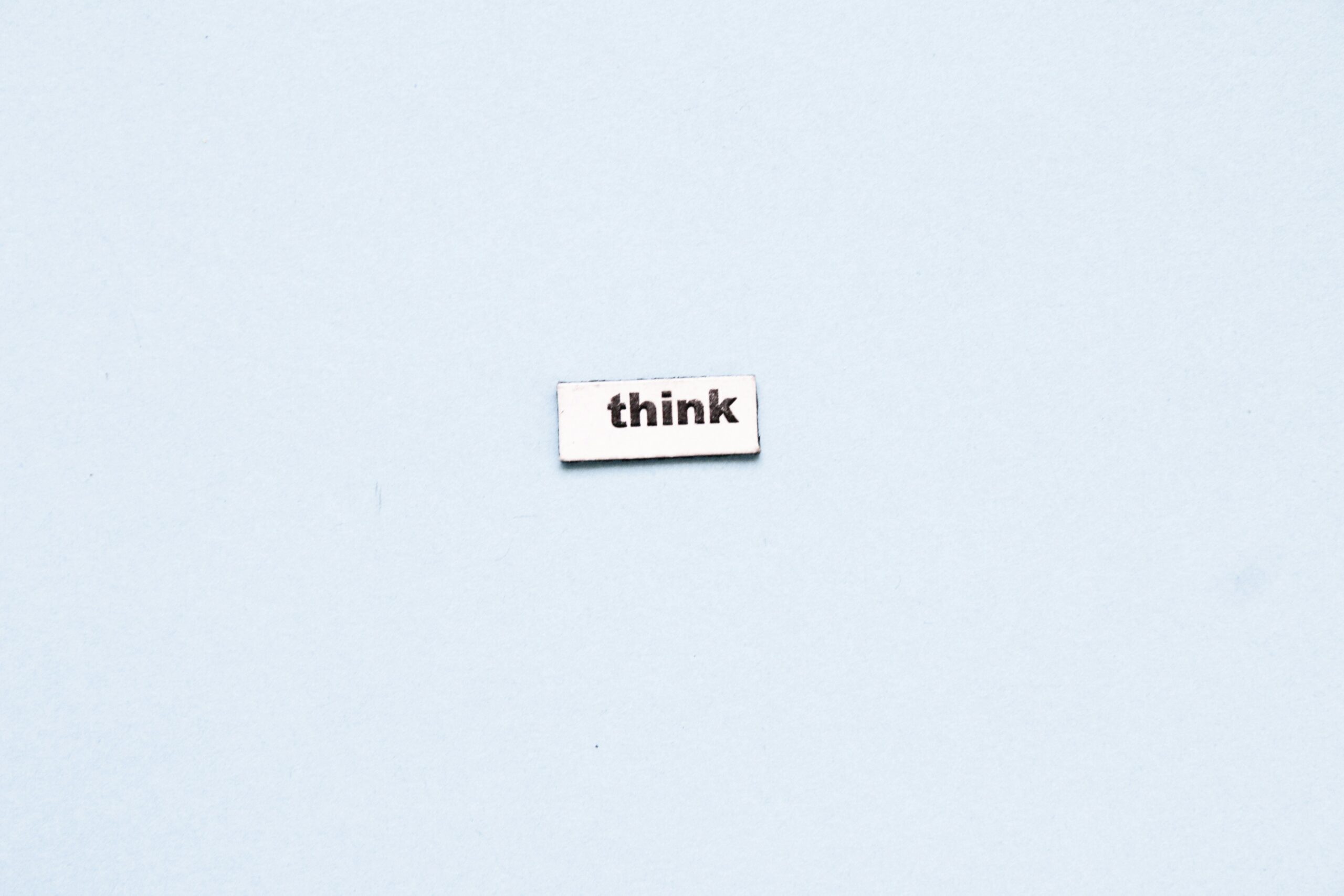
発達支援(療育)の現場で発達に躓きのある子どもたちと接しているとよく耳にする言葉に「支援」があります。
発達支援に携わる身として、一言で「支援」といってもその意味合いはとても広く、深いものだと思います。
それでは、発達支援の「支援」とは一体どのようなことを指すのでしょうか?
今回は、著者の療育経験も踏まえ、発達支援の「支援」とは何かについて考えていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回、参照する資料は「田中康雄(2011)こころの科学叢書:発達支援のむこうとこちら.日本評論社.」です。
発達支援の「支援」とは何か?
以下、著者を引用します。
僕は、支援の根幹に、生きづらさへの生活支援を置きたいと考える。支援する標的は、生活様式といった社会的な枠組みではなく、さまざまな生活を営むその人の「生きている過程」である。そこでは、現在から未来に向けて「発達していくこと」への関わりを大切にしたい。
著書の内容では、「支援」を本質的な意味で、生活で生じた困り感・生きづらさを支えるものと捉えています。
そして、現在から未来に向けた時間軸での関わりもまたその中に含まれると指摘しています。
もちろん「支援」には、具体的なものに、ソーシャルスキルトレーニングや認知行動療法、運動療法など技術的なものもあります。
一方で、今回は、もっと広義な意味として、発達障害を生活障害と置き換えた際に、その人の困り感や生きづらさを応援する、その人の人生を支えるという意味で「支援」という言葉を活用しています。
それでは、上記のように「支援」を捉えた際に、どのような関わり方が発達支援(療育)で必要になるのでしょうか?
次に、著者の経験談についてお伝えします。
著者の経験談
著者は長年療育現場で発達に躓きのある子どもたちと関わってきています。
子どもたちの状態像は、その子の個人の要因と環境要因といった相互性から、生活で生じる困り感・生きづらさも変化してきます。
そのため、現場では、その時その時の対応策を講じていく必要があります。
その時に大切な視点として、今の関わりが長い人生においてどのような意味があるのかを考えて関わることだと思います。
例えば、未就学児では、大人との信頼関係がとても重要な発達課題です。
幼い頃の大人から愛され安全と安心感を与えられた子は、自らの内部に自他に対する肯定的な表象(イメージ)を形成すると言われています。
それが、後の対人関係に影響するなど生涯に渡って大切な対人関係の鋳型になります。
著者が関わる子どもたちの中には、こうした大人との信頼関係をうまく獲得できている子どもたちは、情緒が安定し、他者を信頼し、自己を肯定する傾向があるように見えます。
学童期では、同年代集団との関わりから獲得する自己肯定感・自尊心・自己有能感とった感情が大切な課題です。
著者も学童期の子どもと関わることが多くありますが、高学年になるにつれて友だち意識が増し、その中で自分の立ち位置や役割など他者から見られる自分を再度自己の中に構築するようになります。
その中で、同年代集団とうまく関わることができた経験は、自己肯定感などに繋がり、その後、様々な対人関係を築く基盤となります。
著者が関わる子どもにも、対人関係を築き、その中でうまく関わることができたことで自信を獲得したケースも多くあります。
その他、全ライフステージに関わるものとして、人生における楽しみがあるかということです。
興味関心の獲得は、つらいことも頑張れる、人生が豊かになる、仕事に繋がるなど、人それぞれ内容は異なるかと思いますが、重要な課題だと考えます。
著者も療育現場で、子どもたちの興味関心を育むことをとても大切にしています。
興味関心が満たされると、そのエネルギーが蓄積し、次の行動の原動力になっているといった印象があります。
そのため、療育現場で遊びが満足している子どもたちは、次回への期待や満足感・達成感の表情を浮かべて帰宅しているように感じます。
このように、「支援」と言えば、何か特別な取り組みをしているわけではなく、その人の生活を長期のスパンをもってイメージしながら日々を支え、そして、その人の人生がより豊かになるような関わりをしていくことだと思います。
以上、発達支援の「支援」について、お伝えしてきました。
もちろん「支援」には、こうした内容以外にも様々な取り組みがあるかと思います。
私自身、まだまだ未熟ですが、発達支援の現場を通して、今度も「支援」の意味について実践を通して学んでいきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
支援の充実に関して〝発達的視点”もまた大切なヒントになります。この点に関しては以下の記事で詳しく紹介しています。
関連記事:「【支援の質を変える発達的視点】人を理解するための経験×理論の融合」
田中康雄(2011)こころの科学叢書:発達支援のむこうとこちら.日本評論社.









