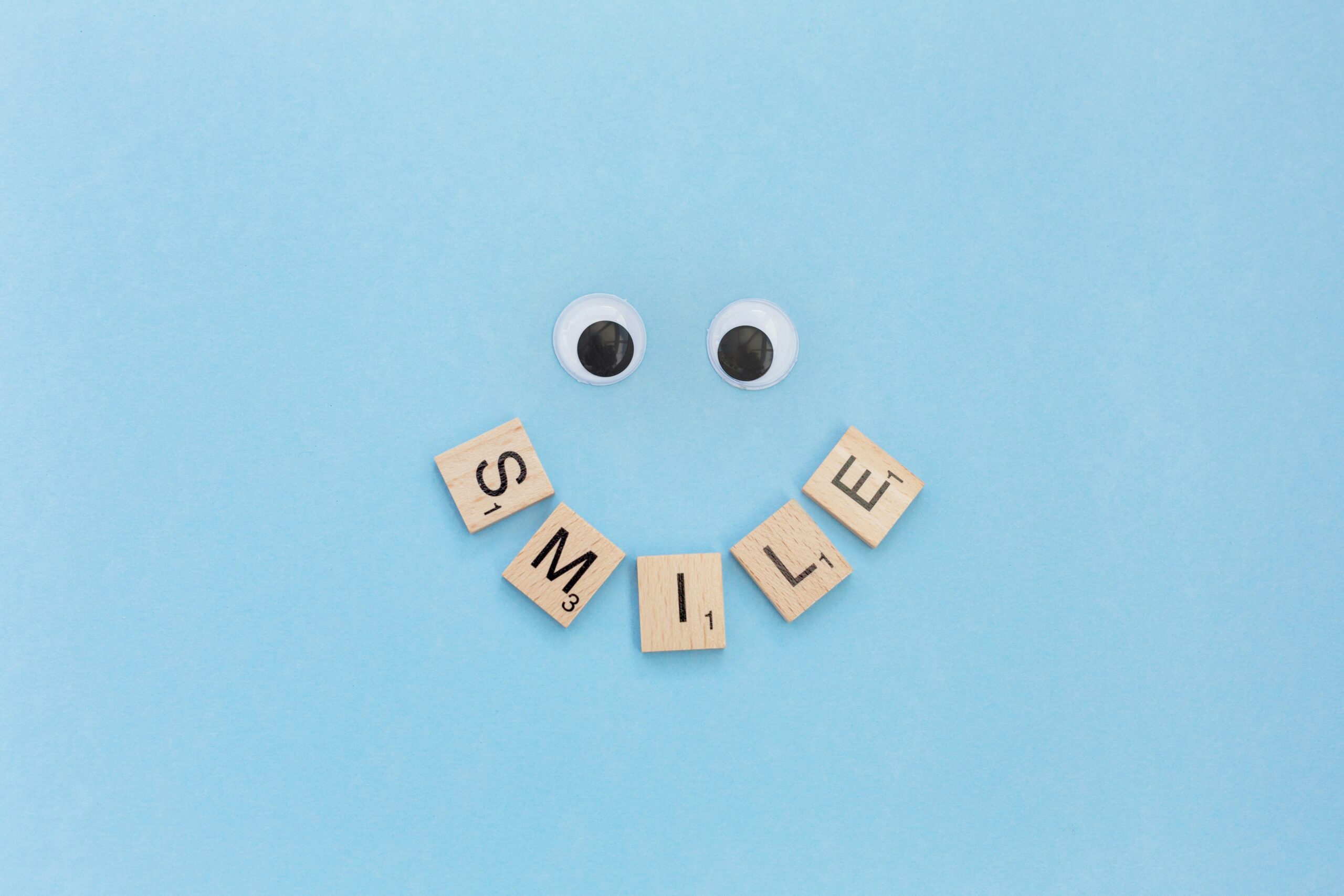
療育(発達支援)の現場に携わっていると、子どもたちの困った行動や気になる行動などにどうしても目が向いてしまうことが多くあります。
もともと、発達に躓きのある子どもたちということもありますので、まず大切となるのは、発達の躓きを、発達的な視点や発達特性なども含め周囲との環境の中で、どこに困り感を本人が持っているのかを周囲が理解し配慮していくことです。
課題となるのは、こうした発達理解を進めていく中で、困った行動や気になる行動の背景が少しずつ分かってきた中で、何を大切に対応していくかです。
そこで、今回は、著者の療育経験も踏まえて、発達支援を進めていく中で、「制限」よりも「満足感」を持たせることの大切さについてお伝えします。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
「制限」のメリット
・リスク回避に繋がる
「制限」するとは、子どもたちの困った行動や気になる行動に対して、守るべきルールなどを提示することです。
例えば、○○遊びのルールなど、著者の療育現場でも外遊びや集団遊びの際などには行います。この場合の制限とは、禁止事項という意味合いですので、どうしても、ダメ、×などの視点が強くなります。
こうした制限を加えることで短期的にはリスク回避には繋がります。
・事故を防ぐ・命を守る
問題行動や他児とのトラブルは時に事故や命に関わるものにまで発展しかねません。
こうした事故や怪我、命に関るものに対しては制限を作る必要があります。
例えば、公園遊びで危険行為をするなど、著者の療育経験の中でも時々見られました。
また、放課後等デイサービスでは、車内でのルールを守ることがとても大切です。著者の現場では、走行中に車のハンドルを急に動かそうとするなどの事例もあったため、こうした事故や命に直結するものは、すぐに制限をかける必要があります。
著者が今回強くお伝えしたかったのは、「満足感」の方です!
それでは、次に「満足感」の大切さについて見ていきます。
「満足感」のメリット
・「満足感」を与えると問題行動や気になる行動が減る
子どもたちの困った行動や問題行動には様々な背景があります。
そのため、こうした行動に制限を加えたくもなりますが、大切なことは、同時に「満足感」を、それ以上に与えるということです。
満足感を与えるためには、子どもたちの普段の様子や、その時々の気持ちの状態を深く感じながら対応することが必要になります。
そのため、関わるスタッフには、多くの集中力などエネルギーが必要になります。
しかし、そうして使ったエネルギーが子どもたちに伝搬し、「楽しかった!」と帰り際などに聞くと関わるスタッフにも達成感と次回への活力が湧いてきます。
もちろん、問題行動を起こしやすい子どもに対しては、「満足感」をもってもらうためには、関わるスタッフがチームで協力していく姿勢、そして、その子に対して長期的な展望を持って支援に関わることが重要です。
また、満足感を与えるためには、子どもたちの興味関心を探る視点、共感する視点、創造する視点なども大切になります。
子どもたちは自分の興味のある世界を他者と共感することで、心が充足していきます。
著者もこれまで、問題行動をよく起こす子どもと関わってきましが、その中で感じたこと、学んだことが多くあります。
それは、その子の生きにくさを感じることや、難しい状態でも繋がりや喜びを共感し合えた体験、日々の地道な関わりが長期の子どもの成長に繋がっているといった経験、チームの力がとても重要だと実感した経験などです。
こうした様々な学びの中において、子どもの「満足感」を活動で共有できたという経験が常に関与しているのだと思います。
そして、「満足感」を多く持つことで、子どもの問題行動や気になる行動は減っていくという実感があります。
関連記事:「「愛情の器モデル」とは【愛情のエネルギーを満たすことの重要性】」
問題行動や気になる行動への「制限」は時には重要です。
しかし、それ以上に、子どもの「満足感」を探す、共有する、作ることが子どもたちの成長においてとても大切です。
著者も疲れている時やエネルギーが不足しているときなど、どうしても「制限」からの対応が頭に浮かんでしまいますが、長いスパンを考えた際に「満足感」を持たせるという関わりがとても大切だということを常に念頭において支援に携わっていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。









