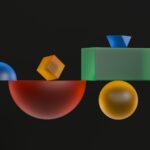DSM-5によると、自閉症(自閉症スペクトラム障害:ASD)の診断基準としてには以下の2つがあります。
①持続する相互的な社会的コミュニケーションや対人的相互反応の障害
②限定された反復的な行動、興味、または活動の様式
そして②は「こだわり行動」とも言われ、自閉症を代表する特徴の一つです。
それでは、「こだわり行動」には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、自閉症のこだわり行動:限定した興味と反復行動について、臨床発達心理士である著者の経験談も交えながら理解を深めていきたいと思います。
※この記事は、臨床発達心理士として10年以上療育現場に携わり、修士号(教育学・心理学)を有する筆者が執筆しています。
今回参考にする資料として、「公認心理師のための「発達障害」講義」を取り上げていきます。
【自閉症のこだわり行動:限定した興味と反復行動について】療育経験を通して考える
①新しいことや変化を怖がる
①新しことや変化を怖がる
幼児期:初めての食べ物には手をつけたがらない。母親が髪型を変えると怖がる。家具の位置を元に戻そうとする。
児童~成人期:新しいことなど変化があると落ち着かない。予定が変わると混乱する。
著者の実体験
子どもたちと接していると、マスクを外そうとしたり、メガネを取ろうとする子もいます。また、扉を必ず閉めたり、物を元の場所に直ぐに戻そうとするお子もいます。
大人であると、急な変更に対して、混乱するなど不安な様子が増えることが多いため、できるだけ事前に伝えるようにしています(子どもも同様です)。
②自分なりのやり方や手順を変えられない
②自分なりのやり方や手順を変えられない
幼児期:食べる順番や道順が決まっている。
児童~成人期:臨機応変、応用、汎化する力が弱い、完璧主義。
著者の実体験
子どもたちの中で、送迎などで道順がいつもと違うと混乱する子もいます。物事の手順や順番にはその人なりのやり方が多いといった印象もあります。
大人であると、自分なりのやり方があり、そのペースを維持したく、なかなかその状況に応じて臨機応変な対応が難しい人もいます。
③切り替えが苦手
③切り替えが苦手
幼児期:一度ぐずるとなかなか気分が変わらない。
児童~成人期:気分の落ち込みが長引く、「こうあるべき」「○○すべき」思考。
著者の実体験
切り替えが苦手な子は多くいます。何かが中断されたことに腹を立てて気持ちを切り変えられない、時間がきて次の行動に移るのに時間がかかるため、事前に見通しなどを伝えることを大切にしています。
大人であると、「こうあるべき」「○○すべき」思考の方もいるため、本人にとって納得のいく説明を論理的に伝える工夫をしています。
④独特な身体の使い方
④独特な身体の使い方:ぴょうんぴょん跳ぶ、手をひらひらさせる、ロッキング
著者の実体験
著者が見てきた子どもの中で、はねたり、一人で手をひらひらさせたりする子どもは時々見受けられます。また、椅子でロッキングしており、椅子ごと倒れた子もいました。どちらかというと、高機能の子どもよりかは、知的に遅れのある子どもに多い印象があります。
⑤細部に目がいきやすい、全体把握が苦手
⑤細部に目がいきやすい、全体把握が苦手
幼児期:車の玩具の車輪を回して遊ぶ
児童~成人期:仕事の全体を捉えて計画を立てることができない
著者の実体験
子どもの中で車輪マニアという子どもがおり、何でも車輪を回そうとして、車輪が回っている様子をじっとみたり、車輪が回る様子を見てテンションが上がる子どももいます。
大人であると、仕事の全体像をとらえることが苦手な人が多くいる印象がりあます。そのため、早めに取り組むべき課題を整理したり、要点(ポイント)などを伝えるようにしています。
⑥感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または感覚側面に対する並外れた興味
⑥感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または感覚側面に対する並外れた興味:合唱の声を嫌がる、くるくる回るものを見入る
著者の実体験
過敏さ鈍感さは子どもから大人までよく見られます。例えば、特定の音、例えば、子どもの泣き声、掃除機の音、工事音などが苦手な人もいます。耳栓やイヤマフなどで対応している人もいます。
以上、【自閉症のこだわり行動:限定した興味と反復行動について】療育経験を通して考えるについて見てきました。
今回見てきた内容は、一例になり、まだまだ他にもあります。
著者は、療育現場に携ってだいぶ年月が経つため、上記の内容に関しては当たり前な行動として見れるようになっていますが、療育に関わり始めた当時は多くの疑問や不思議な感覚がありました。
こうしたこだわり行動(限定した興味と反復行動)は自閉症の人を理解するためにとても重要です。理解しなければ、適切な配慮ができないからです。
私自身、これからもより良い発達理解と発達支援ができるように、様々な発達特性への理解を学んでいきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
自閉症に関するお勧め書籍紹介
関連記事:「自閉症に関するおすすめ本【初級~中級編】」
下山晴彦(監修)(2018)公認心理師のための「発達障害」講義.北大路書房.